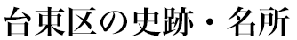01. 黙阿弥と浅草(もくあみとあさくさ)
浅草1-36
歌舞伎作者河竹黙阿弥(1816~1893)は文化13年(1816)江戸日本橋の商家に生まれ、かぞえて20歳のとき五世鶴屋南北に入門、78歳で歿するまでに360篇にのぼる作品を残した。
天保の改革による江戸三座の猿若町移転に伴ってこの地に移り住んだのは、弘化4年(1847)の30歳ごろから明治20年(1887)、本所南二葉町いまの墨田区亀沢に隠棲するまでの約40年間である。宇都谷峠・十六夜清心・三人吉三・弁天小増・村井長庵・御所の五郎蔵・髪結新三・河内山と直侍・鳥ちどり・魚屋宗五郎・土蜘・船弁慶・紅葉狩などの代表作をはじめ、ほとんど全作品がここで書かれたのであった。
坪内逍遥は黙阿弥を「真に江戸演劇の大間屋なり……一身にして数世紀なり」と評し「日本の沙翁」とも讃えたが、馬道町2丁目12番地といったこの地が浅草寺子院正智院の境内だったので、江戸、東京の市民からは「地内の師匠」と親しまれたという。

02. 鎮護堂(ちんごどう)
浅草2-3 浅草(せんそう)寺
鎮護堂は「おたぬきさま」の名で親しまれ、防火、盗難除、商売繁栄の守護神として知られている。
明治5年(1872) 、浅草寺境内に住みついた狸の乱行を鎮めるため、浅草寺の用人であった大橋亘(おおはしわたる)が浅草寺貫首唯我韶舜(ゆいがしゅうしゅん)と相談の上、自身の邸内に祀ったことがはじまりと伝える。数度の移転を経て、同16年(1883)伝法院の当地に再建した。
現在の入母屋造(いりもやづくり)の本殿は、大正2年(1913)に再建されたものである。
祭礼は、毎年3月17・18日に行われている。
また、境内には昭和38年(1963)に建てられた幇間塚(ほうかんづか)がある。幇間のことを「たぬき」と呼んだことから、この地に建てられたもので、碑には幇間の由来と久保田万太郎の「またの名のたぬきづか春ふかきかな」の句が刻まれ、裏面には幇間一同の名が刻まれている。

03. 至徳の古鐘(しとくのこしょう)
浅草2-3 浅草(せんそう)寺
この梵鐘は、「至徳二年丁卯五月初三日」と刻字されているので、至徳4年(1387)の鋳造である。至徳は南北朝時代、北朝の後小松天皇の年号。南北朝時代鋳造の鐘は東京都では珍しく、都内有数の古鐘として、特に「至徳の古鐘」と呼ばれている。当初、浅草寺の鐘として彫像されたものではなく、武蔵国多西郡または騎西郡、あるいは相模国西郡のいずれかの寺にあったものを、のち浅草寺に移したと推察されている。
江戸時代、この鐘は、随身門(現在の二天門)北側、浅草神社東南隅の鐘楼上に掛けられていたが、明治初年の神仏分離令により、現在地の伝法院邸内に移された。昭和24年(1949)5月28日、重要美術品の認定を受けている。[非公開]
浅草2-3 浅草(せんそう)寺
この梵鐘は、「至徳二年丁卯五月初三日」と刻字されているので、至徳4年(1387)の鋳造である。至徳は南北朝時代、北朝の後小松天皇の年号。南北朝時代鋳造の鐘は東京都では珍しく、都内有数の古鐘として、特に「至徳の古鐘」と呼ばれている。当初、浅草寺の鐘として彫像されたものではなく、武蔵国多西郡または騎西郡、あるいは相模国西郡のいずれかの寺にあったものを、のち浅草寺に移したと推察されている。
江戸時代、この鐘は、随身門(現在の二天門)北側、浅草神社東南隅の鐘楼上に掛けられていたが、明治初年の神仏分離令により、現在地の伝法院邸内に移された。昭和24年(1949)5月28日、重要美術品の認定を受けている。[非公開]

04. 伝法院(でんぼういん)
国名勝・国指定重要文化財
浅草2-3 浅草(せんそう)寺
伝法院は浅草寺の貫首(かんす)が居住する本坊の称号である。客殿は安永5年(1776)、玄関は翌6年(1777)の建築である。客殿は大規模な方丈形式の建物で、仏壇を広く構える内陣3室を並べた平面構成に特徴があり、本尊阿弥陀如来坐像(台東区指定文化財)を安置する。6月の山家会(伝教大師の忌日法要)、11月の霜月会(天台大師の忌日法要)をはじめ、故人の追善供養、寺内徒弟の加行(けぎょう)などが行われる。台所・小書院・大書院・新書院は明治後期から大正期に復興した建造物である。伝法院の主要建物6棟は平成27年(2015)に国重要文化財に指定された。
建物の背後には、大池泉を中心とする池泉庭園があり、江戸時代初期の作庭と考えられている。伝法院庭園として平成23年(2011)に国名勝に指定された。池畔には京都表千家の茶室、不審庵(ふしんあん)を模した天祐庵(てんゆうあん・東京都指定文化財)がある。[非公開]

05. 添田 唖蝉坊碑・添田知道筆塚(そえだあぜんぼう・そえだともみちふでづか)
浅草2-3 浅草(せんそう)寺
添田唖蝉坊 本名平吉、筆名は添田 唖蝉坊の他、不知山人、のむき山人、凡人など。神奈川県大磯に生まれる。昭和19年(1944)2月8日歿。享年73歳。明治20年代に壮士節の世界に入り、のち演歌の作詞作曲、演奏に従事。作品は、「四季の歌」「ストライキ節」「ラッパ節」「あゝ金の世」「金色夜叉の歌」「むらさき節」「奈良丸くづし」「マックロ節」「青島節」「ノンキ節」「生活戦線異状あり」など。著書に『浅草底流記』『唖蝉坊流生記』『流行歌明治大正史』ほか。
添田知道 唖蝉坊の長男。東京出身。昭和55年(1980)3月18日歿。享年77歳。父唖蝉坊とともに演歌の作詞、作曲に従事したあと作家活動に入る。筆名は知道の他、さっき、吐豪。演歌作品に「東京節」「復興節」「ストトン節」など。著書に新潮文芸賞受賞の長編小説『教育者』『利根川随歩』『演歌の明治大正史』などがある。

06. 松尾芭蕉の句碑(まつおばしょうのくひ)
浅草2-3 浅草(せんそう)寺
くわんをんの
いらか見やりつ
花の雲 はせを
俳諧紀行文『奥の細道』などを著した松尾芭蕉は、寛永21年(1644)伊賀上野(現三重県上野市)に生まれました。
芭蕉という俳号は、深川の小名木川のほとりの俳諧の道場「泊船堂」に、門人が芭蕉一枚を植えたことに由来します。独自の蕉風を開き「俳聖芭蕉」の異名をとった松尾芭蕉は、元禄7年(1694)10月12日、大阪の旅舎で51年の生涯を閉じました。
この句碑は寛政8年(1796)10月12日、芭蕉の一〇三回忌に建立され、元は浅草寺本堂の北西、銭塚不動の近くにありましたが、戦後この地に移建されました。
八十三歳翁泰松堂の書に加えて、芭蕉のスケッチを得意とした、佐脇嵩雪が描いた芭蕉の座像が線刻されていますが、碑石も欠損し、碑面の判読も困難となっています。
奥山庭園にある「三匠句碑」(花の雲 鐘は上野か浅草か)と共に、奇しくも「花の雲」という季語が詠みこまれています。

07. 時の鐘(浅草寺)(ときのかね)
台東区有形文化財
浅草2-3 浅草(せんそう)寺
江戸時代、人々に時刻を知らせる役割を果たしていたのが時の鐘である。当初、江戸城中にあったが、江戸市街地の拡大にともない日本橋本石町にも設置され、さらには浅草寺や寛永寺(上野山内)など、9箇所でも時を知らせた。
鐘の大きさは、高さ2.12メートル、直径1.52メートル。鐘銘によれば、撰文は浅草寺別当権僧正宣存で、元禄5年(1692)8月、五代将軍徳川綱吉の命により、深川住の太田近江大掾藤原正次が改鋳し、その費用として下総(現千葉県)関宿藩主牧野備後守成貞が黄金2百両を寄進した。
この鐘は、時の鐘として、あるいは浅草寺の梵鐘として、さまざまな文学作品にも登場しているが、中でも松尾芭蕉の句、
花の雲 鐘は上野か浅草か
は、あまりにも著名である。
昭和20年(1945)3月の東京大空襲で火を浴びたが無事に残り、今なお昔のままの姿を見せている。なお、鐘楼は同空襲で焼け落ち、昭和25年(1950)5月に再建されたものである。

08. 二尊仏(にそんぶつ)
銅造観音菩薩坐像・銅造勢至菩薩坐像、台東区有形文化財
浅草2-3 浅草(せんそう)寺
「濡れ仏」の名で世に知られるこの二尊仏は、観音(右)、勢至(左)二菩薩の金銅坐像で、像の高さは共に2.36メートル、蓮台を含めれば4.54メートルにおよぶ。基壇の組石は、長さ約12メートル、幅6.21メートル、高さ1.5メートルとなっている。
蓮弁台座銘によれば、願主は上野国(現群馬県)館林在大久保村の高瀬善兵衛。かつて奉公した日本橋伊勢町の米問屋成井家より受けた恩を謝し、観音像は、旧主善三郎の菩提を弔うため、勢至像はその子次郎助の繁栄を祈るため、貞享4年(1687)8月に造立した。
江戸時代初期の優秀な鋳造仏の一つで神田鍋町の太田久衛門正儀の作。
安永6年(1777)2月高瀬仙右衛門が施主、千住の高瀬奥右衛門が願主となり、修理したことが観音像銘に追刻されている。

09. 久米平内堂(くめのへいないどう)
浅草2-3 浅草(せんそう)寺
久米平内は江戸時代前期の武士。『武江年表(ぶこうねんぴょう)』によると、天和3年(1683)に没したとされるが、その生涯については諸説あり、実像は明らかではない。
平内堂には次のような伝承がある。平内は剣術に秀でており、多くの人をあやめてきた。後年、その供養のために、仁王坐禅の法を修行し、浅草寺内の金剛院に住んで禅に打ち込んだという。臨終にのぞみ自らの姿を石に刻ませ、多くの人々に踏んでもらうことによって、犯した罪を償うために、この像を人通りの多い仁王門付近に埋めたと伝える。
その後、石像はお堂に納められたという。「踏付け」が「文付け」に転じ、願文をお堂に納めると願い事が叶うとされ、江戸時代中期以降、とくに縁結びの神として庶民の信仰を集めた。
平内堂は、昭和20年(1945)3月の戦災で焼失した。現在のお墓は同53年(1978)10月に浅草寺開創 1350年記念として再建されたものである。

10. 宝蔵門(ほうぞうもん)
浅草2-3 浅草(せんそう)寺
宝蔵門は、大谷米太郎(おおたによねたろう)の寄進で、昭和39年(1964)に浅草寺宝物の収蔵庫を兼ねた山門として建てられた。鉄筋コンクリート造で重層の桜門である。外観は旧山門と同様に、江戸時代初期の様式を基準に設計されている。高さ21.7メートル、間口21.1.メートル、奥行は8.2メートルある。下層の正面左右には、錦戸進観(にしきどしんかん)・村岡久作(むらおかきゅうさく)の製作による、木造仁王像を安置している。
浅草寺山門の創建は、『浅草寺縁起』によると、天慶5年(942)、平公雅(たいらのきみまさ)によると伝える。仁王像を安置していることから仁王門とも呼ばれる。その後、焼失と再建をくり返し、慶安2年(1649)に再建された山門は、入母屋造(いりもやづくり)、本瓦葺の桜門で、昭和20年(1945)の空襲で焼失するまでその威容を誇っていた。

11. 二天門(にてんもん)
重要文化財
浅草2-3 浅草(せんそう)寺
この二天門は、慶安2年(1649)頃に浅草寺の東門として建立されたようであるが、江戸時代を通じて浅草寺観音堂の西側に建てられた東照宮の随身門と伝えられ、随身像が安置されていた。なお、浅草寺の東照宮は元和4年(1618)に建立されたが、寛永8年(1631)と同19年(1642)の火災によって、浅草寺の他の諸堂とともに焼失し、その後東照宮は江戸城内の紅葉山に移された。
明治初年の神仏分離令によって門に安置された随身像は、仏教を守護する四天王のうち持国天・増長天の二天像に変わり、名称も二天門と改称した。
現在安置されている二天像は、京都七条の仏師、吉田兵部が江戸時代初期(17世紀後半)に製作したもので(東京都指定有形文化財)、昭和32年(1957)に寛永寺の厳有院殿(四代将軍徳川家綱)霊廟の勅使門から移されたものである。
二天門は昭和25年(1950)、国指定重要文化財に指定された。

12. 川口松太郎句碑(かわぐちまつたろうくひ)
浅草2-3 浅草(せんそう)寺
川口松太郎ハ明治三十二年十月一日浅草今戸ニ生レル 昭和十年第一回直木賞受賞ノ『鶴八鶴次郎』ヲ初メトシテ小説脚本ニ名作多ク文壇劇団ニ多大ナ足跡ヲシルス 特ニ新派俳優花柳章太郎水谷八重子等ニヨッテ演ジラレタ情緒豊カナ諸作品ハ観客ヲ魅了ス 這般ノ功績ニヨリ三十八年菊池寛賞受賞 四十年芸術院会員 更ニ四十四年『しぐれ茶屋おりく』ノ一篇ニヨリ吉川英治文学賞受賞 四十八年文化功労者ニ叙セラレル 最晩年渾身ノ筆デ連載小説『一休さんの門』ヲ脱稿後昭和六十年六月九日永眠ス 行年八十五才 三回忌ニ因ミ故人ノ終世ノ師久保田万太郎ノ傍ラニ同ジク句碑ヲ建テテ逝者ヲ偲ブ
生きると いうこと
むずかしき 夜寒かな

13. 粧太夫碑(よそおいだゆうひ)(蕋雲女史書の柿本人麻呂歌碑)
浅草2-3 浅草(あさくさ)神社
ほのぼのと明石の浦の朝霧に
島かくれゆく船をしぞ思う
有名な万葉歌人柿本人麻呂の和歌を万葉仮名で刻んだもので、骨太な文字を認めたのは、碑文にあるように蕋雲女史である。
蕋雲は文化年間(1804~1817)、遊里新吉原の半松楼に抱えられていた遊女で、源氏名を粧太夫といい、蕋雲はその号である。
粧太夫として当時の錦絵にも描かれており、書を中井敬義(なかいたかよし)に学び、和歌もたしなむ教養ある女性で、江戸時代の代表的な文人、亀田鵬斎(かめだぼうさい)から蕋雲の号を送られたほどの人物であった。
この歌碑は、人麻呂を慕う太夫が、文化13年(1816)8月、人丸社に献納したものである。人丸社は幕末の絵図によると、三社権現(現浅草神社)の裏手にあったが、明治維新後に廃され、碑のみが被官稲荷社のかたわらに移され、昭和29年(1954)11月、現在地に移された。

14. 浅草神社(あさくさじんじゃ)
重要文化財
浅草2-3 浅草(あさくさ)神社
明治初年の文書によると、祭神は土師真中知命(はじのまつちのみこと)・桧前浜成命(ひのくまのはまなりのみこと)・桧前竹成命(ひのくまのたけなりのみこと)・東照宮である。浜成と竹成は推古天皇36年(628)に隅田川で漁猟中、浅草寺本尊の観音像を網で拾い上げた人物、真中知はその像の奉安者と言われている。三神を祀る神社なので、「三社様」と呼ばれた。しかし鎮座年代は不詳。東照宮は権現様すなわち徳川家康のことで、慶安2年(1649)に合祀された。以来、三社大権現といい、明治元年(1868)に三社明神、同6年(1873)に浅草神社と改称した。
現在の社殿は、慶安2年(1649)12月、徳川家光が再建したもの。建築様式は、本殿と拝殿との間に「石の間」(幣殿・相の間ともいう)を設け、屋根の棟数の多いことを特徴とする権現造。この社殿は、江戸時代初期の代表的権現造として評価が高く、国の重要文化財に指定されている。毎年5月に行われる例祭は「三社祭」の名で知られ、都指定無形民俗文化財「びんざさら」の奉演、100体近い町御輿の渡御があって、人々が群集し、賑やかである。

15. 初代市川猿翁句碑(しょだいいちかわえんおうくひ)
浅草2-3 浅草(あさくさ)神社
「翁の文字はまだ身にそはず 衣がえ」猿翁
建碑 昭和42年(1967)5月17日
撰文 市川猿翁
孫団子に三代目猿之助を譲り、自らは猿翁を襲名。昭和38年(1963)5月、歌舞伎座に於いて襲名興行。(浅草寺の襲名お練り行列は4月16日)
『猿翁』(昭和39年6月東京書房刊)には、「翁の文字まだ身にそはず 衣がへ 猿翁 昭和三十七年五月猿翁襲名のとき」とある。
明治21年(1888)5月10日、浅草千束町2丁目に生まれる。
父、喜熨斗亀次郎(初代市川猿之助ー段四郎)、母古登の長男(弟妹は10人)。兵役を終えたのち明治43年(1910)10月、22才で二代目市川猿之助を襲名。
昭和38年(1963)6月、聖路加病院で心不全にて死去。享年75才。
昭和36年(1961)3月28日、浅草3丁目39番地に生家に因みて「猿之助横丁碑」を建てる。

16. 花塚(はなづか)
浅草2-3 浅草(あさくさ)神社
「濁(にごり)流」の花道の師、笠翁斉乱鳥の死を悲しんだ弟子たちによって建てられた。
笠翁乱鳥は、享和3年(1803)7月晦日死去。享年88才。浅草本然寺(曹洞宗、現西浅草3丁目25番3号)に埋葬。悲しんだ弟子たちが瓶に花を挿したが、衰える花を惜んで地中に埋め塚とした。
戦後、昭和31年(1956)観音堂裏手東北より移転。
建碑 文化元年(1804) 3月17日
「かめに花を挿こと古しへより聞え来れるを近き代には其花をさすにのり有事と成り其流くさくさに分れぬ。
笠翁斉乱鳥其わざを好てこの大城のもとに濁流としなへて弟子あまた有き。こその文月つごもり、歳八十餘八にてみまかり給。浅草本然禅寺に葬ぬ。ことし三月十七日、かの翁の親しき友垣に弟子の集りて、かめに花をさして手向つ。其花のなごりを空しくなさむ事を惜み、はた翁の名の朽さらん事をおもひて、浅草寺の大ひさのみ堂のうしろ清らなる所を撰て其花を埋めて花塚と名付て後の世に残しなんとす。彼弟子の中、平石氏乱雨翁え残されしほゝに笠翁斉の名を残したれば人々共に計りて其事成ぬ其わきかいつけよとこはるゝにいなひあへずして記つ。
「文化元年七月千蔭」

17. 江戸・東京の農業 檜前の馬牧(えど・とうきょうののうぎょう ひのくまのうままき)
浅草2-3 浅草(あさくさ)神社
大宝元年(701)、大宝律令で厩牧令(きゅうもくれい)が出され、全国に国営の牛馬を育てる牧場(官牧・かんまき)が39ヵ所と、皇室に馬を供給するため、天皇の命により32ヵ所の牧場(勅旨牧・ちょくしまき)が設置されました。
東京には「檜前(ひのくま)の馬牧(うままき)」「浮嶋の牛牧」「神崎の牛牧」が置かれたと記録にあって「檜前の馬牧」は、ここ浅草に置かれたのではないかと考えられています。
浅草神社の祭神で、浅草寺本尊の発見者ではある、檜前浜成、竹成兄弟の説話から、檜前牧は浅草付近であったと『東京市史稿』では推定していて、「浮嶋の牛牧」は本所に、「神崎の牛牧」は牛込に置かれたとされています。
時代は変わり江戸時代、徳川綱吉の逝去で「生類憐みの令」が解かれたり、ペリー来航で「鎖国令」が解けた事などから、江戸に欧米の文化が流れ込み、牛乳の需要が増え、明治19年(1886)東京府牛乳搾取販売業組合の資料によると、浅草区の永住町、小島町、森下町、馬道と、浅草でもたくさんの乳牛が飼われるようになりました。

18. 初代中村吉衛門句碑(しょだいなかむらきちえもんくひ)
浅草2-3 浅草(あさくさ)神社
「女房(にょうぼう)も 同じ氏子(うじこ)や 除夜詣(じょやもうで)」
吉右衛門
建碑 昭和28年(1953) 4月21日
初代中村吉右衛門 歌舞伎俳優 日本芸術院会員 文化勲章受賞
明治19年(1886)3月24日、浅草象潟町に生まれ、幼少から舞台に立って名声を得、長じて大成し、大正・昭和期を代表する歌舞伎俳優となった。
高浜虚子に師事して「ホトトギス」の同人となり、句集も3冊に及ぶ。初め秀山と号したが、後に吉右衛門の名前を用いた。
妻千代もまた浅草の生まれ、この句の由縁である。昭和14年(1939)冬の作、この碑は自詠自筆である。
実名 波野辰次郎
昭和29年9月5日没 享年68

19. 初代花柳壽輔略傅(しょだいはなやぎじゅすけりゃくでん)
浅草2-3 浅草(あさくさ)神社
出 生 文政4年(1821)2月 19 日、芝・新明にて出生。
6 才 文政9年(1826)、四世西川扇蔵の許に入門し舞踊修行の道に入る。
8 才 文政11年(1828)、七世市川団十郎の鑑識に叶い市川鯉吉の芸名にて舞台を踏む。
19 才 天保10年(1839)、旧師西川扇蔵の許に復帰し、西川芳次郎として振付師の第一歩を踏み出す。
25才 吉原の玉屋小三郎より俳号の「花柳」なる二字を与えられ、以後花柳芳次郎と称 す。爾後、七世市川団十郎が嘉永2年(1849)、当時市川海老蔵を名乗り、その俳号「寿海」に因みて「壽」の字を贈られ、29才にして初めて花柳 壽助を名乗り、後に「助」を「輔」に改め、と共に、諸流に冠絶して振付の第一人者として謳はれる事、実に半世紀。その作品は1千5百種を超え、就中「土蜘」「茨木」「戻橋」「舟辯慶」の如きは不滅の傑作と讃される。
83 才 明治36年(1903)1月28日、花柳流の祖としての偉業を樹(た)て 、門弟、縁者に見守られてその生涯を終わる。

20. 神木『槐』の木の由来(しんぼくえんじゅのきのゆらい)
浅草2-3 浅草(あさくさ)神社
槐(えんじゅ)は中国原産のマメ科の落葉喬木で、葉は藤に似て、夏、黄白色の花をつけ、高さ10メートルに及ぶ。古来中国では宮廷の庭に3本の槐を植え三公のつく位置を示したといわれる通り、高貴の木として珍重された樹木である。
浅草寺のご本尊の聖観音菩薩は推古天皇36年(628年)3月18日、墨田川で漁をしていた檜前浜成(ひのくまのはまなり)、竹成(たけなり)の二兄弟によって網得され川辺の槐の木の切株に安置されたが、その主、土師仲知(はじのなかとも)の教導により、三人共々深く観世音に帰依し、草堂を結び自邸を寺にかえたのが浅草寺の始まりと伝えられている。その後、この三人が浅草観音示現の功労者として、三社権現の尊称を奉られ、神として祭祀されたが、これが当浅草神社であるから、槐は浅草寺にとっても当社にとっても非常に因縁の深い木である。
その故か、当境内には槐の木が自生し、枯れては生え、枯れては生え、連綿として絶える事がない。まことに不思議な縁を感じさせる木である。

21. 被官稲荷社(ひかんいなりしゃ)
浅草2-3 浅草(あさくさ)神社
安政元年(1854)、新門辰五郎(しんもんたつごろう)の妻女が 重病で床に伏したとき、山城国(現京都府南部)の伏見稲荷社に祈願した。その効果があって病気全快、同2年(1855)、お礼の意味を込め、伏見から祭神を当地に勧請(かんじょう)し、小社を創設して被官稲荷社と名付けた。名称の由来は不詳だが、被官は「出世」と解せば良いという。
辰五郎は上野寛永寺住職輪王寺宮の家来、町田仁右衛門の養子。本姓は町田であった。輪王寺宮舜仁法親王が浅草寺伝法院に隠居し、上野に行くのに便の良い新門を造った。その門の番を命じられたので、新門辰五郎と呼ばれた。辰五郎は町火消十番組の組頭としても、多彩な活躍をした。
社殿は一間社流造(いっけんしゃながれづくり)、杉皮葺。創建以来のもの。間口約1.5メートル、奥行約1.4メートルと小さいが、覆屋(おおいや)を構えて保護している。覆屋は大正期の建築であろう。社前には、「安政二年九月立之 新門辰五郎」と刻む鳥居他がある。

22. 初代並木五瓶句碑(しょだいなみきごへいくひ)
浅草2-3 浅草(せんそう)寺
碑面には、正面に「月花のたわみこころや雪の竹」、右手側面に「なにはづの五瓶、東武に狂言を出して、あまねく貴賤の眼目を驚かし、金竜の山中に雪月花の碑を築て、永く繁栄を仰ぐ、つづくらん百三十里雪の人晋子堂大虎」、左手側面に「寛政八年丙辰十二月十日建之 庭柏子書(印)」、裏面に「篠田金二迂造」と刻んである。
「なにはづの五瓶」は初代並木五瓶のこと。五瓶は大阪に生まれ、歌舞伎狂言作者として活躍した。生存年代は延享4年(1747)から文化5年(1808)まで。はじめ五八、のち吾八・呉八・五兵衛と改め、ついで五瓶という。寛政6年(1794)江戸へ出て、非凡な才能をみせ、初代桜田治助とともに、江戸の二大作者と謳われた。時代物・世話物に優れた作品を遺し、四代市川団蔵、四代松本幸四郎らによって演じられた。作品には、「金門五山桐」「隅田春奴七容性」「富岡恋山開」「幡随院長兵衛」などがある。

23. 山東京伝机塚の碑(さんとうきょうでんつくえづかのひ)
台東区有形文化財
浅草2-3 浅草(せんそう)寺
山東京伝(1761~1816)は、浅草や吉原を題材とする戯作を多く著し、北尾政演の画号で浮世絵もよくした人物。
この碑は、京伝の弟京山が文化14年(1817)に亡兄を偲んで建立。表面には晩年の京伝撰「書案之紀」を刻む。書案とは机のことで「9歳の時に寺子屋に入った際、親の買ってくれた机を生涯愛用し、この机で100部を超える戯作を書いた。しかし50年近くも使ったので、ゆがみ、老い込んださまは哀れである」という意味の文と、「耳もそこね あし(足)もくしけてもろともに 世にふる机なれも老たり」の歌が記されている。また裏面には、京伝と親交のあった戯作者太田南畝(おおたなんぽ)の撰による京伝の略歴を刻む。
京伝の生涯や人間性を伝える貴重な資料で、平成2年(1990)に台東区有形文化財として登載。

24. 西仏板碑(さいぶついたび)
都指定有形文化財・歴史資料
浅草2-3 浅草(せんそう)寺
建立者の西仏(さいぶつ)については明らかではないが、この板碑(いたび)は彼が妻子の後世安楽を祈って建立したものと推測される。建立の年代も不詳であるが、鎌倉末から室町初期かと思われる。
上部が破損しているが、製作時には3メートル近くあったものと思われる。寛保2年(1742)暴風雨によって倒れ破損、文化11年(1814)に有志が側柱を立てて支えたという。材質は秩父粘板岩(青石)。
現存の板碑の大きさは高さ217.9センチメートル、幅48.0センチメートル、厚さ4.7センチメートル。
中世の信仰を知るうえでも貴重な遺品であり、かつ巨大板碑の典型例である。

25. 浅草寺六角堂一棟(せんそうじろっかくどういっとう)
都指定有形文化財・建造物
浅草2-3 浅草(せんそう)寺
六角堂は『浅草寺誌』(文化10年編)に元和4年(1618)の建立とあり、江戸時代初期の建築と考えられ、浅草寺内では最古の遺構である。
木造で単層の六角造り瓦葺き形式で、建物中央の直径は1.82メートルあり、一面の柱真々は0.91メートルである。
建物の基礎は、六角形状に廻した土台を布石の基礎で支え、その下部に11段の石積みをした1.5メートル余りの井戸状の穴が掘られている。六角堂という特異な形式であり、都内においては遺例の少ない建造物で、貴重な文化財である。
もとは東方21.8メートルの場所(現影向堂[ようごうどう]の南基壇上に元位置の明示あり)に建っていたが、平成6年(1994)10月境内整備のためにここに移された。

26. 橋本薬師堂(はしもとやくしどう)
浅草2-3 浅草(せんそう)寺
当初は観音堂の北方にあって、北薬師と呼ばれた。慶安2年(1649)三代将軍徳川家光が観音堂の北西に再建し、堀にかかる橋のかたわらにあったので、家光自身が橋本薬師堂と名付けた。平成6年(1994)、現在の場所に移転した。
現在の建物は、桁行(けたゆき)3間(約5.35メートル)、梁間(はりま)3間(約5.10メートル)、屋根は入母屋造(いりもやづくり)、瓦葺。外部はかなり改変され、前面にあった3間に一間の向拝(こうはい)は取り除かれているが、浅草寺境内に遺存する堂宇のうち、浅草神社の社殿と同時代で、二天門や影向堂脇の六角堂に次ぐ古建築である。薬師如来坐像を本尊とし、他に前立の薬師如来と十二神将像が安置されている。

27. 三匠句碑(さんしょうくひ)
浅草2-3 浅草(せんそう)寺
ながむとて花にもいたし頚の骨 宗因
花の雲鐘は上野か浅草か 芭蕉
ゆく水や何にとどまるのりの味 其角
江戸時代前期を代表する俳人三匠の句が刻まれている。
西山宗因 慶長10年(1605)肥後(熊本県)の生まれ。後、大坂に住み談林の俳風を聞く。この句は『新古今集』にある西行法師の和歌「ながむとて花にもいたく…」からとった句。天和2年(1682)没。
松尾芭蕉 正保元年(1644)伊賀(三重県)の生まれ。数次の漂泊の旅に出て作品集や紀行文を残し、『おくのほそ道』は世に知られている。蕉風俳諧を樹立。元禄7年(1694)大坂で没。
宝井其角 寛文元年(1661)江戸に生まれる。蕉門十哲の一人。後、蕉風を脱し、その一派の傾向は洒脱風などともいわれた。宝永4年(1707)の没。
碑は、文化6年(1809)の建立。台石には明治27年(1894)春の移築の由来が記されている。

28. 戸田茂睡墓(とだもすいはか)
都指定旧跡
浅草2-3 浅草(せんそう)寺
戸田茂睡(1629〜1706)は元禄期の歌人です。渡辺監物忠の六男として駿府城内で生まれ、父の死後伯父戸田政次の養子になります。名は馮、後に恭光、通称は茂右衛門、茂睡のほか露寒軒などと号しました。一時岡崎藩本多家に仕えましたが出家し、浅草寺近くに居をかまえました。『梨本集』『紫の一本』『若葉』などを著し、形骸化した伝統歌学の積極的批判者としての文学的意義が認められています。
自然石の土台、宝篋印塔の基壇、五輪塔の順に配されており、茂睡自身が生前に自らを後世に供養した逆修塔です。

29. 瓜生岩子女子の銅像(うりゅういわこじょしのどうぞう)
浅草2-3 浅草(せんそう)寺
岩子は通称。正しくは「岩」という。文政12年(1829)2月15日、岩代耶麻郡(現福島県喜多方市)熱塩村渡辺家に生まれたが、9歳の時、父を失い、母は岩を連れて生家へ帰った。そのため、岩は母方の姓瓜生氏を称した。14歳の時、若松(現福島県会津若松市)の叔母に預けられ、その夫で会津若松藩侍医を勤める山内春瓏(しゅんろう)の薫陶を受け、堕胎間引の防止に関心を持つに至る。17歳で佐瀬茂助を婿に迎え、若松で呉服屋を営み、一男三女を生んだが、早くに夫を亡くした。明治元年(1868)会津戦争で孤児となった幼童の教育に尽力した他、堕胎など当時のさまざまな悪習を正し、明治22年(1889)貧民孤児救済のため福島救済所を設立するなど、社会事業の推進に努めた。
明治30年(1897)4月19日、福島で没す。享年69。生涯を慈善事業に捧げた岩の善行を賞揚し、同34年(1901)4月、篤志家によって、浅草寺境内にこの銅像が造立された。台石正面には、下田歌子女史の撰文を刻む。

30. 淡島堂(あわしまどう)
浅草2-3 浅草(せんそう)寺
淡島堂は、元禄年間(1688~1703)紀伊国(現和歌山県)の加太神社を勧請(かんじょう)したものである。加太神社は、淡島と呼ぶ小島に鎮座し、淡島明神の俗称があるため、この堂も淡島堂と呼ばれている。祭神は少彦名命(すくなひこなのみこと)、堂内には両手で宝珠を持つ坐形の神像を安置する。
淡島明神は、江戸時代より女性の守り神として、信仰を集めた。現在も毎年2月8日、ここで針供養が行われ、女性の参詣人が群集する。針供養は、日頃使い慣れた針に感謝し、柔らかな豆腐に刺し、供養する行事。かつては、この日に限り女性は針仕事をしない風習があった。