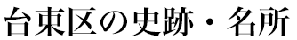01. 助六歌碑(すけろくかひ)
花川戸2-4-15 花川戸公園
碑面には、
助六にゆかりの雲の紫を
弥陀の利剣で鬼は外なり 団洲
の歌を刻む。九世市川団十郎が自作の歌を揮毫したもので、「団洲」は団十郎の雅号である。
歌碑は、明治12年(1879)九世団十郎が中心となり、日頃世話になっている日本橋の須永彦兵衛(通称棒彦)という人を顕彰して、彦兵衛の菩提寺仰願寺(現清川1丁目4番6号)に建立した。大正12年(1923)関東大震災で崩壊し、しばらくは土中に埋没していたが、後に発見、碑創建の際に世話役を務めた人物の子息により、この地に再造立された。台石に「花川戸鳶平治郎」、碑裏に「昭和三十三年秋再建 鳶花川戸桶田」と刻む。
歌舞伎十八番の「助六」は、二代目市川団十郎が正徳3年(1713)に初演して以来代々の団十郎が伝えた。ちなみに、今日上演されている「助六所縁江戸桜(すけろくゆかりのえどざくら)」は、天保3年(1832)上演の台本である。助六の実像は不明だが、関東大震災まで浅草清川にあった易行院(現足立区伊興町狭間870)に墓がある。

02. 姥ヶ池(うばがいけ)
都指定旧跡
花川戸2-4-15 花川戸公園
姥ヶ池(うばがいけ)は、昔、隅田川に通じていた大池で、明治24年(1891)に埋め立てられた。浅草寺の子院妙音院所蔵の石枕にまつわる伝説に次のようなものがある。
昔、浅茅ヶ原(あさぢがはら)の一軒屋で、娘が連れ込む旅人の頭を石枕で叩き殺す老婆がおり、ある夜、娘が旅人の身代わりになって、天井から吊した大石の下敷きになって死ぬ。それを悲しんで悪行を悔やみ、老婆は池に身を投げて果てたので、里人はこれを姥ヶ池と呼んだ。

03. 九品寺大仏(くほんじだいぶつ)
台東区有形文化財
花川戸2-11-13 九品(くほん)寺
境内の左側に建つ大きな仏像は銅像の阿弥陀如来坐像で、「九品寺大仏」の名で親しまれている。この仏像は明暦3年(1657)の大火で亡くなった人々の菩提を弔うため、当寺第二世住職天誉が江戸市民から浄財を募って万治3年(1660)に造立した。蓮華坐には、造立に協力した人々やその縁故者と思われる人物の戒名・法名などを刻む。作者の長谷川五郎兵衛尉益継(ごろべえのじょうますつぐ)は、万治から寛文年間(1658~1672)の頃に活躍した鋳物師(いもじ)のひとりで、遺品としては九品寺大仏を含め4点の仏像・梵鐘(ぼんしょう)がある。
また、かつて九品寺には平安朝の学者小野篁の作と伝える沓履(くつはき)地蔵尊(木造念持仏)が安置されていたが、関東大震災で焼失した。平成3年(1991)、当寺では文献に拠って沓履地蔵尊をほぼ等身大の大きさに復元し、大仏の向かい側に再建した。履物のまち花川戸にふさわしく沓を履いている珍しい地蔵菩薩像である。

04. 山の宿の渡し(やまのしゅくのわたし)
花川戸1-1 隅田公園
隅田川渡し舟の一つに、「山の宿の渡し 」と呼ぶ渡し舟があった。明治40年(1907)発行の『東京市浅草区全図』には、隅田川に船路を描き、「山ノ宿ノ渡、枕橋ノ渡トモ云」と記されている。位置は、吾妻橋上流約250メートル。浅草区花川戸河岸・本所区中ノ郷瓦町間を結んでいた。花川戸河岸西隣の町名を、「山ノ宿町」といった。渡しの名はその町名をとって命名。別称は、東岸船着場が枕橋橋畔にあったのにちなむ。枕橋は墨田区内現存の北十間川架橋。北十間川の隅田川合流点近くに架設されている。
渡船創設年代は不明。枕橋上流隅田河岸は、江戸中期頃から墨堤と呼ばれ、行楽地として賑わった。桜の季節は特に人出が多く、山の宿の渡しはそれらの人を墨堤に運んだであろう。したがって、江戸中期以降開設とみなせるが、天明元年(1781)作「隅田川両岸一覧図絵」はこの渡しを描いていない。

05. 花の碑 (はなのひ)
浅草7-1 隅田公園
春のうららの隅田川
のぼりくだりの船人が・・・
武島羽衣(たけしまはごろも)作詞・滝廉太郎作曲「花」。本碑は、羽衣自筆の歌詞を刻み、昭和31年(1956)11月3日、その教え子たちで結成された「武島羽衣先生歌碑建設会」によって建立された。
武島羽衣は、明治5年(1872)、日本橋の木綿問屋に生まれ、赤門派の詩人、美文家として知られる人物である。明治33年(1900)、東京音楽学校(現東京藝術大学)教授である武島羽衣と、同校の助教授、滝廉太郎とともに「花」を完成した。羽衣28歳、廉太郎21歳の時であった。
滝廉太郎は、作曲者として有名な人物であるが、よく知られているものに「荒城の月」「鳩ぽっぽ」などがある。「花」完成の3年後、明治36年(1903)6月29日、24歳の生涯を閉じた。
武島羽衣はその後、明治43年(1910)から昭和36年(1961)に退職するまでの長い間、日本女子大学で教鞭をふるい、昭和42年(1967)2月3日、94歳で没した。
手漕ぎ舟の行き交う、往時ののどかな隅田川。その情景は、歌曲「花」により、今なお多くの人々に親しまれ、歌い継がれている。

06. 竹屋の渡し(たけやのわたし)
浅草7-1 隅田公園
隅田川にあった渡し舟の一つ。山谷掘口から向島三囲(みめぐり)神社(墨田区向島2丁目)の前あたりを結んでいた。明治40年(1907)刊『東亰案内 』には「竹屋の渡」とあり、同年発行『東京市浅草全図』では山谷堀入口南側から対岸へ船路を描き「待乳ノ渡、竹家の渡トモ云」と記しており、「竹屋の渡」とも、あるいは「待乳ノ渡」とも呼ばれたようである。「竹屋」とは、この付近に竹屋という舟宿があったためといわれ、「待乳」とは待乳山の麓にあたることに由来する。
「渡し」の創設年代は不明だが、文政年間(1818~1830)の地図には、山谷堀に架かる「今戸はし」のかたわらに「竹屋のわたし」の名が見える。
江戸時代、隅田川をのぞむ今戸や橋場は風光明媚な地として知られ、様々な文学や絵画の題材となり、その中には「竹屋の渡し」を描写したものも少なくない。
昭和3年(1928)言問橋の架設にともない、渡し舟は廃止された。

07. 待乳山聖天(まつちやましょうでん)
浅草7-4-1 本龍(ほんりゅう)院
待乳山聖天は、金龍山浅草寺の支院で正しくは、待乳山本龍院という。その創建は縁起によれば、推古天皇9年(601)夏、旱魃(かんばつ)のために人々が苦しみ喘いでいたときに、十一面観音が大聖尊歓喜天に化身してこの地に姿を現し、人々を救ったため、「聖天さま」として祀ったといわれる。
ここは隅田川に臨み、かつての竹屋の渡しにほど近い小丘で、江戸時代には東都随一の眺望の名所と称され、多くの浮世絵や詩歌などの題材ともなっている。特に、江戸初期の歌人戸田茂睡の作、
哀れとは夕越えて行く人も見よ
待乳の山に残す言の葉
の歌は著名で、境内にはその歌碑(昭和30年再建)のほか、石造出世観音立像、トーキー渡来の碑、浪曲双輪塔などが現存する。また、境内各所にほどこされた大根・巾着の意匠は、当寺の御利益を示すもので、大根は健康で一家和合、巾着の意匠は商売繁盛を表すという。1月7日大般若講大根祭には多くの信者で賑わう。
なお、震災・戦災により、本堂などの建築物は焼失、現在の本堂は昭和36年(1961)に再建されたものである。

08. 浅間神社(せんげんじんじゃ)
浅草のお富士さん・台東区有形民俗文化財
浅草5-3-2
浅間神社は、富士山への信仰に基づき勧請された神社で、神体として「木造木花咲耶姫命坐像」(もくぞうこのはなさくやひめのみことざぞう)を安置する。
創建年代は不明だが、『浅草寺志』所収『寛文十一年江戸絵図』に表記があり、江戸時代初期の寛文11年(1671)までには鎮座していたようである。現在の鎮座地は、2メートルほどの高みを成しているが、中世から江戸初期にかけて、関東地方では人工の塚、あるいは自然の高みに浅間神社を勧請する習俗があったとされており、当神社の立地もそうした習俗に基づくものと思われる。
江戸時代には浅草寺子院修善院の管理のもと、修験道による祭祀が行われ、江戸を代表する富士信仰の聖地として、各所の富士講講員たちの尊崇を集めた。明治維新後は浅草寺の管理を離れ、明治6年(1873)には浅草神社が社務を兼ねることとなり、現在に至っている。
本殿は、平成9・10年(1997・1998)の改修工事によって外観のみ新たに漆喰塗が施されたが、内部には明治11年(1878)建築の土蔵造り本殿が遺されている。さらに、この改修工事に伴う所蔵品調査により、江戸時代以来の神像・祭祀用具・古文書などが大量に確認された。
これら、本殿・諸資料群・境内地は、江戸時代以後の江戸・東京における富士信仰のありさまを知る上で貴重であり、平成11年(1999)3月、台東区有形民俗文化財に指定された。
祭礼は、毎年7月1日の「富士山開き」が著名で、また、5・6月の最終土・日曜日には植木市が開催されている。

09. 銅造宝篋印塔
台東区有形文化財
浅草7-4-1 本龍(ほんりゅう)院
宝篋印塔は「宝篋印陀羅尼経」という経典に基づいて造立された塔である。本塔は江戸時代中期以降に流行した、屋根型の笠をもつ宝篋印塔で、時代性をよく表している。基礎に刻まれた銘文から、天明元年(1781)に鋳物師西村和泉守が制作し、蔵前の札差等16名が奉納したものであることが分かる。西村和泉守は、江戸時代から大正時代にかけて、11代にわたり鋳物師を務めた家で、本塔の作者は5代西村政平にあたると考えられる。
銅造の宝篋印塔は全国的にも類例が少なく、とくに区内では造立当初からほぼ完全な形で遺された唯一の事例である。各部の装飾は優れており、鋳物師の高い技能を知ることができる。また、蔵前の札差の奉納物としても貴重な歴史資料である。
平成14年(2002)に、台東区有形文化財として台東区区民文化財台帳に登載された。