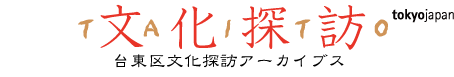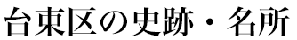01. 駒形堂(こまがたどう)
雷門2-2
『浅草寺縁起(せんそうじえんぎ)』によると、創建年代は朱雀(すざく)天皇の天慶5年(942)で、建立者は安房守平公雅(あわのかみたいらのきみまさ)。名称由来には、
1)隅田川を舟で通りながらこの堂を見ると、まるで白駒が馳けているようなので、「駒馳け」の転訛(『江戸名所図会(えどめいしょずえ)』)。
2)観音様へ寄進する絵馬を掛けたので「駒掛け堂」と呼んだのが訛る(『燕石雑誌(えんせきざっし)』)。
3)駒形神を相州箱根山から勧請(かんじょう)したのにちなむ(『大日本地名辞典』)。
これらの説がある。本尊は馬頭観世音菩薩。
葛飾北斎・安藤広重らによって、堂は絵に描かれた。小さくとも、江戸で名高い堂だった。当時の堂の位置は現駒形橋西詰道路中央付近。堂は関東大震災で焼けた。
※堂は震災後、昭和8年(1933)に再建されました。現在の堂は、損傷のため平成15年(2003)にさらに再建されたものです。

02. 浅草観音戒殺碑(あさくさかんのんかいさつひ)
都指定有形文化財・古文書
雷門2-2-3
駒形堂は浅草寺の伽藍の一つで、浅草寺本尊の聖観世音菩薩が隅田川から発見された霊地である。このため元禄5年(1692)、当地を魚鳥殺生禁断の地とする法度が出された。これを記念して、翌年(元禄6年)浅草寺第四世権僧正宣存が願主となり、戒殺碑が建てられた。殺生禁断の範囲は駒形堂を中心に、南は諏訪町より北は聖天岸に至る十町余の川筋だった。『御府内備考』によると、諏訪町・聖天町にも高札が建てられたという。
戒殺碑が建てられた駒形堂の堂宇は、江戸時代に何度か焼失している。戒殺碑も倒壊し、宝暦9年(1759)に堂宇とともに再建された。現存の碑は関東大震災の後の昭和2年(1927)に土中より発見され、同8年駒形堂再建と同時に修補されたものである。元禄当初の碑か、宝暦再建のものか定かではない。
碑身は石造(安山岩)で、長方形円頭板状。正面及び両側面を研磨し、背面は野面のままである。台石は昭和8年(1933)修補時のもので、上面・正面・両側面・背面の五面を研磨してある。総高183.5センチ、正面幅61センチ。銘文は『浅草寺誌』や『江戸名所図会』にも収載される。元禄当時の信仰及びその周辺の状況を明らかにする貴重な史料である。
※浅草観音戒殺碑は、向かって左側の石碑

03. 紙漉町跡(かみすきちょうあと)
雷門1-5付近
この付近は、江戸時代、紙漉町といい江戸における最初の紙漉きが行われた場所である。江戸時代を通じて盛んに製紙業が行われ、その産紙は浅草紙(あさくさがみ)と呼ばれて土地の特産物だった。
延宝4年(1676)版の『江戸絵図(えどえず)』には田原町1丁目の西側の道に「カミスキ丁」と記され、貞亨4年(1687)刊『江戸鹿子(かのこ)』にも「紙すき町」の名が見える。また、安永2年(1773)に成立した『江戸図説(えどずせつ)』によると、田原町のほかに橋場・鳥越や足立区千住方面でも生産されていたという。
明治時代になると、浅草紙の製造工場は橋場や南千住の方に移り、浅草付近では作られなくなる。わずかに紙漉きの名残をとどめているのは、以前山谷堀に架かっていた「紙洗橋(かみあらいばし)」の名の交差点表示である。
浅草紙は、不要になった古紙を手で漉き返して再利用する、今でいうリサイクルペーパーである。