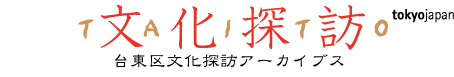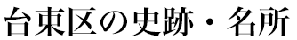01. 銅造地蔵菩薩坐像(どうぞうじぞうぼさつざぞう)
江戸六地蔵第二番・都指定有形文化財
東浅草2-12-13 東禅(とうぜん)寺
江戸六地蔵は、深川の地蔵坊正元(じぞうぼうしょうげん)が病気平癒に感謝して造立を発願(ほつがん)し、多くの人々の浄財を集め、江戸市中六ヶ所に勧請したものである。全身にある陰刻から神田鍋町の鋳物師太田駿河守正義によって鋳造されたことがわかる。本像の高さは2.71メートル、品川寺に次いで第二番の宝永7年(1710)に造立された。他の六地蔵は鍍金が施されているのに対し、記録では本像は像の表面を布目状にやすりをかけ、弁柄(べんがら)色の漆を塗った上に金箔を置いたあとが残っていたとある。長年の風雨により、損傷が著しかったため、平成11年(1999)に修復工事を行った。胎内仏として小型の銅造六地蔵菩薩坐像等が現存する。
なお、江戸六地蔵は次のとおりである。
品川寺 品川区南品川三丁目
太宗寺 新宿区新宿二丁目
真性寺 豊島区巣鴨三丁目
霊巌寺 江東区白河一丁日
永代寺 江東区(消滅)
東京都文化財保護条例(昭和51年3月31日改正)により、文化財の指定種別を都重宝から東京都指定文化財に変更しましたので、石造標識については、このように読み替えて下さい。
02. 権利者の意向により非公開

03. 駿馬塚(しゅんめづか)
東浅草2-16-1
駿馬塚は、平安時代の康平年間(1058~1064)源義家が陸奥へ向かう際、この地で愛馬「青海原(あおうなばら)」が絶命し、これを葬った所と伝えている。
現存する塚は、明治28年(1895)造立の石碑や石造層塔の一部を遺すのみだが、天保7年(1836)刊行の『江戸名所図会』には塚の挿絵を載せており、江戸時代後期には土饅頭型の塚や「駿馬塚」と書した石碑が建っていたようである。
現在、付近の人々はこの塚を「馬頭観音」と呼び、覆屋等を設けて大切に守っている。

04. 采女塚(うねめづか)
清川1-13-13 出山(しゅっさん)寺
石碑の正面上部に横書きで「采女塚」とあり、その下に仮名混じりの文でその由来を刻んでいる。
江戸時代の初期、寛文年間(1661~1672)新吉原雁金屋(かりがねや)の遊女「采女」に心を寄せた若い僧侶が師から固く制され悩んだ末、雁金屋の前で自害してしまった。采女は悲しんで浅茅ケ原(あさぢがはら)の鏡が池に身を投げた。時に17才。翌朝、草刈りの人たちが
名をそれとしらずともしれさる沢の
あとをかがみが池にしずめば
としるした短冊を見つけ、采女とわかり、塚に葬った。
浅茅ヶ原は、現在の橋場1、2丁目と清川1、2丁目のあたりを指し、『江戸名所図会』によると、鏡が池の面積は、文政(1818~1829)の頃、約5百平方メートル、橋場1丁目の北部あたりにあったという。
碑は、文化元年(1804)大田南畝(おおたなんぽ)ら文人たちによって建立。第二次世界大戦で火をあびている。

05. 其角の句碑 (きかくのくひ)
清川1-13-13 出山(しゅっさん)寺
草茎をつつむ葉もなき雲間哉
碑の正面に宝井其角の句を刻む。
其角の著『末若葉(すえわかば)』によれば、これは元禄9年(1696)正月、弟子を連れて当寺に遊んだときに詠んだ句であるという。碑は、この風流の故事を顕彰して、寛政5年(1793)に建立された。
其角は、寛文元年(1661)の生まれ。榎本ともいった。医師 竹下東順の子。14、5才のころ、芭蕉に入門し、早くから頭角をあらわしたという。天和3年(1683)蕉風の先駆とみなされる『虚栗(みなしぐり)』を編集し、芭蕉の新しい俳風の確立に活躍した。いわゆる蕉門十哲の第一人者とされたが、芭蕉の死後、次第に蕉風をはなれ、清新華麗な独自の句風をなし、江戸俳壇の中心となった。宝永4年(1707)没。
なお、右側面に刻む「くさぐきの今にのこるや人の口 屠竜(とりゅう)」は、姫路城主酒井忠以(ただもと)の弟であり、当時根岸に住んでいた画家酒井抱一の句である。

06. 妙亀塚(みょうきづか)
都指定旧跡
橋場1-28-3 妙亀塚公園
この妙亀塚のある地は、かつて浅茅ヶ原(あさぢがはら)と呼ばれた原野で、近くを奥州街道が通じていた。
妙亀塚は、「梅若伝説」にちなんだ名称である。「梅若伝説」とは平安時代、吉田少将惟房の子梅若が、信夫藤太という人買いにさらわれ、奥州へつれて行かれる途中、重い病にかかりこの地に捨てられ世を去った。我が子を探し求めてこの地まできた母親は、隅田川岸で里人から梅若の死を知らされ、髪をおろして妙亀尼と称し庵をむすんだ、という説話である。謡曲「隅田川」はこの伝説をもとにしている。
塚の上には板碑が祀られている。この板碑には「弘安十一年戊子五月二十二日孝子敬白」と刻まれており、区内でも古いものである。しかし、妙亀塚と板碑との関係は、明らかではない。
なお、隅田川の対岸、木母寺(もくぼじ・墨田区堤通)境内には、梅若にちなむ梅若塚(都旧跡)があり、この妙亀塚と相対するものと考えられている。

07. お化け地蔵(おばけじぞう)
橋場2-5-3 松吟(しょうぎん)寺
「お化け地蔵」の名には、かつて大きな笠をかぶり、その笠が向きをかえたから、あるいは高さ3メートル余の並はずれて大きいからなど、いくつかの伝承がある。
この辺りは、室町時代以来、禅宗の名刹総泉寺の境内地であった。門前一帯を浅茅ケ原(あさぢがはら)といい、明治40年(1907)刊『東京名所図会』には「浅茅ヶ原の松並木の道の傍らに大いなる石地蔵ありしを維新の際並木の松を伐りとり、石地蔵は総泉寺入口に移したり」とあり、「当寺入口に常夜灯あり、東畔に大地蔵安置す」とも記している。
お化け地蔵の台石によれば、この石仏は享保6年(1721)の建立。関東大震災で二つに折れたが、補修し現在にいたっており頭部も取りかえられている。常夜灯は、寛政2年(1790)に建てられた。
総泉寺は、昭和4年(1929)板橋区へ移転した。「お化け地蔵」近くにある「元総泉寺境内諸仏供養の為」の碑は移転に際し建てられたものと思われる。

08. 平賀源内墓(ひらがげんないはか)
国指定史跡
橋場2-22-2
平賀源内は享保13年(1728)、讃岐国志度浦(現香川県志度町)に生まれる(生年には諸説ある)。高松藩士白石良房の三男で名は国倫(くにとも)。源内は通称である。
寛延2年(1749)に家督を継ぎ、祖先の姓である平賀姓を用いた。本草学・医学・儒学・絵画を学び、事業面では成功しなかったが、物産開発に尽力した。物産会の主催、鉱山開発、陶器製造、毛織物製造などをおこない、エレキテル(摩擦起電機)を復元製作、火浣布(かかんぷ・石綿の耐火布)を発明した。一方で風来山人(ふうらいさんじん)・福内鬼外(ふくちきがい)などの号名をもち、『風流志道軒伝(ふうりゅうしどうけんでん)』などの滑稽本や、浄瑠璃「神霊矢口渡(しんれいやぐちのわたし)」などの作品を残している。
安永8年(1779)11月に誤って殺傷事件を起こし、小伝馬町の牢内で12月18日に病死、遺体は橋場の総泉寺(曹洞宗)に葬られた。墓は角塔状で笠付、上段角石に「安永八己亥十二月十八日 智見霊雄居士 平賀源内墓」と刻む。後方に従僕福助の墓がある。
総泉寺は昭和3年(1928)板橋区小豆沢へ移転したが、源内墓は当地に保存された。昭和4年(1929)に東京府史蹟に仮指定され、昭和6年(1931)には松平頼壽(よりなが・旧高松藩主)により築地塀が整備される。昭和18年(1943)に国指定史跡となった。

09. 対鴎荘跡 (たいおうそうあと)
橋場2-1
隅田川畔の橋場一帯は、風光明眉な地であり、かつては著名人の屋敷が軒を連ねていたという。対鴎荘もその一つで、明治時代の政治家三条実美(さんじょうさねとみ・1837~1891)の別邸であった。
「征韓論(せいかんろん)」をめぐって、政府内に対立が続いていた明治6年(1873)の10月、太政大臣の要職にあった実美は心労のあまり病に倒れ、この別邸で静養していたが、同年12月19日明治天皇は病床の実美を気遣い、この邸を訪れている。
隣の碑 は、この事蹟を顕彰して、のち対鴎荘の所有者となった一市民の尽力によって建立されたものである。高さ3メートル余。側面に「昭和六年歳次辛未五月建之石井久太郎」、裏面に「多摩聖蹟記念館顧問中島利一郎謹撰 上条修徳謹書」の碑文が刻まれている。
対鴎荘は、昭和3年(1928)、白髭橋架橋工事に伴い、多摩聖蹟記念館(多摩市連光寺)に移築された。

10. 安藤東野墓(あんどうとうやはか)
都指定旧跡
橋場1-16-2 福寿(ふくじゅ)院
江戸時代中期の儒学者。名は煥図、字は東壁、仁左衛門と称し、東野と号していた。元滝田氏といい、天和3年(1683)1月28 日下野那須郡黒羽に生まれた。父大沼玄佐は医師と して下野黒羽藩大関家に仕え、彼は次子であったが幼くして父を失い江戸に移った。ここで太宰春台とともに中野撝謙(ぎけん)の門に学び、後に安藤氏に養われ、これにより安藤氏を称した。柳沢吉保に仕え 荻生徂徠(おぎゅうそらい)に就いて詩文を学ぶ。たまたま将軍綱吉が柳沢邸に来た時に講義したという。正徳元年(1711)29歳の時に致仕し駒込白山に隠居した。のち河内西代(にしだい)藩主本田忠統の賓師となったが、肺を病み、享保4年(1719)4月13日37歳で死去した。著書『東野遺稿』は没後友人が編集して刊行したものである。

11. 銅鐘(どうしょう)
台東区有形文化財
今戸2-32-16 長昌(ちょうしょう)寺
長昌寺は日蓮宗の古刹で、開創は弘安2年(1279)といわれる(一説に同5年)。開山の日寂は浅草寺座主を務めた天台宗の僧であったが、日蓮の直弟子日常と宗論におよび改宗、橋場に妙昌寺を開いた。その後、水害で堂宇を流失し元享元年(1321)現在地に再興、長昌寺と改めた。
元和年間(1615~1624)江戸幕府の有力な譜代大名酒井忠勝によって中興され、日寂が浅草寺から移したといわれる観音像などが庶民の信仰を集めた。
橋場の数か寺にはいわゆる「鐘が淵(かねがふち)」の沈鐘(ちんしょう)伝説があり、長昌寺の鐘もその一つである。現在の銅鐘は、堂宇流失の際に沈んだといわれる鐘の再鋳として、享保5年(1720)二十二世住持日津および橋場の檀信徒によりつくられた。鐘銘は、飯高檀林化主で身延山久遠寺住持にもなった日潮の作になる。また銘文中には、鋳造者の神田鍋町鋳物師小幡内匠の名が記されている。
昭和19年(1944)、重要美術品の認定を受けている。

12. 亀田鵬斎墓(かめだ ぼうさいはか)
都指定史跡
今戸2-6 称福(しょうふく)寺墓地
亀田鵬斎(ぼうさい)は江戸時代後期の著名な儒学者である。宝暦2年(1752)江戸・神田に生まれた。名は翼(よく)といい、のち長興(ちょうこう)。字は穉龍(ちりゅう)、通称文左衛門(ぶんざえもん)、鵬斎・善身堂(ぜんしんどう)と号した。折衷学者井上金峨(墓地は港区青松寺)に学び、山本北山(ほくざん)ともに荻生徂徠(墓地は港区長松寺・国指定史跡)の古文辞学を排撃し、朱子学を批判したために、寛政異学の禁では異端の筆頭と目されていた。
書をよくし、草書は近世を通じての名手といわれている。著書に『論語撮解(ろんごさっかい)』『善身堂詩鈔(ぜんしんどうししょう)』などがある。
文政9年(1826)75歳で没した。墓石には「鵬斎亀田先生之墓」と刻している。

13. 明治天皇御製碑(めいじてんのうぎょせいひ)
今戸1-1 隅田公園
明治6年(1873)、明治天皇は元勲三条実美公の別邸対鴎荘に行幸し、病床にあった実美を見舞われた。御見舞いの帰途、伊達宗城邸で御休息の際、隅田川の冬景色を賞せられ、和歌をお詠みになった。
いつみてもあかぬ景色は隅田川
難美路の花は冬もさきつつ

14. 今戸焼(いまどやき)
今戸1-5-22 今戸神社
今戸焼とは現在の台東区今戸の地で焼かれてきた日用品の土器類・土人形類のことで、かつては江戸を代表する焼き物として繁栄していた。地元の今戸神社にある狛犬台座には宝暦2年(1752)に奉納した42名の陶工らの名が刻まれており、数多く軒を並べていたことが伺える。
今戸焼きの起源は定かではないが、伝承では天正年間(1573~1591)に千葉氏の家臣が今戸辺りで焼き物を始めたとか、徳川家康入府後三河の陶工が今戸に移って来たともいわれる。「今土焼」の名としては18世紀末頃から明らかに見られ、18世紀前半頃に本格的な土器生産が始まったと思われる。隅田川沿岸はかつて瓦を含めた土製品の生産が盛んであったようで、瓦町の名や瓦焼が早くから知られていた。江戸時代の文献である『江戸名所図会』には瓦作りの挿絵がみられ、『隅田川長流図巻』(大英博物館所蔵)には今戸焼の窯が描かれている。
近年の江戸遺跡の調査によって施釉土器、土人形や瓦等が多く出土し、そのなかには今土焼職人の名が刻印されている土器・土人形、今戸の地名を印した瓦も見られ、隅田川沿岸の窯業との関連が注目されている。
関東大震災や東京大空襲により職人が次々に区外へ移り、現在今戸には一軒のみが残り、伝統を伝える「口入れ狐」や「招き猫」などの人形が今でも製作されている。