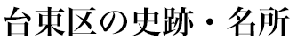01. 目黄不動(めきふどう)
三ノ輪2-14-5 永久(えいきゅう)寺
目黄不動は、江戸五色不動の一つとして知られている。江戸五色不動とは、目白、目赤、目黒、目青、目黄の各不動尊のことで、寛永年間(1624~1643)の中頃、徳川三代将軍家光が寛永寺創建で知られる天海大僧正の具申により、江戸府内の名ある不動尊を指定したと伝える。
不動明王は、密教ではその中心仏とされる大日如来が、悪を断じ、衆生を教化するため、外には忿怒の形相、内には大慈悲心を有する民衆救済の具現者として現われたとされている。また、宇宙のすべての現象は、地、水、火、風、空の五つからなるとする宇宙観があり、これらを色彩で表現したものが五色といわれる。
不動尊信仰は、密教がさかんになった平安時代初期の頃から広まり、不動尊を身体ないしは目の色で描きわけることは平安時代(794〜1185)すでに存在したという。

02. 阿部友之進照任墓(あべとものしんてるとうはか)
都指定旧跡
三ノ輪1-27-3 梅林(ばいりん)寺
阿部友之進照任は、江戸中期、徳川吉宗治世期に活躍した本草学者で、その墓は都の旧跡に指定されている(昭和3年指定)。友之進、名を照任、また輝任、字を伯重、号を将翁(しょうおう)また将翁軒といい、友之進は通称である。奥州盛岡出身。
東条琴台(とうじょうきんだい)著『先哲叢談続編(せんてつそうだんぞくへん)』四巻によると慶応3年(1650)の生まれとされているが、没年の宝暦3年(1753)から逆算すると、104歳で没したことになり、生年に疑問が持たれている。近年、照任の著になる『金之書』などにより、生年は寛文7年(1667)前後という見解も出された。
照任は、享保12年(1727)に奥州盛岡に、翌年甲斐(現山梨県)に赴き採薬を果たしている。同年神田紺屋町(現千代田区)に薬草植場を貸与され、また同14年(1729)、奥羽、蝦夷へ採薬に出掛けたことは幕府の史料で判明しているが、未だ不明な点が多い。
照任の曾孫喜任(よしとう)は字を享、享父、通称・号を曾祖父と同じ友之進、将翁と名乗るが、櫟斎(れきさい)の号を使用することが多い。他に巴菽園、矴庵の号がある。本草学を曽占春(そうせんしゅん)、岩崎灌園(いわさきかんえん)に学び、漢学を東条琴台に学んだ。文久元年(1861)幕府が派遣した咸臨丸(かんりんまる)に乗船し小笠原の調査を行うなど実地調査の傍ら、曾祖父照任の事蹟を顕彰することに努めた。文化2年(1805)生、明治3年(1870)没。

03. 見返り柳(みかえりやなぎ)
千束4-10-8
旧吉原遊廓の名所のひとつで、京都の島原遊廓の門口の柳を模したという。遊び帰りの客が、後ろ髪を引かれる思いを抱きつつ、この柳のあたりで遊廓を振り返ったということから、「見返り柳」の名があり、
きぬぎぬのうしろ髪ひく柳かな
見返れば意見か柳顔をうち
など、多くの川柳の題材となっている。
かつては山谷堀脇の土手にあったが、道路や区画の整理に伴い現在地に移され、また、震災・戦災による焼失などによって、数代にわたり植え替えられている。

04. 新吉原花園池(弁天池)跡(しんよしわらはなぞのいけ べんてんいけあと)
千束3-22 吉原神社
江戸時代初期までこの付近は湿地帯で、多くの池が点在していたが、明暦3年(1657)の大火後、幕府の命により湿地の一部を埋立て、日本橋の吉原遊廓が移された。以来、昭和33年(1958)までの300年間に及ぶ遊廓街新吉原の歴史が始まり、とくに江戸時代にはさまざまな風俗・文化の源泉となった。
遊廓造成の際、池の一部は残り、いつしか池畔に弁天祠が祀られ、遊廓楼主たちの信仰をあつめたが、現在は浅草七福神の一社として、毎年正月に多くの参拝者が訪れている。
池は、花園池・弁天池の名で呼ばれたが、大正12年(1923)の関東大震災では多くの人々がこの池に逃れ、490人が溺死するという悲劇が起こった。弁天祠付近の築山に建つ大きな観音像は、溺死した人々の供養のため大正15年(1926)に造立されたものである。昭和34年(1959)吉原電話局(現在の吉原ビル)の建設に伴う埋立工事のため、池はわずかにその名残を留めるのみとなった。

05. 花吉原名残碑 (はなのよしわらなごりのひ)
千束3-22 吉原神社
吉原遊廓は、江戸における唯一の幕府公許の遊廓で、元和3年(1617)葺屋町東隣(ふきやちょうひがしどなり・現中央区日本橋人形町付近)に開設した。吉原の名称は、植物の葭(よし)の生い茂る湿地を埋め立てて町を造成したことにより、はじめ葭原と称したのを、縁起の良い文字にあらためたことによるという。
明暦3年(1657)の明暦の大火を契機に、幕府による吉原遊廓の郊外移転命令が実行され、同年8月浅草千束村(現台東区千束)に移転した。これを「新吉原」と呼び、移転前の遊廓を「元吉原」という。
新吉原は江戸で有数の遊興地として繁栄を極め、華麗な江戸文化の一翼をにない、幾多の歴史を刻んだが、昭和33年(1958)売春防止法の成立によって廃止された。
その名残を記す当碑は、昭和35年(1960)地域有志によって建てられたもので、碑文は共立女子大学教授で俳人、古川柳(こせんりゅう)研究家の山路閑古(やまじかんこ)による。
昭和41年(1966)の住居表示の変更まで新吉原江戸町、京町、角町、揚屋町などの町名が残っていた。

06. 鷲神社(おおとりじんじゃ)
千束3-18-7
鷲神社は、江戸時代「鷲大明神社(わしだいみょうじんのやしろ)」と称されていたが、明治のはじめ「鷲神社」と改称された。祭神は天之日鷲命(あめのひわしのみこと)・日本武尊(やまとたけるのみこと)の二神。草創は不明である。社伝によれば、天之日鷲命の祠に、日本武尊が東国征伐の帰途、熊手をかけて戦勝を祝った。この日が11月酉の日で、以後、この日をお祭と定めたという。
酉の市は、江戸中期より冬の到来を告げる風物詩として発展し、足立区花畑を「大鳥」、浅草を「新鳥」と称した。浅草はとくに浅草観音・新吉原・猿若町芝居小屋を控え、賑わいをみせた。
一の酉、二の酉、年によって三の酉とあり、世俗に三の酉があると火事が多いと言われる。
酉の市は、当初、農産物や農具の一種として実用的な熊手を売る市であった。その後、熊手は幸運や財産を「かきこむ」といわれ、縁起物として商売繁昌開運の御守として尊ばれてきた。また、八つ頭は、人の頭になる、子宝に恵まれるといわれる。

07. 飛不動 (とびふどう)
竜泉3-11-11 正寶(しょうぼう)院
正賓院は、享禄3年(1530)の創建といわれる修験寺院で、はじめ聖護院末・園城寺末から現在天台宗系の単立寺院となっている。
当寺の本尊は木造不動明王坐像で、「飛不動」の通称で知られている。名の由来は、昔、当寺の住職が大和国(奈良県)大峰山に本像を持って修行に行ったところ、一夜にして当地へ飛び帰り、人々にご利益を授けたことによると伝えられている。「飛不動」は本尊の通称だけでなく正寶院の通称ともなり、江戸時代前期、寛文年間(1661~1673)の『新板江戸大絵図』には、すでに「飛不動」の名で見える。福利増長・息災延命の祈願道場として庶民の信仰が厚く、『日本国華万葉記』や『江戸砂子』などに江戸の代表的な不動霊場の一つとして記されている。近年は航空安全の守護神として有名になり、空の安全を祈願する参詣者が多い。

08. 樋口一葉旧居跡(ひぐちいちようきゅうきょあと)
竜泉3-15
樋口一葉は明治26年(1893)7月20日、本郷菊坂町より下谷竜泉寺368番地に移り住み、この界隈を背景にして不朽の名作「たけくらべ」や「わかれ道」の題材を得た。この碑の位置は、一葉宅の左隣り酒屋の跡にて、一葉と同番地の西端に近く碑より東方6メートルが旧居に当る。
なお一葉はこのあたりを
鶉なく聲もきこえて花すゝき
まねく野末の夕べさびしも
と和歌に詠んでいる。

09. 一葉女史たけくらべ記念碑(いちようじょしたけくらべきねんひ)
竜泉3-19-1 一葉記念公園
近代文学不朽の名作「たけくらべ」は樋口一葉在住当時の竜泉寺町を中心に吉原界わいが舞台となった。これを記念して昭和26年(1951)11月、地元一葉記念公園協賛会によって建てられ、その後台東区に移管された。
碑文は女史の旧友歌人佐佐木信綱博士作並びに書による次の歌2首が刻まれている。
紫の古りし光にたぐへつべし
君こゝに住みてそめし 筆のあや
一葉女史たけくらべ記 念碑
そのかみの美登利信如らも この園に
来あそぶらむか 月しろき夜を
佐佐木信綱