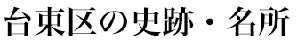01. 入谷鬼子母神(いりやきしもじん)
下谷1-12-16 眞源(しんげん)寺
入谷鬼子母神(「鬼」はツノのつかない字を用いる)は、日蓮上人の尊像とともにここ眞源寺に祀られている。眞源寺は、万治2年(1659)日融(にちゆう)上人により創建された。
鬼子母神は、鬼神般闍迦(はんしか)の妻で、インド仏教上の女神のひとりである。性質凶暴で、子どもを奪い取っては食ってしまう悪神であった。釈迦は鬼子母神の末子を隠し、子を失う悲しみを実感させ、改心させたという。以後、「小児の神」として児女を守る善神となり、安産・子育の守護神として信仰されるようになった。
入谷鬼子母神では、子育の善神になったという由来からツノのない鬼の字を使っている。
また、7月上旬、境内及び門前の道路沿いは「朝顔市」で賑わう。入谷名物となったのは明治に入ってからで、十数軒の植木屋が朝顔を造り観賞させたのがはじまりといわれている。当時この地は、入谷田圃といわれ、朝顔や蓮の栽培に適していた。
大正初期、市街化により朝顔市は途絶えたが、昭和23年(1948)復活。以後、下町情緒豊かな初夏の行事として親しまれている。

02. 子規庵 (しきあん)
都指定史跡
根岸2-5-11
正岡子規(1867~1902)は俳人・歌人・随筆家。幼名は升(のぼる)、本名は常規(つねのり)、別号を獺祭書屋主人(だっさいしょおくしゅじん)、竹の里人などといった。伊予国藤原新田(現・愛媛県松山市)に生まれ、俳句・短歌の革新を唱え、また写生文を提唱した。
新聞「日本」及び雑誌『ホトトギス』により、活動、子規庵での句会には森鴎外も訪れ、歌会には伊藤左千夫、長塚節等が参加、歌誌『アララギ』の源流となる。
著書には、俳論『俳諧大要』『俳人蕪村』、歌論『歌よみに与ふる書』、歌集『竹の里歌』、随筆『墨汁一滴』『病牀六尺』『仰臥漫録』など多い。
子規はこの場所に明治27年(1894)2月から住み、同35年(1902)9月19日病のため没す。母八重、妹律は子規没後もここに居住し、その後は子規の門弟寒川鼠骨(そこつ)が庵を守りつづけた。
昭和20年(1945)戦災によって平屋造り家屋は焼失したが、昭和25年(1950)鼠骨らにより旧規の通り再建され現在に至っている。史跡に指定されている土地の面積は405.6平方メートル。

03. 中村不折旧宅(なかむらふせつきゅうたく)
書道博物館・都指定史跡
根岸2-10-4
中村不折は、明治・大正・昭和初期の洋画家で書家であり、慶應2年(1866)7月10日江戸八丁堀に生まれた。幼名を鈼太郎という。少年時代を長野で過ごし明治20年(1887)上京し、浅井忠や小山正太郎に師事し、明治美術会に出品するほか、「小日本」新聞の挿絵なども担当していた。明治34年(1901)から4年間フランスに留学し、ラファエル・コランやジャン=ポール・ローランスの教えを受けた。帰国後は、太平洋画会や帝国美術院の会員として展覧会活動を行う一方、太平洋美術学校校長として後進の育成にも力を入れ、多くの逸材を育て美術教育にも貢献した。
書道界では、書家としての活動の他に書道博物館の創設者としても知られている。昭和11年(1936)11月3日に開館した書道博物館は、中国と日本の書道史研究上重要なコレクションを有する専門博物館で、重要文化財12点、重要美術品5点を含む1万6千点が収蔵されている。昭和20年(1945)4月の空襲で中村邸の居宅と蔵は焼失してしまったが、博物館とその収蔵資料および不折の胸像や石燈龍などは焼失を免れた。不折は大正2年(1913)から亡くなるまでの30年間、この根岸の地に住んだ。昭和18年(1943)6月6日78歳で死去、多磨霊園に葬られた。

04. 御隠殿跡(ごいんでんあと)
根岸2-19-10 薬師(やくし)寺
輪王寺宮一品法親王(りんのうじのみやいっぽんほうしんのう)は、天台座主(てんだいざす)に就き、東叡山・日光山・比叡山の各山主を兼帯したので「三山管領宮(さんざんかんりょうのみや)」とも呼ばれ、第三世から幕末の第十五世まで、親王あるいは天皇の猶子(養子)を迎え継承されてきた。当地は、この輪王寺宮の別邸「御隠殿」があった所である。
御隠殿の創建年代は明らかでないが、幕府編纂の絵図『御符内沿革図書(ごふないえんかくずしょ)』には、宝暦3年(1753)7月に「百姓地四反一畝」を買上げ、「御隠殿前芝地」としたという記述があり、同年までには建造されていたようである。
敷地はおよそ三千数百坪、入谷田圃の展望と老松の林に包まれた池をもつ優雅な庭園で、ことにここから眺める月は美しかったと言われている。
輪王寺宮は一年の内九ヶ月は上野に常在していたので、その時は寛永寺本坊(現東京国立博物館構内)で公務に就き、この御隠殿は休息の場として利用した。また、谷中7丁目と上野桜木2丁目の境からJRの跨線橋へ至る御隠殿坂は、輪王寺宮が寛永寺と御隠殿を往復するために設けられたという。
慶応4年(1868)5月、御隠殿は彰義隊の戦いによって焼失し、現在ではまったくその跡を留めていない。

05. 御行の松 (おぎょうのまつ)
根岸4-9-5
西蔵(さいぞう)院境外仏堂不動堂
江戸期から、根岸の大松と人々に親しまれ、『江戸名所図会』や広重の錦絵にも描かれた名松。現在の松はその三代目である。
初代の松は、大正15年(1926)に天然記念物の指定を受けた当時高さ13.63メートル、幹の周囲4.09メートル、樹齢350年と推定された。枝は大きな傘を広げたようで、遠くからもその姿が確認できたという。しかし、天災や環境悪化のため昭和3年(1928)に枯死。同5年(1930)に伐採した。
二代目の松は、昭和31年(1956)に上野中学校敷地内から移植したが、これも枯死してしまい、昭和51年(1976)8月、三代目の松を植えた。戦後、初代の松の根を土中より堀り出して保存し、不動堂の中にこの根の一部で彫った不動明王像をまつり、西蔵院と地元の不動講の人々によって護持されている。
御行の松の名の由来に定説はないが、一説には松の下で寛永寺門主輪王寺宮が行法を修したからともいわれる。また、この地を時雨が岡といったところから、別名時雨の松とも呼ばれた。

06. 酒井抱一住居跡(さかいほういつじゅうきょあと)
根岸5-11-35
このあたりに、江戸時代後期の俳人画家酒井抱一(1761~1828)の晩年の住居雨華庵(うげあん)があった。
抱一は姫路城主酒井忠以(たださね)の弟。少壮より文武両芸に通じ、寛政9年(1797)京都で出家、文詮暉真(ぶんせんきしん)の名を与えられ江戸に帰った。画は尾形光琳に私淑して一家をなし、また俳諧等にも秀で、谷文晁(たにぶんちょう)・亀田鵬斎(かめだぼうさい)等の文人と親交があった。
抱一は文化6年(1809)以来、この雨華庵に閑居し、土地の名物鴬に因んで鴬村(おうそん)と号し、正月15日には画始(えはじめ)、10月5日には報恩講を開き、また文政9年(1826)6月には、庵で光琳忌を催している。抱一の後を継いだ画家鴬蒲もここに住して、雨華庵二世と呼ばれた。

07. 小野照崎神社 (おのてるさきじんじゃ)
下谷2-13-14
小野照崎神社の祭神は、平安初期の漢学者・歌人として著名な小野篁(おののたかむら)である。創祀の年代は不明だが、次のような伝承がある。篁は上野国司の任期を終え、帰洛の途についた際、上野照崎(忍岡、現在の上野公園付近)の風光を賞した。仁寿2年(852)篁が亡くなったとき、その風光を楽しんだ地に彼の霊を奉祀した。その後、江戸時代をむかえ、寛永2年(1625)忍岡に東叡山寛永寺を創建するにあたり、当社を移転することとなり、坂本村の長左衛門稲荷社が鎮座していた現在地に遷した、というものである。また、一説には、忍岡から孔子聖廟が昌平橋に移った元禄4年(1691)頃に遷座したのではないかともいう。
現在の社殿は慶応2年(1866)の建築で、関東大震災や東京大空襲などを免れた。また、境内には、富士浅間神社・御嶽神社・三峰神社・琴平神社・稲荷神社・織姫神社、さらには庚申塔が現存する。
例大祭は5月19日で、3年に一度、本社の御輿渡御が行われる。

08. 下谷坂本の富士塚 (したやさかもとのふじづか)
重要有形民俗文化財
下谷2-13-14 小野照崎(おのてるさき)神社
この塚は模造の富士山で、文政11年(1828)の築造と考えられている。『武江年表(ぶこうねんぴょう)』同年の項に、「下谷小野照崎の社地へ、石を畳みて富士山を築く」とある。境内の「富士山建設之誌碑」によると、坂本の住人で東講先達の山本善光が、入谷の住人で東講講元の大坂屋甚助と協議して築造し、富士山浅間神社の祭神を勧請したという。
東講は富士山信仰の集団、いわゆる富士講のひとつ。富士山信仰は室町末期頃に起り、江戸時代中期には非常に盛んになり、江戸をはじめとして富士講があちこちで結成された。それにともない、模造富士も多数築かれ、江戸とその近郊の富士塚は五十有余を数えるに至った。しかし、いまに伝わる塚は少ない。
ここの富士塚は高さ約5メートル、直径約16メートル。塚は富士の熔岩でおおわれ、東北側一部が欠損しているものの、原形がよく保存されている。原形保存状態が良好な塚は東京に少ないので、この塚は貴重である。昭和54年(1979)5月21日、国の重要有形民俗文化財に指定された。