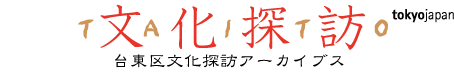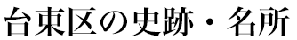01. 柳瀬美仲墓(やなせびちゅうはか)
池之端1-2-5 教證(きょうしょう)寺
柳瀬美仲(1685~1740)は徳川時代中期の歌人。かれは貞享2年(1685)、遠江国浜松に生まれ、名を方熟、字は美仲、号を隠江翁と称していた。京都に居住して詠歌を武者小路実陰の門に学び、のち、江戸に出て和歌を教授した。
はつせ路や 初音聞かまく尋ねても
まだこもりくの山ほととぎす
の一首によって、世人は美仲を「こもりくの美仲先生」と呼んでいた。著書には『秋夜随筆』その他がある。
元文5年(1740)5月17日、年56で歿した。墓石には「隠口先生美仲甫之墓」とあり、巷間に「こもりく先生」の名がもてはやされたことが知られる。

02. 旧岩崎家住宅(きゅういわさきけじゅうたく)
重要文化財
池之端1-3-45 旧岩崎邸庭園
明治から昭和にかけての実業家、岩崎久弥のかつての住宅。明治29年(1896)竣工した。
設計者はイギリスのジョサイア・コンドル。上野の博物館(現在の東京国立博物館)や鹿鳴館など数多くの官庁の建造物の設計監督にあたり、19世紀後半のヨーロッパ建築を紹介して日本の近代建築の発展に指導的役割を果たした。
同一敷地内に洋館-社交の場、和館-生活の場を併立する大邸宅は明治20年(1887)頃から建てられたが、岩崎邸はその代表例であり、現存する明治建築として貴重である。
洋館(木造二階建地下室附)正面に向かって左半分が主屋でスレート葺の大屋根をかけ、その右にやや規模の小さい棟が続く。両者のあいだの玄関部には塔屋がたち、角ドーム屋根となっている。南側のベランダには装飾の施された列柱が並び、全体的にはイギリス・ルネッサンス風となっている。洋館左側に建つ撞球室(ビリヤードルーム、木造一階建地下室附)とは地下道でつながれている。
洋館と撞球室は昭和36年(1961)に重要文化財の指定を受け、昭和44年(1969)には、和館内の大広間と洋館の袖塀一棟が追加指定を受けた。
※平成10年(1999)に、さらに宅地、煉瓦塀を含めた屋敷全体と実測図が重要文化財に指定されました。

03. 境稲荷神社と弁慶鏡ヶ井戸(さかいいなりじんじゃとべんけいかがみがいど)
池之端1-6-13
境稲荷神社の創建年代は不明だが、当地の伝承によれば、文明年間(1469~1486)に室町幕府第九代将軍足利義尚(よしひさ)が再建したという。「境稲荷」の社名は、この付近が忍ヶ岡(しのびがおか・上野台地)と向ヶ岡(むこうがおか・本郷台地)の境であることに由来し、かつての茅町(現池之端1・2丁目の一部)の鎮守として信仰を集めている。
社殿北側の井戸は、源義経とその従者が奥州へ向かう途中に弁慶が見つけ、一行ののどをうるおしたと伝え、『江戸志』など江戸時代の史料にも名水として記録がある。一時埋め戻したが、昭和15年(1940)に再び堀り出し、とくに昭和20年(1945)の東京大空襲などでは多くの被災者を飢渇から救った。井戸脇の石碑は掘り出した際の記念碑で、造立者の中には当地に住んでいた画伯横山大観の名も見える。

04. 鳥居清信墓(とりいきよのぶはか)
池之端2-4-19 妙顕(みょうけん)寺
鳥居清信は、江戸時代中期の浮世絵師で、鳥居派の始祖である。清信(俗称庄兵衛)は寛文4年(1664)浮世絵師鳥居清元の子として大坂に生まれた。貞享4年(1687)父に伴い江戸に移った。画技を父から学んだが、菱川師宣に私淑しその影響を大きく受けた。また狩野派や土佐派の画風も取り入れて独自の画風を築いた。父清元が江戸で歌舞伎の看板絵を描いていた関係で清信も役者絵を描き、ついに鳥居派の役者絵様式を完成した。以後鳥居派は江戸における歌舞伎絵の流派として定着し、代々、清信の子孫に世襲されていった。代表作に「立美人」「傘持美人」などがある。享保14年(1729)7月28日、66歳で没した。
清信は浅草法成寺(現豊島区駒込)に葬られたが、その後、墓所は妙顕寺に移された。墓石には清信夫妻および清信の父母の戒名が刻されている。

05. 川路聖謨墓(かわじとしあきらはか)
池之端2-1-21 大正(だいしょう)寺
享和元年(1801)4月25日、豊後国日田(現大分県日田市)領代官の部下、内藤吉兵衛の子として生まれ、幕臣川路光房の養子となる。幼名は弥吉または万福。通称を三左衛門・左衛門尉と言い、敬斎と号す。文政元年(1818)支配勘定出役に就任し、評定所留役・寺社奉行調役・勘定吟味役などを歴任。ついで佐渡・奈良・大坂町奉行などを経て、嘉永五年(1852)勘定奉行兼海防掛に任じられた。
翌嘉永6年(1853)、米使ペリーの浦賀、露使プチャーチンの長崎来航により、国防の急務を痛感し、江戸湾品川沖に台場を築く。特に露使とは、応接全権となって交渉に当たり、樺太の北緯50度以南、千島列島択捉島のわが国領有を主張した。井伊直弼の大老就任により左遷されるが、文久3年(1863)、外国奉行に起用された。のち病のため退官し、江戸開城前の明治元年(1868)3月15日に自害した。
『長崎日記』『下田日記』『京都日記』など、彼の日記類は貴重な史料である。

06. 北村季吟墓 (きたむらきぎんはか)
都指定史跡
池之端2-4-22 正慶(しょうけい)寺
季吟(きぎん)は江戸時代前期の歌人、俳人です。通称を九助といい、拾穂軒と号していました。はじめは祖父の宗竜、父の宗円を継いで医学を業としていました。俳人安原貞室、松永貞徳の門に入り、和歌・俳諧を学びました。元禄2年(1689)、幕府の歌学所に補せられ、元禄12年(1699)、再昌院法印の称を受けました。
著書に『徒然草文段抄』『枕草子春曙抄』『源氏物語湖月抄』その他があります。
宝永2年(1705)6月15日、82歳で逝去しました。円頂角石の正面に楷書で「再昌院法印季吟先生」と題し、右側面には丸に井桁の家紋と「花も見す郭公をも待ち出つこの世後の世、おもふ事なき」と辞世の句が刻まれています。裏面には「宝永二乙酉六月十五日、八十二歳卒」と刻んでいます。

07. 森鴎外旧居跡(もりおうがいきゅうきょあと)
池之端3-3-21
森鴎外は文久2年(1862)正月19日、石見国津和野藩典医(いわみのくにつわのはんてんい)森静男の長男として生まれた。本名を林太郎という。
明治22年(1889)3月9日、海軍中将赤松則良の長女登志子と結婚し、その夏に根岸からこの地(下谷区上野花園町11番地)に移り住んだ。この家は現在でもホテルの中庭に残されている。
同年8月に『国民之友』夏期附録として、「於母影(おもかげ)」を発表。10月25日に文学評論『しがらみ草紙』を創刊し、翌23年(1890)1月には処女作「舞姫」を『国民之友』に発表するなど、当地で初期の文学活動を行なった。一方、陸軍二等軍医正に就任し、陸軍軍医学校教官としても活躍した。
しかし、家庭的に恵まれず、長男於菟(おと)が生まれた同23年9月に登志子と離婚し、翌10月、本郷区駒込千駄木町57番地に転居していった。

08. 浄厳律師墓(じょうごんりっしはか)
都指定史跡
池之端2-5-30 妙極(みょうごく)院
浄厳律師は、江戸時代の真言宗を代表する高僧の一人である。寛永16年(1639)、河内国錦部郡鬼住村に生まれる(現大阪府河内長野市)。俗称上田氏。慶安元年(1648)、高野山で悉地院雲雪を師として出家した。字は覚彦(かくげん)。諱は雲農(うんのう)、のち浄厳(じょうごん)。妙極堂(みょうごくどう)などの号がある。修行・学問に努め、『法華経秘略要鈔(ほけきょうひりゃくようしょう)』『悉曇三密鈔(しったんさんみつしょう)』『諸真言要集(しょしんごんようしゅう)』など多数の著作がある。特に悉曇(しったん)学(梵字・梵語の音声や書法の学問)に大きな業績を残した。
寛文11年(1671)下山して、各地で教化に努めた。元禄4年(1691)、柳沢吉保の邸宅で五代将軍徳川綱吉に謁見して、普門品(観音経)を講じた。綱吉は深く帰依し、浄厳を開基として、霊雲寺を創建した(文京区湯島2丁目)。同11年(1698)、幕府より霊雲寺墓所地として当地を拝領(1300坪)、妙極院が創建された。
同15年(1702)6月27日、64歳で没した。当地のほか、郷里の延命寺にも墓がある(大阪府高河内長野市)。