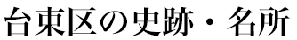01. 寛永寺旧本坊表門(かんえいじきゅうほんぼうおもてもん)
重要文化財
上野公園14 輪王(りんのう)殿
江戸時代、現在の上野公園には、寛永寺の堂塔伽藍が整然と配置されていた。現在の噴水池周辺(竹の台)に、本尊薬師如来を奉安する根本中堂、その後方(現東京国立博物館敷地内)に本坊があり、「東叡山の山主である」輪王寺宮法親王が居住していた。寛永寺本坊の規模は 3,500坪(約1.15ヘクタール)という壮大なものであったが、慶応4年(1868)5月の上野戦争のためことごとく焼失し、表門のみ戦火を免れた。
これはその焼け残った表門である。明治11年(1878)、帝国博物館(現東京国立博物館)が開館すると正門として使われ、関東大震災後、現在の本館を改築するのにともない、現在地に移建した。
門の構造は、切妻造(きりつまづく)り本瓦葺(ほんかわらぶき)、潜門のつく薬医(やくい)門である。薬医門とは、本柱が門の中心線上から前方にずれ、本柱と控柱を結ぶ梁の中間上部に束をのせ、その上に切妻屋根を乗せた門をいう。なお、門扉には上野戦争時の弾痕が残されていて、当時の戦闘の激しさがうかがえる。

02. 両大師(りょうだいし)
上野公園14 輪王(りんのう)殿
正保元年(1644)、寛永寺開山天海僧正の像を安置する堂として建立。天海僧正は慶安元年(1648)朝廷より慈眼(じげん)大師の諡号(しごう・没後に贈られる号)を受けたため、「開山堂」または「慈眼堂」と称した。
その後、天海がもっとも尊敬した平安時代の高僧慈恵(じえ)大師良源の像をも安置したため、慈眼大師天海とともに一般には「両大師」と呼ばれるようになった。
天海僧正の像は木造の坐像で、寂後まもなく制作され、多くの天海像の中でも優れたものの一つ(都指定有形文化財)。良源を描いた「元三大師画像」は、室町時代初期の制作。優れた画風を有し、江戸庶民の信仰を受けてきた(台東区指定有形文化財)。
また、江戸時代初期の銅鐘・銅燈籠が現存。いずれも、国の旧重要美術品である。

03. 旧因州池田屋敷表門(黒門)(きゅういんしゅういけだやしきおもてもん・くろもん)
重要文化財
上野公園13-9 東京国立博物館
この門は、もと因州池田屋敷の表門で丸の内大名小路(現丸の内3丁目)に建てられていた。明治25年(1892)、芝高輪台町に東宮御所の正門として移建し、のちに高松宮邸に引き継がれ、さらに昭和29年(1954)3月、ここに移して修理を加えたものである。創建時代は明らかでないが、形式と手法からみて江戸末期のものである。屋根は入母屋(いりもや)造り、門の左右に向唐破風屋根の番所を備えており、大名屋敷表門として最も格式が高い。

04. 旧東京音楽学校奏楽堂(きゅうとうきょうおんがくがっこうそうがくどう)
重要文化財
上野公園8-43
この建物は、明治23年(1890)東京音楽学校(現東京藝術大学)本館として建設された。設計は山口半六、久留正道で、わが国初の本格的な音楽ホールであり、音楽教育の記念碑的な存在である。
中央天井をヴォールト状(かまぼこ型)に高くし、視覚、排気、音響上の配慮がなされている。また、壁面や床下に藁や大鋸屑が詰められ、遮音効果をあげるなど技術的な工夫があり、貴重な建築物である。
この奏楽堂からは、滝廉太郎を初めとする幾多の音楽家を世に送り出してきたが、老朽化が進み、取壊しの危機に瀕していた。しかし、音楽関係者や建築史家を始めとする多くの人々の保存に対する努力が実り、昭和62年(1987)3月、歴史と伝続を踏まえ、広く一般に活用されるよう、この地に移築復元された。
また、移築工事とあわせて、日本唯一の空気式パイプオルガンも修復され舞台中央に甦った。昭和63年(1988)1月13日付で国の重要文化財に指定された。

05. 黒田記念館 (くろだきねんかん)
国登録有形文化財
上野公園13-9
この建物は日本の近代洋画の巨匠で、帝国美術院長であつた黒田清輝の遺言により美術奨励事業のため寄付された資金で建てられた。鉄筋コンクリート造、半地階、二階建て、東京美術学校教授岡田信一郎(1883~1932)の設計になる。
古典的な左右対称の意匠で、正面中央部に端正なイオニア式オーダーを用い、安定感のある正統的な表現でまとめられている。表面に用いられた素材は、当時流行していた茶褐色のスクラッチ・タイルで、その時代の表現が読み取れる。内部は二階の右奥に記念室があり、黒田清輝の代表作「湖畔」(1897)「智・感・情」(1897)など、約40点が展示されている。

06. 護国院(ごこくいん)
国登録有形文化財
上野公園10-18 護国(ごこく)院
護国院は、天海の弟子生順(しょうじゅん)が、釈迦堂の別当寺として、現在の東京国立博物館の右手裏に開創した。承応2年(1653)・延宝8年(1680)に、寺地を西方へ移転し、さらに、宝永6年(1709)現在地に移った。延宝8年・宝永6年の移転は、それぞれ四代将軍家綱霊廟・五代将軍綱吉霊廟の建立にともなうものである。また、昭和2年(1927)、第二東京市立中学校(現都立上野高校)建設にともない、本堂を現在の位置に移した。
現存する本堂は、釈迦堂とも呼ばれ、享保7年(1722)3月の再建。間口7間(18.2メートル)、奥行5間(13.6メートル)。唐様の建築で、中央奥の須弥壇に本尊釈迦三尊坐像を安置する。また、大黒天画像は三代将軍家光から送ら贈られたものと伝え、谷中七福神のひとつとして信仰を集めている。
庫裏の一階部分は、昭和2年の新築。東京美術学校(現東京藝術大学美術学部)教授岡田信一郎の設計で、各間取りは機能的に配置されている。昭和初期の住宅建築の風潮を良く伝えており、平成13年(2001)、国登録有形文化財に登録された。
岡田は、東京美術学校・早稲田大学で設計教育に携わるかたわら、旧鳩山一郎邸(大正13年竣工)・歌舞伎座(同年竣工)等を手がけ、和風建築の設計に手腕を発揮した人物である。

07. 旧吉田屋酒店(きゅうよしだやさけてん)
下町風俗資料館付設展示場・台東区指定有形民俗文化財
上野桜木2-10-6
かつて谷中6丁目の一角にあった商家建築。吉田屋酒店は江戸時代以来の老舗であった。旧店舗の建物が台東区に寄贈され、明治から昭和初期にいたる酒屋店舗の形態を後世に遺すため、昭和62年(1987)移築復元して、当時の店頭の姿を再現、展示している。平成元年(1989)には、一階店舗と二階部分及び道具・文書類が台東区指定有形民俗文化財となった。
棟札(むなふだ)によれば、明治43年(1910)に新築して、昭和10年(1935)に一部改築したもの。正面は一・二階とも出桁(だしげた)造りで商家特有の長い庇(ひさし)を支え、出入り口には横長の板戸を上げ下げして開閉する揚戸(あげど)を設け、間口を広く使って販売・運搬の便を図った。一階は店と帳場で、展示している諸道具類や帳簿などの文書類も実際に使用されていたもの。帳場に続く階段をのぼると三畳半と八畳の部屋があり、店員等が使用していた。向かって右側の倉庫部分は、外観のみを明治43年の写真にもとづいて復元した。店舗後方の和室部分は構造的補強の必要から増設したものである。

08. 八万四千体地蔵 (はちまんよんせんたいじぞう)
上野桜木2-6-4 浄名(じょうみょう)院
この寺の名は初め浄円院といい、寛文6年(1666)寛永寺三十六坊の一つとして創健された。享保8年(1723)浄名院となる。表門は享保年間(1716~1735)の建立。
地蔵信仰の寺となったのは第三十八世地蔵比丘妙運和尚の代からである。妙運和尚は大坂に生まれ、25歳で日光山星宮の常観庵にこもったとき地蔵信仰を得、一千体の石造地蔵菩薩像建立の発願をたてた。明治9年(1876)浄名院に入り、明治12年(1879)、さきの一千体の願が満ちると、さらに八万四千体建立の大誓願に進んだ。明治18年(1885)には地蔵山総本尊を建立。各地から多数の信者が加わり、地蔵菩薩像の数は増え続けている。
境内にある青銅製の大きな地蔵菩薩坐像は、かつて江戸六地蔵第六番の地蔵菩薩像があった深川永代寺が明治維新のとき廃寺になったためと、日露戦争の戦没者を弔うため、明治39年(1906)新たに建立されたものである。
なお、旧8月15日の「へちま供養」には、せき、ぜんそくに効験を願う人々で賑わう。

09. 寛永寺本堂(かんえいじほんどう)
上野桜木1-14-11 寛永(かんえい)寺
旧本堂(根本中堂)は現在の東京国立博物館前の噴水池あたりにあったが、慶応4年(1868)彰義隊の兵火で焼失した。そのため明治9年(1876)から同12年(1879)にかけて、埼玉県川越市の喜多院の本地堂(ほんじどう)が移築され、寛永寺の本堂となったのである。寛永15年(1638)の建造と言われる。
開口・奥行ともに7間(17.4メートル)。前面に3間の向拝(こうはい)と5段の木階、背面には1間の向拝がある。周囲には勾欄付廻縁(こうらんつきまわりえん)をめぐらしており、背面の廻縁には木階を設けて、基壇面に降りるようになっている。桟唐戸(さんからど・正面中央など)、蔀戸(しとみど・正面左右など)、板壁など、すべて素木のままである。屋根は入母屋造(いりもやづくり)、本瓦葺、二重垂木(たるき)とし、細部の様式は和様を主とする。
内部は、内陣が土間で、外陣(げじん)と同じ高さの須弥壇(しゅみだん)が設けられている。須弥壇の上に本尊その他の仏像を安置する。内陣を土間とする構造は中堂造(ちゅうどうづくり)と呼ばれ、天台宗独特のものである。現在は仮の床が張られ、内外陣ともにすべて畳敷になっている。

10. 了翁禅師塔碑(りょうおうぜんじとうひ)
都指定旧跡
上野桜木1-14-11 寛永(かんえい)寺
了翁禅師(1630〜1707)は、江戸時代前期の黄檗(おうばく)宗の僧です。俗姓は鈴木氏。出羽国雄勝郡に生まれ、幼い頃から仏門に入り、後に隠元禅師に師事します。諸国を巡るうち、霊薬の処方を夢に見て「錦袋円(きんたいえん)」と命名し、不忍池付近に薬屋を俗甥の大助に営ませます。その利益で難民救済や寛永寺に勧学寮(図書館)の設置などを行いました。
こうした功績により輪王寺宮から勧学院権大僧都法印位を贈られています。宝永4年(1707)、78歳で没し、万福寺塔頭天真院に葬られました。
本碑は了翁禅師の業績を刻んだ顕彰碑で、生前に作られたものです。元々建てられた場所や、現在の場所に移築された時期などは不明です。

11. 慈海僧正墓 (じかいそうじょうはか)
都指定旧跡
上野桜1-14-11 寛永(かんえい)寺
墓石の正面中央に、聖観音菩薩の像を彫り右側には「当山学頭第四世贈大僧正慈海」左側に「山門西塔執行宝園院住持仙波喜多院第三十世」、背面に「元禄六年癸酉二月十六日寂」と刻む。
慈海僧正は、学徳をもって知られ、東叡山護国院、目黒不動尊、比叡山西塔宝園院、川越仙波喜多院を経て東叡山凌雲院に入った。東叡山は、寛永寺一山の山号で、一山を統轄、代表する学頭には凌雲院の住職が就任することを慣例としたという。学頭は、また門主・輪王寺宮の名代をつとめうる唯一の有資格者であり、学頭の名のとおり宮や一山の学問上の師でもあった。慈海版として知られる「法華経」「薬師経」の翻刻や『四教義算注』『標指鈔』30巻の著作がある。
寛永元年(1624)目黒で生誕。70歳で没した。没後、公弁法親王の奏請によって大僧正の位が贈られた。
墓は、初め凌雲院内にあったが、昭和33年(1958)東京文化会館建設のため寛永寺に移った。

12. 尾形乾山墓碑・乾山深省蹟 (おがたけんざんぼひ・けんざんしんせいせき)
上野桜木1-14-11 寛永(かんえい)寺
尾形乾山は、琳派の創始者である画家・尾形光琳の弟である。寛文3年(1663)京都で生まれた。乾山のほか、深省・逃禅・習静堂・尚古斎・霊海・紫翠の別号がある。画業のほかにも書・茶をよくし、特に作陶は有名で、正徳・享保年間(1711~1735)、輪王寺宮公寛法親王に従って江戸に下り、入谷に窯を開き、その作品は「入谷乾山」と呼ばれた。
寛保3年(1743)81歳で没し、下谷坂本の善養寺に葬られた。しかし、月日の経過につれ、乾山の墓の存在自体も忘れ去られてしまい、光琳の画風を慕う酒井抱一の手によって探り当てられ、文政6年(1823)、顕彰碑である「乾山深省蹟」が建てられた。抱一は江戸琳派の中心人物で、文化12年(1815)に光琳百回忌を営み、『光琳百図』『尾形流略印譜』を刊行、文政2年(1819)には光琳の墓所を整備するなど積極的に尾形兄弟の顕彰に努めた人物である。墓碑及び「乾山深省蹟」は、上野駅拡張のため移転した善養寺(現豊島区西巣鴨4丁目8番25号)内に現存し、東京都旧跡に指定されている。
当寛永寺境内の二つの碑は、昭和7年(1932)、その足跡が無くなることを惜しむ有志により復元建立されたものである。その経緯は、墓碑に刻まれ、それによると現善養寺碑は、明治末の善養寺移転に際し、両碑共に当時鶯谷にあった国華倶楽部の庭へ、大正10年(1921)には公寛法親王との縁により寛永寺境内に、その後、西巣鴨の善養寺へと、三たび移転を重ねたとある。
なお、入谷ロータリーの一隅に「入谷乾山窯元碑」がある。

13. 増山雪斎博物図譜関係資料 虫塚碑 (ましやませっさいはくぶつずふかんえきしりょう むしづかひ)
都指定有形文化財
上野桜木1-14-11 寛永(かんえい)寺
虫塚は伊勢(現三重県)長島藩主である増山雪斎(ましやませっさい)が写生図譜である『虫豸帖(ちゅうちじょう)』の作画に使った虫類の霊をなぐさめるため、雪斎の遺志によって文政4年(1821)に建てられた。
増山雪斎は、宝暦4年(1754)に江戸で生まれた。本名を正賢といい、雪斎・玉園・蕉亭・石顛道人・巣丘隠人などと号した。江戸の文人大田南畝(おおたなんぽ)や大坂の豪商木村兼葭堂(きむらけんかどう)など、広く文人墨客と交流を持ち、その庇護者としても活躍した。自ら文雅風流を愛し、清朝の画家、沈南蘋(しんなんぴん)に代表される南蘋派の写実的な画法に長じ、多くの花鳥画を描いた。中でも虫類写生図譜『虫豸帖(都指定有形文化財、東京国立博物館所蔵)』は、その精緻さと本草学にのっとった正確さにおいて、殊に有名である。文政2年(1819)、66歳で没した。
虫塚は当初、増山家の菩提寺、寛永寺子院勧善院内にあったが、昭和初期に寛永寺に合併されたため、この場所に移転した。勧善院は、四代将軍徳川家綱の生母で、増山氏の出である宝樹院の霊廟の別当寺として創建された。
碑は安山岩製で台石の上に乗る。正面は、葛西因是(かさいいんぜ)の撰文を大窪詩仏(おおくぼしぶつ)が書し、裏面は詩仏と菊池五山(きくちござん)の自筆の詩が刻まれており、当時の有名な漢詩人が碑の建設に関わったことが知られる。

14. 徳川綱吉霊廟勅額門 (とくがわつなよしれいびょうちょくがくもん)
重要文化財
上野桜木1-16 寛永寺霊園
五代将軍綱吉は、延宝8年(1680)5月に兄・家綱の死に伴って将軍の座につき、宝永6年(1709)1月10日に63才で没した。法名を常憲院(じょうけんいん)という。綱吉ははじめ、善政を行ない「天和(てんな)の治(ち)」と賛えられたが、今日では「生類憐みの令」などを施行した将軍として著名。
元禄11年(1698)9月、この綱吉によって竹の台に寛永寺の根本中堂が建立された。造営の奉行は柳沢吉保、資材の調達は紀之国屋文左衛門と奈良屋茂左衛門である。又、それに伴って先聖殿(せんせいでん・現湯島聖堂)が上野から湯島に移されている。
綱吉の霊廟は宝永6年(1709)の11月に竣工したが、それは歴代将軍の霊廟を通じてみても、もっとも整ったものの一つであった。ただ、その一部は維新後に解体されたり、第二次世界大戦で焼失した。この勅額門と水盤舎(すいばんしゃ・ともに重要文化財)は、その廟所と共に、これらの災を免れた貴重な遺構である。勅額門の形式は四脚門(しきゃくもん)、切妻造(きりつまづくり)、前後軒唐破風付(ぜんごのきからはふつき)、銅瓦葺(どうかわらぶき)。

15. 徳川家綱霊廟勅額門 (とくがわいえつなれいびょうちょくがくもん)
重要文化財
上野桜木1-16 寛永寺霊園
四代将軍家綱は、慶安4年(1651)4月に父・家光の死に伴って、わずか10才で将軍の座につき、延宝8年(1680)5月8日に39才で没した。法名を厳有院(げんゆういん)という。
病気がちであった家綱時代の政務は、主として重臣の手に任されていたが、とくに後半の政治を担当した大老・酒井忠清が有名である。時代は家綱の襲職直後に起った由比正雪(ゆいまさゆき)の乱の解決を機に、ようやく安定期に入った。
家綱の霊廟の一部は維新後に解体されたり、第二次世界大戦で焼失したが、この勅額門と水盤舎(すいばんしゃ・ともに重要文化財)は、その廟所と共に、これらの災を免れた貴重な遺構である。勅額門の形式は四脚門(しきゃくもん)、切妻造(きりつまづくり)で、前後軒唐破風付(ぜんごのきからはふつき)、銅瓦葺(どうかわらぶき)。
なお、このうち水盤舎は延宝8年(1680)に家綱のために造立されたものであるが、この勅額門は昭和32年(1957)の改修時に発見された墨書銘によって、もと家光の上野霊廟の勅額門であったものを転用したものと考えられる。

16. 殉死者の墓(じゅんししゃのはか)
上野公園18 現龍院(げんりゅういん)墓地
慶安4年(1651)4月20日、三代将軍徳川家光が死去した。その後を追って家光の家臣5名が殉死、さらにその家臣や家族が殉死した。ここには家光の家臣4名と、その家臣8名の墓がある。
堀田正盛(元老中、下総国佐倉藩主)。
阿部重次(老中、武蔵国岩槻藩主)。家臣の新井頼母・山岡主馬・小高隼之助・鈴木佐五右衛門・村片某。
内田正信(小姓組番頭・御側出頭、下野国鹿沼藩主)。家臣の戸祭源兵衛・荻山主税助。
三枝守恵(元書院番頭)。家臣の秋葉又右衛門。
殉死とは、主君の死を追って家臣や家族らが自殺することで、とくに武士の世界では、戦死した主君に殉じ切腹するという追腹(おいばら)の風習があった。江戸時代になってもこの風習は残り、将軍や藩主に対する殉死者が増加、その是非が論議されるようになった。家光への殉死から12年後、寛文3年(1663)に幕府は殉死を禁止。その後、この風習はほぼ絶えた。