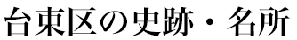01. 板碑(いたび)
台東区有形文化財
谷中5-2-22 長安(ちょうあん)寺
死者の菩提を弔うため、あるいは生前に自らの死後に備えて供養を行う(逆修[ぎゃくしゅう]という)ために建立した、塔婆の一種。板石(いたいし)塔婆・青石(あおいし)塔婆ともいう。関東地方では、秩父地方産の緑泥片岩(りょくでいへんがん)を用い、鎌倉時代から室町時代まで盛んに造られた。頂上を山形にし、その下に二段の切り込み(二条線)を造る。身部には供養の対象となる本尊を、仏像、または梵字の種子(しゅじ・阿弥陀如来の種子[キリーク]が多い)で表し、願文・年号等を刻んだ。
長安寺には、鎌倉時代の板碑3基・室町時代の板碑1基がある。
一、建治2年(1276)4月 円内にキリーク種子を刻む
二、弘安8年(1285)8月 上部にキリーク種子を刻む
三、正安2年(1300)2月 「比丘尼妙阿」と刻む
四、応永3年(1396)正月 上部に阿弥陀三尊の種子を刻む
長安寺の開基は、寛文9年(1669)とされ、同寺に残る板碑は、開基をさかのぼることおよそ400年も前である。長安寺開基以前、この地には真言宗の寺があったと伝えられ、これらの板碑と何らかの関連があったと思われる。
平成3年(1991)、台東区有形文化財として区民文化財台帳に登載された。

02. 狩野芳崖墓(かのうほうがいはか)
台東区史跡
谷中5-2-22 長安(ちょうあん)寺
明治初期の日本画家で、文政11年(1828)長府藩御用絵師狩野晴皐(せいくう)の長男として、長門国長府(現山口県下関市)に生まれる。19歳の時江戸に出て、狩野勝川院雅信(しょうせんいんまさのぶ)に師事。橋本雅邦(がほう)とともに勝川院門下の龍虎とうたわれた。
明治維新後、西洋画の流入により日本画の人気は凋落し、芳崖は窮乏に陥ったが、岡倉天心や米人フェノロサ等の日本画復興運動に加わり、明治17年(1884)第2回内国絵画共進会で作品が褒状を受け、次第に当時の美術界を代表する画家として認められた。芳崖は狩野派の伝統的な筆法を基礎としながら、室町時代の雪舟・雪村の水墨画にも傾倒、さらには西洋画の陰影法を取り入れるなどして、独自の画風を確立した。その代表作「非母(ひぼ)観音図」「不動明王図」(ともに東京芸術大学蔵)は、いずれも重要文化財である。
明治21年(1888)、天心・雅邦等とともに東京美術学校(現東京藝術大学美術学部)の創設に尽力したが、開校間近の同年11月、61歳で没した。
墓所は当寺墓地の中ほどにあり、明治20年(1887)没の妻ヨシとともに眠る。また、本堂前面には芳崖の略歴・功績を刻んだ「狩野芳崖翁碑」(大正6年造立)が建つ。
平成5年(1993)、台東区史跡として区民文化財台帳に登載された。

03. 朝倉彫塑館(あさくらちょうそかん)
国指定名勝・国登録有形文化財
谷中7-18-10
近代日本を代表する彫塑家、朝倉文夫(1883〜1964)の邸宅兼アトリエである。
朝倉は明治16年(1883)大分で生まれ、同40年(1907)、東京美術大学(現東京藝術大学)彫刻科を卒業後、当地に住居とアトリエを新築した。その後改築・増築を繰り返し、現在の建物は大半が昭和10年(1935)の竣工である。すべて朝倉が設計し、銘木、竹などの材も自ら選んだ。庭との一体感に配慮した独特の空間意匠、造詣が追求され、随所に彫塑家朝倉の個性を見ることができる。
中庭は、木造和風の住居棟と近代洋風建築のアトリエに囲まれた日本庭園で、空間の大半を水面が占めている。水面に配された五つの巨石が密度の濃い水景を創り上げ、朝倉の芸術思想の特質である自然観をもうかがえる。屋上庭園は、かつて朝倉が昭和2年(1927)に自邸とアトリエにおいて開設した「朝倉彫塑塾」の塾生が蔬菜を栽培し、日常の園芸実習の場として使われた菜園であった。昭和初期に遡る屋上庭園の事例としても貴重である。
昭和42年(1967)、故人の遺志によって一般公開され、同61年(1986)には台東区に移管され、「台東区立朝倉彫塑館」となった。
平成13年(2001)、建物が国登録有形文化財に、本館所蔵の朝倉の代表作「墓守」の石膏原型が重要文化財指定を受けた。同20年(2008)には、建物と庭一帯が国名勝の指定を受けた。

04. 幸田露伴居宅跡 (こうだろはんきょたくあと)
谷中7-18-25
幸田露伴は、明治24年(1891)1月からほぼ2年間、この地(当時の下谷区谷中天王寺町21番地)に住んでいた。
ここから墓地に沿った銀杏横丁を歩き、左に曲がると天王寺五重塔があった。五重塔は寛永21年(正保元年・1644)に感応寺(天王寺の前身)の五重塔として創建され、明和9年(1772)2月に焼失、寛政3年(1791)棟梁八田清兵衛(はったせいべえ)らにより再建された。
露伴は当地の居宅より日々五重塔をながめ、明治24年(1891)11月には清兵衛をモデルとした名作『五重塔』を発表した。
同26年(1893)1月、京橋丸山町(現中央区)へ転居したが、現在もかたわらに植わる珊瑚樹は露伴が居住していたころからあったという。
露伴は、慶応3年(1867)7月、下谷三枚橋横丁(現上野4丁目)に生まれ、すぐれた文学作品や研究成果を多数発表するなど、日本文学史上に大きな足跡をのこした。昭和22年(1947)7月没、墓所は大田区池上本門寺にある。

05. 七面坂(しちめんざか)
谷中5-11
宝暦年間の『再校江戸砂子(さいこうえどすなご)』に「宗林寺前より七面へゆく坂」とある。宗林寺(台東区谷中3丁目10番)は坂下にあるもと日蓮宗の寺、七面は坂上の北側にある日蓮宗延命院(荒川区西日暮里3丁目10番)の七面堂を指す。七面堂は甲斐国(山梨県)身延山久遠寺(みのぶさんくおんじ)の西方、七面山から勧請した日蓮宗の守護神七面天女を祀る堂である。
坂は『御府内備考(ごふないびこう)』の文政9年(1826)の書上によれば、幅2間(約3.6メートル)ほど、長さ50間(約90メートル)高さ2丈(約6メートル)ほどあった。
なお宗林寺は『再校江戸砂子』に、蛍の所在地とし、そのホタルは他より大きく、光もよいと記され、のちには、境内にハギが多かったので、萩寺と呼ばれた。

06. 銅鐘(どうしょう)
台東区有形文化財
谷中5-10-10 長明(ちょうみょう)寺
本銅鐘は、総高122.9センチ、口径75.1センチ。銘文によると天和2年(1682)初冬(10月)16日、屋代安次(やしろやすつぐ)が自らの逆修(ぎゃくしゅう)供養のために寄進した。逆修とは生前に自分の死後の冥福を祈るために仏事を修することである。撰文は下総国飯高(現千葉県匝瑳市)の日蓮宗檀林所として著名な飯高寺の僧性孝、書は長明寺四世住職日習。鋳物師(いもじ)は椎名伊予良寛(しいないよよしひろ)。鋳物師の椎名家は江戸時代初頭に多くの作例を遺し、椎名伊予吉次(よしつぐ)を初代とする江戸鋳物師の名家であった。
椎名伊予良寛は延宝9年(1681)頃から元禄13年(1700)頃にかけて活躍した鋳物師で、およそ26点の作品を残している。銅鐘が19点、銅燈籠が二対4点、宝塔・水盤が各1点である。とくに宝塔は上野寛永寺にある将軍家墓所のひとつで、四代将軍家綱(厳有院)の墓である。このように将軍家の墓の鋳造を任されている事からも、椎名良寛が当時実力を伴った著名な鋳物師であったことがわかる。

07. 岡倉天心宅跡・旧前期日本美術院跡 (おかくらてんしんたくあと・きゅうぜんきにほんびじゅついんあと)
都指定旧跡
谷中5-7 岡倉天心記念公園
日本美術院は明治31年(1898)岡倉天心が中心になって「本邦美術の特性に基づきその維持開発を図る」ことを目的として創設された民間団体で、当初院長は天心、主幹は橋本雅邦(がほう)、評議員には横山大観、下村観山らがいた。
活動は絵画が主で、従来の日本画の流派に反対し、洋画の手法をとり入れ、近代日本画に清新の気を与えた。
この場所に建てられた美術院は明治31年(1898)9月に竣工した木造二階建で、南館(絵画研究室)と北館(事務室・工芸研究室・書斎・集会室)からなり、附属建物も二、三あったといわれている。明治39年(1906)12月に美術院が茨城県五浦(いづら)に移るまで、ここが活動の拠点となっていた。
昭和41年(1966)岡倉天心史跡記念六角堂が建てられ、堂内には平櫛田中作の天心坐像が安置されている。

08. みしま地蔵尊由来(みしまじぞうそんゆらい)
谷中3-7-1 区立初音児童遊園地
太平洋戦争下の昭和20年(1945)3月4日午前8時40分頃、小雪降る中に、谷中地区はB29爆撃機の空襲を受け、死傷約500人、全半壊家屋約200戸の被害を蒙った。
戦争も終り昭和23年(1948)、当時の三崎町、初音町4丁目、真島町の有志により、三ヵ町の戦災死者70余名の霊を永久に供養するために地蔵尊が建立された。
みしま地蔵尊とは三ヵ町の町名からそれぞれ一字をとったもので(三四真地蔵)、かなで読みやすくした。

09. 笠森お仙と鈴木春信の碑(かさもりおせんとすずきはるのぶのひ)
谷中3-1-2 大円(だいえん)寺
お仙は、笠森稲荷社前の茶屋「鍵屋」の看板娘で、江戸の三美人の一人。絵師鈴木春信はその姿を、当時全く新しい絵画様式である多色刷り版画「錦絵」に描いた。お仙に関係の深い笠森稲荷を合祀している大円寺に、大正8年(1919)、二つの碑が建てられた。「笠森阿(お)仙の碑」は小説家永井荷風の撰、「錦絵開祖鈴木春信」碑は、文学博士笹川臨風が撰し、題字は、東京美術学校(現東京芸術大学美術学部)校長正木直彦の手になる。
荷風の撰文は、漢字仮名交じりの文語調である。
女ならでは夜の明けぬ、日の本の名物、五大州に知れ渡るもの、錦絵と吉原なり。笠森の茶屋かぎや阿仙、春信が錦絵に面影をとどめて、百五十有余年、嬌名今に高し。今年都門の粋人、春信が忌日を選びて、こゝに阿仙の碑を建つ。
時恰大正己未夏 六月鰹のうまい頃
五大州は日本のことで、大正己未は大正8年にあたる。

10. 伊東玄朴墓(いとうげんぼくはか)
都指定旧跡
谷中4-4-33 天龍(てんりゅう)院
伊東玄朴は、近世後期の蘭方医。寛政12年(1800)肥前国仁比山(にいやま)村(現佐賀県神埼郡神埼町)の農家に生まれる。医学を志し、長崎では通詞猪股伝右衛門(いのまたでんえもん)とドイツ人フォン・シーボルトに師事してオランダ語、西洋医学を学んだ。
文政11年(1828)、江戸に出て、本所番場町(ばんばちょう・現墨田区東駒形1丁目)で開業、翌年下谷長者町(現台東区上野3丁目)に転居し医療を施し、天保2年(1831)には、佐賀藩医となった。同4年(1833)、移転した下谷和泉橋通(いずみばしどおり・現台東区台東1丁目)の家は、象先堂(しょうせんどう)と称し、訪れる者が列をなしたという。
玄朴は、嘉永2年(1849)、幕府が発した蘭方禁止令、蘭書翻訳取締令に対抗するため、私設種痘所の建設を企画、同志に呼び掛けた。安政5年(1858)、神田お玉ヶ池(現千代田区岩本町)設立され、これが蘭方医学を幕府に認めさせる突破口となった。種痘所は翌年火災による焼失のため、玄朴宅の隣地である下谷和泉橋通に移転、再建された。万延元年(1860)には、幕府直轄となり翌年西洋医学所と改称、玄朴はその取り締まりに任命された。その後は明治新政府に引継がれ、現在の東京大学医学部の前身となった。
玄朴は、明治4年(1871)、72歳で没し、ここ天龍院(てんりゅういん)に葬られた。ドイツ人ビショップの著書の翻訳『医療正始(いりょうせいし)』は、現在でも高く評価されている。
なお、台東1丁目30番には、種痘所跡・伊東玄朴居宅跡の説明板が建っています。

11. 仮名垣魯文墓 (かながきろぶんはか)
谷中4-2-37 永久(えいきゅう)寺
幕末・明治時代の戯作者、新聞記者。本名は野崎文蔵、号を鈍亭。猫々道人(みょうみょうどうじん)などといった。文政12年(1829)江戸京橋の生まれ。長じて商家に奉公したが、戯作者を志し、式亭三馬(しきていさんば)や十返舎一九(じっぺんしゃいっく)などの戯作を耽読、諸方を遊歴して作家生活に入った。万延元年(1860)『滑稽富士詣』を書いて世に出た。
明治時代になると、当時の文明開化の世相を風刺した『西洋道中膝栗毛』『安愚楽鍋』等の作品を発表、明治開花期の花形作家となった。のち、ジャーナリズムの世界に転じ、『横浜毎日新聞』『仮名読新聞』『いろは新聞』『今日新聞』などに関係し軽妙な文章で活躍。明治12年(1879)発表の『高橋阿伝夜叉譚(おでんやしゃものがたり)』は世上を賑わせた。明治27年(1894)11月、66歳で没し、当寺に葬られた。
墓石には、聖観音を線刻した板碑(13~16世紀頃に追善のため造られた供養塔、台東区有形文化財)がはめ込まれている。
本堂右側の山猫めをと塚は、夫婦の飼猫の供養の碑で、福地桜痴の碑文が刻されている。

12. 弘田龍太郎墓・曲碑(ひろたりゅうたろうはか・きょくひ)
谷中5-4-7 全生(ぜんしょう)庵
「春よ来い」「叱られて」などの作曲家。明治25年(1892)高知県に生まれる。大正3年(1914)、東京音楽学校(現東京藝術大学)を卒業、さらに研究科を修了し母校で教えた。昭和3年(1928)、ドイツに留学、翌年に帰国し7月、同校教授に任命されたが、9月には作曲活動に専念するため職を辞した。
弘田龍太郎は、作曲や合唱指導など音楽活動に大きな足跡を残した。さらに晩年には、幼稚園を設立、園長となり幼児の音楽指導にあたった。特に中山晋平(なかやましんぺい)らとともに多くの童謡を作曲したことはよく知られている。その活動は幅広く作品は千数百曲にも及ぶという。主な作品には、「くつが鳴る」「雀の学校」「雨」「鯉のぼり」「お山のお猿」などの童謡、「浜千鳥」「小諸なる古城のほとり」「千曲川旅情の歌」などの歌曲があり、今なお愛唱されている。このほか歌劇、合唱曲、仏教音楽、舞踊曲など多方面にわたる作曲活動を行った。
昭和27年(1952)、文京区本郷の自宅でなくなり、ここ全生庵(ぜんしょうあん)に葬られた。享年60歳。平成元年(1989)春、親族によって、龍太郎夫妻が眠る墓のかたわらに、「叱られて」(清水かつら作詞)の譜面と、作曲家松村禎三の撰文が浮き彫りされる碑が建立された。

13. 三遊亭円朝墓(さんゆうていえんちょうはか)
都指定旧跡
谷中5-4-7 全生(ぜんしょう)庵
初代三遊亭円朝は、通称出淵(いずぶち)次郎吉といい、天保10年(1839)4月1日音曲師橘屋円太郎(おんぎょくしたちばなやえんたろう・出淵長蔵)の長男として江戸湯島切通町(ゆしまきりどおしちょう)に生まれた。二代目三遊亭円生の門人となり、安政2年(1855)16歳で真打ちとなる。芝居噺で人気を博し『真景累ヶ淵(しんけいかさねがふち)』や『怪談牡丹燈籠(かいだんぼたんとうろう)』『塩原多助一代記(しおばらたすけいちだいき)』などを創作した。
本業の話芸以外にも點茶(てんちゃ)、華道、聞香(もんこう)、和歌、俳句、書画など和敬(わけい)清寂の道に精通していた。建築、作庭にも秀で、自らの設計監督によって内藤新宿では、数寄屋造の家屋や茶室、更に新宿御苑を借景とした100坪余の枯山水の平庭を完成させた実績もある。
また、臨済宗の修行においても、山岡鉄舟や由利滴水(ゆりてきすい)の指導の下に参禅し、難しい公案を喝破(かっぱ)して居士号を授けられた。更に書画古美術品に対する鑑識眼は極めて高く、毎年円朝忌を中心に円朝の収集した幽霊画が公開されている。
明治33年(1900)8月11日62歳で死去した。墓石には、山岡鉄舟の筆により「三遊亭円朝無舌居士」とある。

14. 山岡鉄舟墓(やまおかてっしゅうはか)
都指定旧跡
谷中5-4-7 全生(ぜんしょう)庵
江戸開城の功労者で宮内省御用掛(くないしょうごようがかり)を務めた鉄舟は、天保7年(1836)6月10日幕臣小野朝右衛門の五男として江戸本所に生まれた。通称は鉄太郎、諱は高歩(たかゆき)、字は曠野(こうや)、猛虎、鉄舟、一楽斎は号である。
父の飛騨郡代(ひだぐんだい)在任中、高山で井上清虎に一刀流を学んだ。嘉永5年(1852)江戸に戻り槍術の師山岡静山(やまおかせいざん)の婿養子となって山岡家を嗣いだ。幕末の動乱の中で東征軍の東下に対し、駿府で西郷隆盛と会見し、勝海舟と協力して江戸無血開城を実現させた。
明治維新後は天皇の側近として宮内大書記官や宮内少輔(くないのしょうゆう)などを歴任した。公務の傍ら剣術道場を開き、明治13年(1880)には無刀流を創始した。書家としても優れ、また明治16年(1883)臨済宗普門山全生庵の開基となった。開山は越叟義格(えっそうぎかく)である。明治21年(1888)7月19日53歳で死去した。
山岡家墓所には、基壇上にある有蓋角塔の正面に「全生庵殿鉄舟高歩大居士」とある。墓所の周囲には、鉄門と言われる石坂周造(いしざかしゅうぞう)、千葉立造(ちばりゅうぞう)、松岡萬(まつおかつもる)、村上政忠(むらかみまさただ)の墓がある。