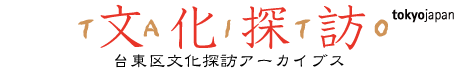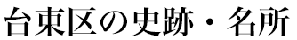01. 小花作助墓(おばなさくすけはか)
都指定史跡
谷中7 谷中霊園
小花作助(1829~1901)は江戸時代の幕臣で、はじめ作之助と称し、明治に入って作助と改めている。
幕末の文久元年(1861)11月には小笠原島開拓御用を命ぜられ渡航し、1年半にわたり現地にとどまり、その支配にあたっていた。明治維新後は新政府に仕え、明治9年(1876)12月には小笠原島内務省出張所の初代所長を命ぜられ着任。以後、3年にわたり在島し、小笠原の初期島治に尽力した。
彼は小笠原諸島の歴史を正しく理解する上で欠くことのできない人物の一人で、その墓は旧態をよくとどめている。指定面積1.619平方メートル。
なお、小花作助関係の遺品(所有者 小笠原村)は彼の事績を裏付け、小笠原初期島治の実態を明らかにすることができる貴重な史料として、東京都有形文化財(歴史資料)に指定されている。

02. 菊池容斎墓 (きくちようさいはか)
都指定旧跡
谷中7 谷中霊園
容斎(1788~1878年)は江戸時代中期の著名な歴史人物画家である。名は、武保、量平と称し、容斎は号である。与力菊池武長の養子となり、18歳の時、高田円乗の門に入って狩野派の画法を学び、絵を極むるには先哲の古跡を研究する必要を感じた容斎は、これに専心して一家を成した。容斎は有識衣冠の人物、官女遊女雅俗の人物を得意として、古代の面影をほうふつとさせる妙をきわめた。のち、京畿に遊んで古代の真髄を学び、作品は実に多数にのぼった。
88歳の時アメリカ博覧会に出品して賞牌を受けた。明治11年(1878)6月16日、年91歳の天寿を全うして没した。

03. 大原重徳墓 (おおはらしげとみはか)
都指定旧跡
谷中7 谷中霊園
幕末、明治維新期の公卿で、大原重尹(しげのぶ)の五男として享和元年(1801)10月16日京都に生まれた。天保2年(1831)従三位右近衛権中将(じゅうさんみうこんえのごんちゅうじょう)。天保9年(1838)兄重成(しげなり)の死去により大原家六代の当主となった。嘉永6年(1853)ペリー来航以来攘夷論を主張し、安政5年(1858)日米修好通商条約の勅許に反対して、水戸藩前藩主徳川斉昭の許に赴こうと密かに出京したが失敗した。文久2年(1862)左衛門督(さえもんのかみ)に任ぜられて、勅使として江戸に下り、辰の口伝奏屋敷(たつのぐちでんそうやしき)から江戸城に臨み、将軍家茂に幕政を改革し攘夷を方策を整うべしとの勅諭を伝達した。これによって一橋慶喜の将軍後見職、松平慶永(春岳)の政事総裁職(せいじそうさいしょく)就任が実現した。王政復古派の公卿の一人として活躍し、慶応3年(1867)12月9日の夜小御所で開かれた御前会議(小御所会議)では、山内豊信(容堂)、松平慶永ら公議政体派と論争し、この会議で徳川慶喜の辞官(内大臣の辞退)、納地(所領の返上)が決定した。
維新後に刑法官知事、議定(ぎじょう)、集議院長官等に任ぜられたが、明治3年(1870)官を退き、麝香間祗候(じゃこうのましこう・非職となった重臣に与えられた称号)を命ぜられた。明治6年(1873)家督を重実(しげみ)に譲り、同年11月麝香間祗候会議の発足にあたり、その発起人のひとりとなった。明治12年(1879)4月1日79歳で死去した。贈正二位。墓域右手に閑院宮載仁親王(かんいんのみやことひとしんのう)の篆額(てんがく)による勅撰神道碑(ちょくせんしんとうひ)がある。

04. 徳川慶喜墓(とくがわよしのぶはか)
都指定史跡
谷中7 谷中霊園
徳川慶喜(1837~1913)は、水戸藩主徳川斉昭の第七子で、はじめは一橋徳川家を継いで、後見職として将軍家茂を補佐しました。慶応2年(1866)、第一五代将軍職を継ぎましたが、翌年、大政を奉還し慶応4年(1868)正月に鳥羽伏見の戦を起こして敗れ、江戸城を明け渡しました。復活することはなく、慶喜は江戸幕府のみならず、武家政権最後の征夷大将軍になりました。
駿府に隠棲し、余生を過ごしますが、明治31年(1898)には大政奉還以来30年ぶりに明治天皇に謁見しています、明治35年(1902)には公爵を授爵。徳川宗家とは別に「徳川慶喜家」の創設を許され、貴族院議員にも就任しています。大正2年(1913)11月22日に77歳で没しました。
お墓は、間口3.6メートル、奥行き4.9メートルの切石土留を囲らした土壇の中央奥に径1.7メートル、高さ0.72メートルの玉石畳の基壇を築き、その上には葺石円墳状を成しています。

05. 田中芳男墓(たなかよしおはか)
台東区史跡
谷中7 谷中霊園
幕末から明治期の博物・物産学者、農務官僚。天保9年(1838)、信濃国飯田(現長野県飯田市)に医師田中隆三(如水)の三男として生まれる。
安政4年(1857)、伊藤圭介(いとうけいすけ)に入門、ここで医学・蘭学・本草学を学ぶ。文久元年(1861)芳男は圭介に従い、幕府の洋学研究機関「番書調所(ばんしょしらべしょ)」の一施設「物産所(ぶっさんじょ)」勤務のため江戸に出る。慶応3年(1867)、パリ万国博覧会に赴き、ジャルダン・デ・プラント(フランス国立自然史博物館)を日本の自然史博物館の理想とした。
明治3年(1870)、芳男は、町田久成(まちだひさなり)とともに大学南校に開局した物産局(文部省博物局の前身)で働く。ここでわが国の博物館創設のために尽力し、後の東京国立博物館、国立科学博物館、東京都恩賜上野動物園の基盤を築いた。明治4年(1871)、芳男の主唱により招魂社(靖国神社)で開かれた「大学南校物産会」は、近代博覧会の嚆矢として画期的な事業である。また芳男は、明治6年(1873)と9年(1876)には、明治政府からウィーンとフィラデルフィアの万国博覧会に派遣され、日本と西洋との文化交流にも大きな役割を果たした。
明治15年(1882)の上野の博物館開館の後、芳男は博覧会事業に重きを置き、日本初の産業博物館、神宮農業館の創設、また農会・水産会・山林会の会頭を務めるなど農林水産業の振興に貢献した。
大正4年(1915)、男爵を授けられ、翌5年6月22日、本郷の自宅にて没する。享年77歳。墓石の正面に「従二位勲一等男爵田中芳男墓」とあり、裏面に略歴が刻まれる。

06. 天王寺五重塔跡(てんのうじごじゅうのとうあと)
都指定史跡
谷中7 谷中霊園
谷中の天王寺は、もと日蓮宗・長耀山感応寺尊重院(ちょうようざんかんのうじそんちょういん)と称し、道潅山(どうかんやま)の関小次郎長耀(せきこじろうながてる)に由来する古刹である。元禄12年(1699)幕命により天台宗に改宗した。現在の護国山天王寺と改称したのは、天保4年(1833)のことである。
最初の五重塔は、寛永21年(正保元年・1644)に建立されたが、130年ほど後の明和9年(安永元年・1772)目黒行人坂(めぐろぎょうにんざか)の大火で焼失した。罹災から19年後の寛政3年(1791)に近江国(おうみのくに・滋賀県)高島郡の棟梁八田清兵衛(はったせいべえ)ら48人によって再建された五重塔は、幸田露伴の小説『五重塔』のモデルとしても知られている。総欅造(そうけやきづく)りで高さ11丈2尺8寸(34.18メートル)は、関東で一番高い塔であった。明治41年(1908)6月東京市に寄贈され、震災・戦災にも遭遇せず、谷中のランドマークになっていたが、昭和32年(1957)7月6日放火により焼失した。
現存する方三尺の中心礎石と四本柱礎石(しほんばしらそせき)、方二尺七寸の外陣四隅柱礎石(よすみばしらそせき)及び回縁(まわりえん)の束石(つかいし)20個、地覆石(じふくいし)12個総数49個はすべて花崗岩(かこうがん)である。大島盈殊(おおじまえいしゅ)による明治3年(1870)の実測図が残っており復原も可能である。中心礎石から金銅硝子荘舎利塔(こんどうがらすそうしゃりとう)や金銅製経筒(きょうづつ)が、四本柱礎石と外陣四隅柱からは金銅製経筒などが発見されている。

07. 福地源一郎(桜痴)墓(ふくちげんいちろう おうち はか)
台東区史跡
谷中7 谷中霊園
福地源一郎は、天保12年(1841)、長崎で生まれ、はじめ星泓(せいおう)、のち桜痴と号し、源一郎は通称である。明治時代前半、『東京日々新聞(とうきょうにちにちしんぶん)』(『毎日新聞』の前身)の主筆として筆を奮い、初めて社説を採用するなど、明治のジャーナリズムに大きく貢献し、新聞界を去った後は、文学者として活躍した人物である。
源一郎は、二長町(現台東1・2丁目)、浅草馬道、下谷茅町(現池之端1丁目)など区内に居を定めた。茅町にいた時期は、新聞に主権在君論を載せ立憲帝政党(りっけんていせいとう)を組織するなどの政治面、また浅草公園の整備に携わるなどの経済面で、手腕を発揮した全盛期に当たる。
文学面での源一郎は、市川団十郎(いちかわだんじゅうろう)・河竹黙阿弥(かわたけもくあみ)らと歌舞伎座を創設し、演劇改良運動などに携わる一方で、『幕府衰亡論(ばくふすいぼうろん)』『幕末政治家(ばくまつせいじか)』などの歴史書を執筆し、その業績は現在でも高く評価されている。
明治39年(1906)1月4日、66歳で没す。墓の正面には「福地源一郎之墓」、側面に本人と妻さと子の戒名が刻まれる。
福地源一郎墓は、平成7年(1995)台東区史跡として台東区区民文化財台帳に登載された。

08. 中村正直墓(なかむらまさなおはか)
都指定旧跡
谷中7-7 了俒(りょうごん)寺
明治時代の教育者、啓蒙学者。天保3年(1832)幕臣中村武兵衛の子として江戸に生まれ、幼名を釧太郎、名を正直、号を敬宇(けいう)という。昌平坂学問所に入り、佐藤一斎について儒学を学ぶ。慶応2年(1866)幕府の英国留学生派遣に取締として同行、英国市民社会の実情に触れた。
明治5年(1872)新政府に出仕し、大蔵省翻訳御用を務めるかたわら、翌年、家塾同人社を開いた。女子高等師範学校(現御茶の水女子大学)校長就任、訓盲院の開設など女子教育、障害者教育にも力を注ぎ、東京帝国大学教授・元老院議官・貴族院議員を歴任した。
明治24年(1891)6月7日、60歳で病没。葬礼は神葬で行われた。
正直は、西周(にしあまね)・神田孝平(かんだこうへい)らと明六(めいろく)社を起し、啓蒙思想の普及に努め、日本の近代化に貢献した。
訳著書に『西国立志編』『自由之理』などがある。

09. 塩谷宕陰墓(しおのやとういんはか)
都指定旧跡
谷中7-16 天王(てんのう)寺墓地
宕陰(1809~1867)は江戸時代後期の儒学者で、江戸愛宕山下で生まれた(一説には山形)。名は世弘(せいこう)、字は毅候(きこう)、号を宕陰といい、九里香園の別号もある。幼名を甲蔵と称したという。父桃蹊(とうけい)の教えをうけ、父の死後学塾を開いて教育を業としたが、貧しく、これを見かねた松崎慊堂(まつざきこうどう)が水野忠邦に推挙して、これに仕えた。水野忠邦が老中になるにおよんで、天保の改革に参画した。アヘン戦争のニュースを聞いた彼は、その原因を西欧列強の侵略であるとし、海防の急務を説き、軍艦の建造を建言した。しかし、容れられず慶応3年(1867)8月28日、年59で没した。著書には『隔鞾論 (かっかろん)』『阿芙蓉彙聞(あふよういぶん)』『籌海私議(ちゅうかいしぎ)』その他多い。

10. 護国山天王寺(ごこくざんてんのうじ)
谷中7-14-8 天王(てんのう)寺
日蓮上人はこの地の住人、関長耀(ながてる)の家に泊まった折、自分の像を刻んだ。長耀は草庵を結び、その像を奉安した。ー伝承による、天王寺草創の起源である。一般には、室町時代、応永(1394~1427)頃の創建という。『東京府志料(とうきょうふしりょう)』は「天王寺 護国山卜号ス 天台宗比叡山延暦寺末 此寺ハ本日蓮宗ニテ長耀山感応寺卜号シ 応永ノ頃ノ草創ニテ開山ヲ日源トイヘリキ」と記している。東京に現存する寺院で、江戸時代以前、創始の寺院は多くない。
天王寺は都内有数の古刹である。江戸時代、ここで「富くじ」興行が開催された。目黒の滝泉寺・湯島天神の富とともに、江戸三富と呼ばれ、有名だった。富くじは現在の宝くじと考えればいい。
元禄12年(1699)幕府の命令で、感応寺は天台宗に改宗した。ついで天保4年(1833)、天王寺と改めた。境内の五重塔(都指定史跡)は、幸田露伴の小説『五重塔』で知られていた。しかし昭和32年(1957)7月6日、惜しくも焼失してしまった。

11. 銅造釈迦如来坐像 (どうぞうしゃかにょらいざぞう)
台東区有形文化財
谷中7-14-8 天王(てんのう)寺
本像については、『武江年表(ぶこうねんぴょう)』元禄3年(1690)の項に、「五月、谷中感応寺丈六仏建立、願主未詳」とあり、像背面の銘文にも、制作年代は元禄3年、鋳工は神田鍋町に住む太田久右衛門と刻まれている。また、同銘文中には「日遼(にちりょう)」の名が見えるが、これは日蓮宗感応寺(かんのうじ)第十五世住持のことで、同寺が天台宗に改宗して天王寺(てんのうじ)と寺名を変える直前の、日蓮宗最後の住持である。昭和8年(1933)に設置された基壇背面銘文によれば、本像は、はじめ旧本堂(五重塔跡北方西側の道路中央付近)右側の地に建てられたという。『江戸名所図会(えどめいしょずえ)』(天保7年[1836]刊)の天王寺の項には、本堂に向かって左手に描かれており、これを裏付けている。明治7年(1874)の公営谷中墓地開設のため、同墓地西隅に位置することになったが、昭和8年(1933)6月、修理を加え、天王寺境内の現在地に鉄筋コンクリート製の基壇を新築してその上に移された。さらに昭和13年(1938)には、基壇内部に納骨堂を増設し、現在に至る。
なお、「丈六仏(じょうろくぶつ)」とは、釈迦の身長に因んで一丈六尺の高さに作る仏像をいい、坐像の場合はその2分の1の高さ、八尺に作るのが普通である。
本像は、明治41年(1908)刊『新撰東京名所図会(しんせんとうきょうめいしょずえ)』に「唐銅丈六釈迦」と記され、東京のシンボリックな存在「天王寺大仏」として親しまれていたことが知られる。
平成5年(1933)に、台東区有形文化財として区民文化財台帳に登載された。