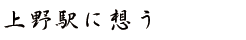上野駅
上野駅は、鉄道黎明期の明治16年(1883)に初の私鉄日本鉄道の上野・熊谷間を結ぶ起点駅として開業しました。明治39年(1906)の「鉄道国有法」により国有化され、東北、上越方面へと向かう列車の起点駅「北の玄関駅」として発展してきました。昭和62年(1987)の日本国有鉄道(国鉄)分割民営化により分割され、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)上野駅となり、今日に続いています。現在では、JR東日本、そして地下には東京メトロ(東京地下鉄)銀座線、日比谷線が乗り入れています。昭和2年(1927)に上野・浅草間を結んで営業を開始した銀座線は、アジア最初の地下鉄路線です。(台東区上野7丁目)

上野駅構内
現在の上野駅には、東北新幹線、秋田新幹線、上越新幹線、長野新幹線、山形新幹線、常磐線、常磐・成田線、宇都宮線、高崎線、山手線、京浜東北線の11路線、そして東京メトロの2路線が乗り入れ、一日35万人に及ぶ乗客が往来する、まさに北の玄関口となっています。上野駅は、明治、大正、昭和、そして平成と130年に及ぶ歴史を刻み、東北、上越から東京へと上る人、そしてこの駅から東北、上越へと旅立つ人々の思い出深い地ともなっています。
昭和57年(1982)に大宮-盛岡間に開業した東北新幹線は昭和60年(1985)に上野-大宮間が開通し、さらに平成3年(1991)には上野-東京間が開通しました。その後の平成14年(2002)から駅舎の複合化が始まり、駅舎内にはショッピングモールやギャラリーなどが整備されました。また、駅中央口から上野公園口を結ぶ連絡橋「パンダ橋」が架けられて駅での乗降に加えて、これらの施設の利用客や通行客で賑わっています。

中央改札口前のグランドコンコース

グランドコンコースの両側に配されたショッピングモールや飲食街の複合施設が、駅舎内の賑わいを作り出しています。
上野の地名は、江戸時代初期に現在の上野恩賜動物園から上野東照宮に掛けて伊賀上野の大名藤堂高虎(とうどうたかとら)の下屋敷があった事に由来しています。藤堂家の墓所は、現在でも上野恩賜動物園内に残されています。慶応4年(1868)の彰義隊と新政府軍の戦い、いわゆる「上野戦争」により上野寛永寺の大半は焼失し、明治5年(1872)に上野公園として整備されました。
明治5年(1872)に竣工した東京-横浜間の鉄道開通に続いて、「陸奥青森までの鉄道築造の儀」「東京より青森までの鉄道建言書」などが「米欧使節団」としてイギリスに渡った岩倉具視等により建議され、明治13年(1880)にはアメリカ人技師ジョゼフ・クロフォードが東京-青森間の鉄道敷設について予備調査を行いました。そして、明治14年(1881)に「日本鉄道会社」の創設が認められ、翌15年(1882)に川口-熊谷間の工事着工、開通に続いて、16年(1883)7月28日には上野-熊谷間が開業しましたが、日本鉄道会社の創設、そして上野-熊谷間の鉄道敷設に尽力した岩倉具視は、この日を見ずに7月20日に58歳で生涯を閉じました。当時は、上野停車場(ステーション)-熊谷間を1編成の列車が2往復し、2時間24分を要して運行していましたが、同年10月には同線は熊谷から本庄まで延長され、一日3往復で運行されました。明治18年(1885)には煉瓦造りの駅舎が建設されましたが、大正12年(1923)の関東大震災の際に全焼してしまいました。
クロフォードは、その功績から「日本の鉄道の父」とも呼ばれています。後に北海道開拓使顧問として官営幌内鉄道建設に尽力し、北海道旧幌内線三笠駅跡には、鉄道記念館に隣接してクロフォード公園が設けられています。また、小樽市交通記念館には、クロフォードの功績を顕彰して銅像が建てられています。

上野駅構内では、乗り継ぎや東北、上越方面の列車を待つ人々で賑わい、往来の切れ目がありません。

構内では、昭和の再建当時の面影を残す鉄柱も見掛けられます。

駅舎3階のパンダ橋口を出ると上野駅前の商業地域と上野公園口の芸術文化地域を結ぶ東西自由通路に出ます。(通称パンダ橋)

パンダ橋口では、巨大なパンダが出迎えてくれます。

公園口近くに建つパンダ橋の碑

広々としたパンダ橋
上野公園のパンダ見物の客や修学旅行の生徒の声も聞こえます。
上野広小路口脇には、「あゝ上野駅」(作詞:関口義朗、作曲:新井英一、歌:井沢八郎)の歌碑が建っています。高度成長期の昭和30年から40年代に掛けて、当時金の卵と呼ばれた集団就職の若者たちが上野駅に降り立ちました。「どこかに故郷の香りを乗せて入る列車のなつかしさ・・」のフレーズに当時の集団就職の若者の故郷を想う姿が蘇ります。


上野駅
上野駅は、鉄道黎明期の明治16年(1883)に初の私鉄日本鉄道の上野・熊谷間を結ぶ起点駅として開業しました。明治39年(1906)の「鉄道国有法」により国有化され、東北、上越方面へと向かう列車の起点駅「北の玄関駅」として発展してきました。昭和62年(1987)の日本国有鉄道(国鉄)分割民営化により分割され、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)上野駅となり、今日に続いています。現在では、JR東日本、そして地下には東京メトロ(東京地下鉄)銀座線、日比谷線が乗り入れています。昭和2年(1927)に上野・浅草間を結んで営業を開始した銀座線は、アジア最初の地下鉄路線です。(台東区上野7丁目)

駅舎3階のパンダ橋口を出ると上野駅前の商業地域と上野公園口の芸術文化地域を結ぶ東西自由通路に出ます。(通称パンダ橋)

パンダ橋口では、巨大なパンダが出迎えてくれます。

公園口近くに建つパンダ橋の碑

広々としたパンダ橋
上野公園のパンダ見物の客や修学旅行の生徒の声も聞こえます。
上野広小路口脇には、「あゝ上野駅」(作詞:関口義朗、作曲:新井英一、歌:井沢八郎)の歌碑が建っています。高度成長期の昭和30年から40年代に掛けて、当時金の卵と呼ばれた集団就職の若者たちが上野駅に降り立ちました。「どこかに故郷の香りを乗せて入る列車のなつかしさ・・」のフレーズに当時の集団就職の若者の故郷を想う姿が蘇ります。