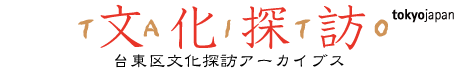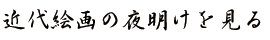黒田清輝は、フランス留学中の明治24年(1891)、25歳の時にソシエテ・デザルティスト・フランセのサロンで作品「読書」入選。さらに明治26年(1893)にはソシエテ・ナショナル・デ・ボザールのサロンにおいて「朝妝(ちょうしょう)」により入選を果たしています。黒田清輝の画風は、コランに学んだアカデミックな基礎の上に、当時隆盛した印象派の影響を受けて外光を採り入れた、明るく濁りを知らない静謐な筆致にありました。当時の日本の洋画の暗く沈んだ、いわゆる脂(やに)派と呼ばれた旧派とは一線を画した外光派(紫派)として、当時の画壇に衝撃を与えました。
智・感・情(明治30年(1897)、重要文化財)
第2回白馬会展に出品された裸体をモチーフとした3点からなる作品。明治30年の第2回白馬会展に出品され、フランス留学時に描いた「朝妝(ちょうしょう)」公開と同じく、裸体画として賛否両論を巻き起こしました。明治33年(1900)に開催されたパリ万国博覧会に"Etudes de Femmes"(女性習作)と改題して出品され、銀賞を受賞しています。

読書(明治24年(1891))
明治23年(1890)から移り住んだグレー= シュル=ロワンの娘マリア・ビヨーをモデルにした作品。ソシエテ・デザルティスト・フランセのサロンに入選し、フランス画壇へのデビュー作ともなりました。鎧戸を通して射し込む光の中で読書に勤しむ女性が、静謐な筆致で描かれています。

舞妓(明治26年(1893)、重要文化財)
帰国後に訪れた京都を題材として描かれた作品。鴨川の明るい水面を背景として出窓に座した舞妓が描かれていますが、画面右手の女中の少女の半身が切り取られ、印象派の表現に通ずる動勢が生き生きと表現されています。

湖畔(明治30年(1897)、重要文化財)
避暑のために滞在した箱根の芦ノ湖畔で、後に夫人となる照子を描いた作品。「湖畔」として知られていますが、明治30年の第2回白馬会展では「避暑」として発表されました。明治33年に開催されたパリ万国博覧会に「智・感・情」と共に出品されました。