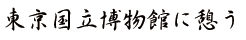本館第13室 / 刀剣

青漆銀流水門半太刀大小拵(せいしつぎんりゅうすいもんはんだちのだいしょうこしらえ) / 安土桃山-江戸時代・16-17世紀
本館第13室 刀剣
神庭: ここは刀剣を展示しているコーナーです。刀剣は熱心なファンの方がいらっしゃる世界ですね。国宝の太刀、このように太刀の姿が綺麗に残っていますね。これは、平安時代(11世紀)の作品です。これは重要美術品です。この太刀は、鎌倉時代(13世紀)の作品です。これも刀身の形が非常に綺麗に残っていますね。これも鎌倉時代13世紀の太刀です。いずれも今から700年以上前のものですね。こういった太刀が現在でもきちっとした形をもって、それも金属が錆びでるのではなく、光って残っているということは、考えてみれば大変不思議なことではあります。太刀、あるいは刀は鉄でできておりますから、大変に錆びやすいものです。放っておけばすぐに錆びて全体が茶色くなり、そして一部分は金属が溶けます。ですから、刀や太刀はそうした状態にならないために、始終手入れをしなければなりません。もし手入れを怠り錆びたら、そこを研がなければいけませんね。そういうことを平安時代から今日までの間、何回繰り返すかによって刀の減り方が違ってきます。始終錆びさせたものは、刀がどんどん減っていきます。しかしここに展示されている太刀や刀は、あまり研ぎ減っていないと考えられております。それは何を意味するかと言いますと、始終点検をして、錆びないように手入れがされていたという証拠なんですね。もしそういう手入れや点検がなされなければ、これらの太刀は今、針のような細い姿でここに展示しなければならないくらい、細くなっていたと思います。
Q: こちらにはどの程度の数の刀や太刀が所蔵されているんですか。また、これらを定期的に研ぎや手入れをされているのですか。
神庭: 当館には、おおよそ1000本の伝世した刀剣類がございます。それを短期間で全部手入れするのは大変ですから、小分けにして定期的に見るようにしています。当館の歴史は140年ほどですが、はるかそれ以前の時代からどうやっていたかというのが大変重要ですね。つまり、点検をし、問題があればその部分だけを手入れしていくということで、私たちが今考えている予防保存と非常にあい通ずる部分がある訳です。傷んでから研ぐのではなくて、傷まない、つまり錆がふかないように常に予防、手入れをしていくというのがあって、初めて何百年の時代を越えて、形がきちっと残っていくと思います。この刀剣は私たちが目指している予防保存の非常に良い見本お手本になると思います。(下段に続く)
Q: ショーケースに触ると実際に動くんですか。ケースの中のコレクションは置いたままで、固定されていないのですか。
神庭: 動きます。なぜこの下の部分のカバーが外れるかと言いますと、装置が動くためにはカバーを押し出さなければなりませんので、動く時には全部外れてしまいます。文化財は、ただ置いてあるだけになります。ここにあるすべてのケースにこのような免震装置が入れてありますので、個別の転等防止のための対策というのは特になくても大丈夫です。ただし、器形によっては、さらに対策を要することは言うまでもありません。
Q: 予想されている震度はどの程度なのですか。
神庭: この免震装置では、阪神淡路大震災で起こりました、大体800~1000galぐらいの大きさでしたら、横揺れに対しては十分に耐えられるように計算されています。
本館10室 浮世絵と衣装
神庭: 本館の第10室は、浮世絵と小袖と、簪(かんざし)類、つまり江戸近世の町方の風俗を扱う展示コーナーです。こちらの面にありますのが、浮世絵ですね。向こうの面にありますのが小袖です。小袖と浮世絵が同じ部屋にあるのは、まさに近世町方の風俗を代表するものだからということの他に、保存的な観点から大切なことがあります。どちらも天然の染料を使っているということです。天然染料で小袖は染織されています。一方、浮世絵も天然染料を用いて刷られているんです。浮世絵は紙に天然染料、もちろん顔料も使っておりますけど、小袖は絹に天然染料、どちらも繊維に対して天然染料を使うということで、非常に似た性格です。いずれも光に対してとても脆弱な作品です。天然染料は強い光に当たると褪せて消えてなくなり易いものです。浮世絵と小袖が一緒に置かれていることは、どちらもある程度の暗さに置くということで、保存の観点からもとても良いコーナーになっているのではないかと思います。
では、どの程度の明るさが好ましいかといいますと、明るさは照度という単位で表しますが、退色をなくすという意味では真っ暗が一番良いわけです。でも真っ暗ですとお客様が見ることができません。(下段に続く)

免震装置に守られた仁清の壷

免震構造の展示ケース
神庭: 当館を代表する仁清の壷です。形も図柄もとても綺麗な壷ですが、地震や振動にはある意味大変危険な形をしていますよね。底の面が非常に細くて、重心が比較的上にありますので、倒れやすいプロポーションをしています。この展示ケースに免震装置がない場合は、万が一のことを考えて、テグスというナイロン製の釣り糸で四方を引っ張り、転倒しないような工夫をする必要があります。そのような展示は、当館や他の美術館、博物館でもご覧になることがあると思いますが、できれば無い方が見栄えが良く、ものそのものに集中できますね。そこで当館では、展示ケースの下の部分に、地震の際に展示ケース全体が揺れずに、この部分だけが揺れるような免震装置を独立展示ケースにはすべて設置してあります。水平方向ならあらゆる方向へ動くことができます。(右上段に続く)

浮世絵のコーナー

浮世絵と衣装は、繊細な照明と工夫によって守られて展示されていました。
したがって、どこまで明るくすることができるかという話なんですが、浮世絵は50ルクスという明るさにしております。50ルクスまで明るくすれば、何とか色や形、雰囲気を理解することができます。この浮世絵も、ほぼ50ルクスで展示されています。暗くすれば安全ですが、見えにくくなります。保存のために良くて、見え易くするにはどうしたら良いか。そこが、我々が考えなければいけないところです。保存もし公開もする、それをうまく結びつけること、そのために作り出されたのが皆さんの目の前にある展示ケースです。これは単純な額縁ではなくて展示ケースです。非常に薄いものですが、額縁型のケースです。ガラスがないように見えますのは、低反射ガラスがつけてあるためで、ほとんど反射光がありません。まるで浮世絵を手に取って見ているかのようです。もっと近づいて見て頂いて構いません。このガラスは叩いて割れるようなものではありません。照明は下方からと上からも当たってます。光が均等に当たるように工夫されていて、非常に見やすくなっています。保存のために暗くしてあるけれども、より良く見せるための工夫もしています。
浮世絵は遠くから眺めていたのでは、作品の細部が見えません。近づくことによって浮き出た表現としての空摺までみることができます。それを可能にしたのがこの展示です。
神庭: ここは刀剣を展示しているコーナーです。刀剣は熱心なファンの方がいらっしゃる世界ですね。国宝の太刀、このように太刀の姿が綺麗に残っていますね。これは、平安時代(11世紀)の作品です。これは重要美術品です。この太刀は、鎌倉時代(13世紀)の作品です。これも刀身の形が非常に綺麗に残っていますね。これも鎌倉時代13世紀の太刀です。いずれも今から700年以上前のものですね。こういった太刀が現在でもきちっとした形をもって、それも金属が錆びでるのではなく、光って残っているということは、考えてみれば大変不思議なことではあります。太刀、あるいは刀は鉄でできておりますから、大変に錆びやすいものです。放っておけばすぐに錆びて全体が茶色くなり、そして一部分は金属が溶けます。ですから、刀や太刀はそうした状態にならないために、始終手入れをしなければなりません。もし手入れを怠り錆びたら、そこを研がなければいけませんね。そういうことを平安時代から今日までの間、何回繰り返すかによって刀の減り方が違ってきます。始終錆びさせたものは、刀がどんどん減っていきます。しかしここに展示されている太刀や刀は、あまり研ぎ減っていないと考えられております。それは何を意味するかと言いますと、始終点検をして、錆びないように手入れがされていたという証拠なんですね。もしそういう手入れや点検がなされなければ、これらの太刀は今、針のような細い姿でここに展示しなければならないくらい、細くなっていたと思います。
Q: こちらにはどの程度の数の刀や太刀が所蔵されているんですか。また、これらを定期的に研ぎや手入れをされているのですか。
神庭: 当館には、おおよそ1000本の伝世した刀剣類がございます。それを短期間で全部手入れするのは大変ですから、小分けにして定期的に見るようにしています。当館の歴史は140年ほどですが、はるかそれ以前の時代からどうやっていたかというのが大変重要ですね。つまり、点検をし、問題があればその部分だけを手入れしていくということで、私たちが今考えている予防保存と非常にあい通ずる部分がある訳です。傷んでから研ぐのではなくて、傷まない、つまり錆がふかないように常に予防、手入れをしていくというのがあって、初めて何百年の時代を越えて、形がきちっと残っていくと思います。この刀剣は私たちが目指している予防保存の非常に良い見本お手本になると思います。

免震装置に守られた仁清の壷

免震構造の展示ケース
神庭: 当館を代表する仁清の壷です。形も図柄もとても綺麗な壷ですが、地震や振動にはある意味大変危険な形をしていますよね。底の面が非常に細くて、重心が比較的上にありますので、倒れやすいプロポーションをしています。この展示ケースに免震装置がない場合は、万が一のことを考えて、テグスというナイロン製の釣り糸で四方を引っ張り、転倒しないような工夫をする必要があります。そのような展示は、当館や他の美術館、博物館でもご覧になることがあると思いますが、できれば無い方が見栄えが良く、ものそのものに集中できますね。そこで当館では、展示ケースの下の部分に、地震の際に展示ケース全体が揺れずに、この部分だけが揺れるような免震装置を独立展示ケースにはすべて設置してあります。水平方向ならあらゆる方向へ動くことができます。
Q: ショーケースに触ると実際に動くんですか。ケースの中のコレクションは置いたままで、固定されていないのですか。
神庭: 動きます。なぜこの下の部分のカバーが外れるかと言いますと、装置が動くためにはカバーを押し出さなければなりませんので、動く時には全部外れてしまいます。文化財は、ただ置いてあるだけになります。ここにあるすべてのケースにこのような免震装置が入れてありますので、個別の転等防止のための対策というのは特になくても大丈夫です。ただし、器形によっては、さらに対策を要することは言うまでもありません。
Q: 予想されている震度はどの程度なのですか。
神庭: この免震装置では、阪神淡路大震災で起こりました、大体800~1000galぐらいの大きさでしたら、横揺れに対しては十分に耐えられるように計算されています。
本館10室 浮世絵と衣装
神庭: 本館の第10室は、浮世絵と小袖と、簪(かんざし)類、つまり江戸近世の町方の風俗を扱う展示コーナーです。こちらの面にありますのが、浮世絵ですね。向こうの面にありますのが小袖です。小袖と浮世絵が同じ部屋にあるのは、まさに近世町方の風俗を代表するものだからということの他に、保存的な観点から大切なことがあります。どちらも天然の染料を使っているということです。天然染料で小袖は染織されています。一方、浮世絵も天然染料を用いて刷られているんです。浮世絵は紙に天然染料、もちろん顔料も使っておりますけど、小袖は絹に天然染料、どちらも繊維に対して天然染料を使うということで、非常に似た性格です。いずれも光に対してとても脆弱な作品です。天然染料は強い光に当たると褪せて消えてなくなり易いものです。浮世絵と小袖が一緒に置かれていることは、どちらもある程度の暗さに置くということで、保存の観点からもとても良いコーナーになっているのではないかと思います。
では、どの程度の明るさが好ましいかといいますと、明るさは照度という単位で表しますが、退色をなくすという意味では真っ暗が一番良いわけです。でも真っ暗ですとお客様が見ることができません。

浮世絵のコーナー

浮世絵と衣装は、繊細な照明と工夫によって守られて展示されていました。
したがって、どこまで明るくすることができるかという話なんですが、浮世絵は50ルクスという明るさにしております。50ルクスまで明るくすれば、何とか色や形、雰囲気を理解することができます。この浮世絵も、ほぼ50ルクスで展示されています。暗くすれば安全ですが、見えにくくなります。保存のために良くて、見え易くするにはどうしたら良いか。そこが、我々が考えなければいけないところです。保存もし公開もする、それをうまく結びつけること、そのために作り出されたのが皆さんの目の前にある展示ケースです。これは単純な額縁ではなくて展示ケースです。非常に薄いものですが、額縁型のケースです。ガラスがないように見えますのは、低反射ガラスがつけてあるためで、ほとんど反射光がありません。まるで浮世絵を手に取って見ているかのようです。もっと近づいて見て頂いて構いません。このガラスは叩いて割れるようなものではありません。照明は下方からと上からも当たってます。光が均等に当たるように工夫されていて、非常に見やすくなっています。保存のために暗くしてあるけれども、より良く見せるための工夫もしています。
浮世絵は遠くから眺めていたのでは、作品の細部が見えません。近づくことによって浮き出た表現としての空摺までみることができます。それを可能にしたのがこの展示です。

青漆銀流水門半太刀大小拵(せいしつぎんりゅうすいもんはんだちのだいしょうこしらえ) / 安土桃山-江戸時代・16-17世紀