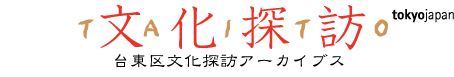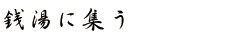六竜鉱泉(台東区池之端3丁目)[台東区写真連盟撮影]
江戸の銭湯の起源は、江戸時代後期の「湯屋」に始まると言われています。嘉永6年(1853)に著された喜田川守貞の「守貞漫稿」には江戸時代の風俗が描かれ、江戸の多くの銭湯は男女別、上方では混浴だったと記されています。また入浴の習慣は、古くは6世紀に渡来し、聖徳太子の導入政策により広まった仏教の身を浄める「沐浴(もくよく)」に始まるとも言われています。そのため仏教寺院の七堂伽藍のひとつは浴堂となっています。寺院での沐浴は、全国に国分寺の建立を勧めた光明皇后(710-760)も努めた仏教布教に伴う慈善事業として提供した「施浴(せよく)」に始まるようです。そのため、今日懐かしさを誘う銭湯の建物の形式は、正安元年(1299)の「一遍上人絵伝」(歓喜光寺所蔵)に描かれた風呂の光景からも、寺院の伽藍を模した「宮造り」であった事が窺えます。(下段に続く)

梅の湯(台東区蔵前4丁目)

梅の湯(台東区蔵前4丁目)
宮造りは外観だけでなく、室内は高い格子状に組まれた格天井と高窓が設えられています。
現在の銭湯の多くは明治以降の創業で、建物の多くは昭和初期に建てられたものとの事ですが、江戸川区にある「あけぼの湯」は安永2年(1773)の創業、中央区銀座の金春通りにある「金春湯」は文久年間(1861-1863)創業と伝わっています。金春(こんぱる)の由来は、江戸時代にこの地に金春流狂言の家元があったからと言われています。

日の出湯(三ノ輪1丁目)[台東区写真連盟撮影]

鶴の湯(東上野5丁目)[台東区写真連盟撮影]

鶴の湯(浅草橋5丁目)[台東区写真連盟撮影]

三筋湯(三筋2丁目)[台東区写真連盟撮影]

梅の湯の富士(蔵前4丁目)

三筋湯の富士(三筋2丁目)[台東区写真連盟撮影]

樋口一葉記念館近くにある一葉泉(竜泉3丁目)

一葉泉には、釜掃除のための巨大な箒が掛かっていました。

梅の湯の富士(蔵前4丁目)

三筋湯の富士(三筋2丁目)[台東区写真連盟撮影]

樋口一葉記念館近くにある一葉泉(竜泉3丁目)

一葉泉には、釜掃除のための巨大な箒が掛かっていました。