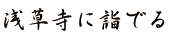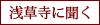浅草神社
浅草神社は、浅草寺のご本尊を感得した土師中知、檜前浜成、竹成の三氏を祀っている事から「三社」と言われ、浅草の総鎮守の神です。現在の社殿は、慶安2年(1649)、徳川三代将軍家光の寄進で、本殿・弊殿・拝殿を渡り廊下で繋ぐ「権現形式」となっており、国の重要文化財に指定されています。

浅草寺二天門
二天門は、浅草神社の鳥居に向かって右手に建っており、国の重要文化財に指定されています。現在の門は、その形式と技法より慶安2年(1649)頃に建立されたと言われています。また、現在の二天像は上野寛永寺の巌有院(徳川四代将軍家綱)霊廟より拝領したもので、増長天と持国天は仏教の守護神である四天王の二天で武装した姿をとり、増長天は南方、持国天は東方を守護しています。

宝蔵門に掛かる大草鞋(わらじ)
高さ4.5m、幅1.5m、重さ500kg、稲藁2,500kgが使用されています。昭和16年(1941)から、山形県村山市の有志によりこれまで7回にわたり、奉納されています。現在の草鞋は、平成20年(2008)に奉納されたものです。草鞋の壮大さは仁王さまの力を示していて、魔除けとされています。

二天門の増長天(左)と持国天(右)



浅草寺の五重塔は、天慶5年(942)に平公雅(たいらのきんまさ)の寄進により建立されましたが、その後に数度にわたり倒壊、焼失しました。徳川三代将軍家光により慶安元年(1648)に建立され国宝に指定されていた五重塔も、昭和20年(1945)の戦災により惜しくも焼失しました。昭和48年(1973)、牌殿・書院等を備えた新たな五重塔院が再建されました。

浅草寺宝蔵門
安房守平公雅が武蔵守に補任された天慶5年(942)にその補任の祈願成就の御礼として建立されたと、縁起に記されています。内部は三層で、上部二層は収蔵室となっていて宝物等が納められています。

浅草寺雷門
天慶5年(942)に平公雅により創建されたと伝えられますが、建立当初は駒形付近にあったと言われています。鎌倉時代以降に現在の地に移築され、風神、雷神が配されました。現在の門は、慶応元年(1865)の大火により焼失した後に、昭和35年(1960)に松下電器創始者の松下幸之助氏の寄進により、復興再建されました。今日では、東京・浅草の象徴となっています。

雷門に掛かる大提灯は、直径3.3m、高さ3.9m、重さ700kgと壮大なもので、提灯の下部には金龍が刻まれています。


浅草寺雷門の雷神、風神像
雷門正面の左に雷神、右に風神のニ神が祀られていますが、慶応元年(1865)の大火により頭部を残して焼失したため、明治7年(1874)に塩川蓮玉氏による補刻により修復されました。 雷門の背面には、平櫛田中刻の「天龍」、菅原安男刻の「金龍」の二体の龍神が祀られています。