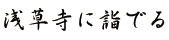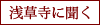四万六千日の風景

浅草寺境内で催されるほおずき市
観音さまのご縁日は毎月18日となっていますが、それとは別に室町時代頃から新たに「功徳日」(くどくび)が設けられました。月に一日のこの日に参拝すると、百日、千日の参拝に相当する功徳が得られると言われます。7月10日は「四万六千日」(しまんろくせんにち)と呼ばれ、その功徳は4万6千日、約126年分に相当する言われます。四万六千日の由来には、一升枡(ます)を満たす米粒が、46000粒程である事から、一升と一生を掛けたとの説もあります。参拝者の長寿や無病息災への祈願が偲ばれます。
四万六千日には、「ほおずき市」が縁日に賑わいを添えます。ほおずきは鵜呑みにすると癪を切り、子どもの虫の気を取り去るとされ、薬草としても用いられてきました。浅草寺のほおずき市は、次第に賑わいを生み、今では四万六千日と言えば、ほおずき市と言われるまでになりました。また江戸時代の文化年間(1804-18)には雷除けのご利益があるとして「赤とうもろこし」が店先に並び、人々はこれを門口に吊していましたが、明治時代に入り赤とうもろこしが不作となったため、浅草寺から赤とうもろこしの代わりに「雷除」のお札が授与されるようになりました。

多くの参拝者で賑わうほおずき市

ほおずき市に並ぶ見事なほおずき

ほおずき市に並ぶ見事なほおずき