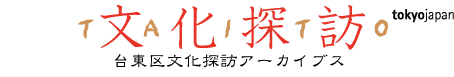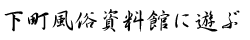懐かしい物売りの声が聞こえました。
Q : 館内で聞こえている物売りの声ですが、解説文には、主として関東地方の声が入っているという事ですが。僕らの時代では、「ロバのパン屋さん」が思い出されますね。
石井 : 物売りの声は地方によって違いがありますが、ここでは主として東京の物売りの声を流しています。元々は物売りですから、各地から物を売りに来ます。例えば孫太郎虫(民間薬)なんかは仙台から来ていますね。ロバのパン屋さんというのは皆さん結構おっしゃいますね。
Q : 台東区内でも今でも物売りの声が聞こえますね。魚屋さんですか、豆腐屋さんもありますね。
石井 : 豆腐屋さんは今ではバイクなどで移動するようですが、ラッパだけは下町に限らず、他の地域でも使っていますね。(右上段に続く)
たとえば名物を売りにしたり、孫太郎虫なんかそうですけど、あれなんか色々な話を聞くと同じようなトーンで他の下町じゃない地域でも売りに来たと聞きます。ある場所でそういった売り方が発生して各地に点在していきますが、元は一緒ということですね。今では、竹竿(たけざお)屋さんが売るのはスチールのパイプになりましたけど、売るときの文句は一緒ですね。
Q : 昭和の初期だとキセルの羅宇屋(らおや)さんっていたような気がしますが。
石井 : 雷門の前に30、40年前ぐらいまではあったんじゃないですかね。写真では割合残ってたりしますね。(左下段に続く)

七色唐辛子売り
図版は「東京風俗志」(明治32・34年)、「風俗画報」(明治37年)、「浪花風俗図絵」(明治43年)より

竈(かまど)には、火吹き竹もありました。

お稲荷さんには、いろいろなお供えが上がっていました。

門口の初午の行灯には、様々な地口(しゃれことば)が書かれています。
Q : 一階の展示室で拝見した長屋は大正期の情景ということでしたが、電気製品を見ると昭和のものだと思われますが、時代は特には明確に設定されていないのですか。
石井 : 関東大震災の前がポイントのひとつとしてあります。一階展示室の"電気製品"は、大正時代には広く普及していた電灯だけですが、様々な生活道具には時代の幅があります。東京がたどってきた経緯を見ますと、まず震災があって、その後の戦災、それから昭和30年代の東京オリンピックを契機とした再開発。その三つをポイントとして大きな町並みへ、そして生活の変化があります。昭和40年代初頭から、このような下町の庶民の文化を残していこうという動きがありました。その頃は高度経済成長の時代、語弊があるかもしれませんが、乱開発で町並みが変わってきたことに危機感を持った人たちがそのような運動を担ってきました。
東京オリンピックに合わせて首都高速道を造り、新幹線を開通させ、街角からはゴミ箱が消えてと、色々なところに影響があったわけですね。そのように町並みが変わっていくことによって生活も変わってくる。古き良き昔ながらの下町の生活というようなものも失われていってしまう。もちろん大量生産大量消費の時代の始まりでもありました。そのような時代背景があり、博物館を造って残していこうということが下地にあります。そのことを踏まえて東京の歴史を振り返ってみますと、まず震災までは江戸の継続だったわけですね。大きな破壊がなくて緩やかな近代化だったのですが、関東大震災によって下町地域を中心に焼け野原になって、まったく新しい都市に生まれ変わるという、そう言っても過言でもない変化がありました。その変化以前の生活空間を想定しています。(右段に続く)
Q : この資料館の基準のようなものがありますか。
石井 : 基準として、関東大震災がまずあります。それ以前の江戸の風情を残していた下町の町並み、そしてその暮らしを残していくことを目的とています。江戸時代まで遡ってしまうと、その当時に開館を目指していた人たちの時代からも隔絶してしまうので、体験したこと、あるいは自分の幼い頃に経験していたその時代を残すことが目的のひとつでした。また、最初にお話しましたような昭和30年代の東京オリンピックも大きな変革のひとつです。その少し前から電化製品があふれ、生活も大きく変化しています。それまでは何百年もの間、火を使って、かまどでご飯を炊いていたのが、電気釜でスイッチポンになりました。何百年、何千年という間、手を使って洗濯していたことが電気洗濯機に取って代わりました。そういう物がだんだん下町の生活に浸透してきました。町並みを顧みると長屋が取り壊されてビルになりました。
一階の展示は、震災前の生活を後世に残していこうという展示方針に基づいています。生活空間に実際に使われていたものを置くことによって、情景展示として、その意図を表しています。二階では昭和30年頃の一画があり、一階の展示との生活の差違が分かるようになっています。さらに当時の実物を置いて、見るだけではなく触ることができ、質感や使い勝手も合わせて伝えています。さらに季節の催しといった年中行事のように具体的な形を成してないものも展示できます。現在展示しているのは初午(はつうま)です。長屋の軒先に地口行灯(じぐちあんどん)を飾り、路地の奥には稲荷があることから、初午が稲荷の祭りであることが分かります。(次ページに続く)

七色唐辛子売り
図版は「東京風俗志」(明治32・34年)、「風俗画報」(明治37年)、「浪花風俗図絵」(明治43年)より

竈(かまど)には、火吹き竹もありました。