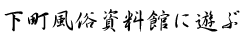下町の生活に根差した展示が魅力です。

台東区立下町風俗資料館専門員の石井広士さん
台東区立下町風俗資料館の専門員の石井広士さんに、同資料館の成り立ち、そして展示品やその時代背景について聞きました。(2008年12月取材)
Q : 一般に郷土資料館の目的は、郷土の歴史や文化遺産の管理が目的としてあるかと思いますが、下町風俗資料館の位置付けはいかがですか。
石井 : 一般的な郷土資料館は、郷土の歴史や文化を通史的に幅広く扱っているところが多いと思いますが、私たちの資料館は時代で言えば近代以降のいわゆる生活史に重点を置いています。
Q : 私たちはあまり学術的だとか、一般社会的というような区分けはしませんけども、いわゆる学問的価値としての位置付けとはどこにあるのでしょう。研究分野から言うと社会文化学、文化史なのでしょうか。
石井 : そうですね。この資料館では中でも台東区などの下町と呼ばれる地域に特化しています。
Q : 昭和の時代の下町の写真集などもそうなんですが、東京の下町というのは、生活パターンやスタイルが地方都市とはずいぶん違うのでしょうか。
石井 : まずひとつ言える特徴は、下町気質のようなものですね。それは一階に再現している長屋という家屋形態とも深く関係しています。たとえば壁一枚隔てて隣人が住んでるので気易い付き合いなど、いわゆる下町気質が生まれました。またこうした家屋形態の基礎は江戸時代に形成されたものですが、木と紙でできた家屋が密集している地域というのは非常に火災に弱いんですよね。火災が起きてしまったらそれで全ておしまいなので、お金を貯め込んでいても仕方ない、つまり「宵越しの金は持たない」という、いわゆる"江戸っ子気質"の形成にも家屋形態が大きく関わっています。
Q: 一階に再現されてる長屋や商家は、台東区のどの辺にあったのでしょうか。
石井 : どこということではないですが、調査の基になったのは橋場(台東区橋場)にあった長屋であると聞いています。(右上段に続く)

Q : 今でも収集されてるわけですか?時代というよりは台東区にちなんだものと限定されているんですか。
石井 : 限定はしてませんし、生活資料についてはしづらい部分があるんですね。しかし明らかに北海道でしか使わないような物はありません。おおよそは多くの地域で使われた物や東京で使われたものですね。生活道具だけではありませんので、例えば写真や絵はがき、図版の類、錦絵なども結構沢山あります。そういう意味では多少範囲は広がります。
Q : 海外や地方からもお出でになるんですよね。そのような際には、若干体験として違うというか、関東周辺だと懐かしいと思うかもしれませんが、地方の人から見れば若干違うのかなと思います。
石井 : そうですね。けれども道具の視点からだとあまり変わらないと思います。もちろん地方の方もすごく多くて、上野という土地柄もすごくあるんでしょうけれども。例えば感想帳には様々な方が書かれるんですが、自分のところとの違いよりも、懐かしさのようなものを書かれる方は多いです。火鉢や箪笥(たんす)、部屋の狭さ、そういった所に関する感覚なのかもしれないですね。自分の所は違ったという感覚よりも共通性を持とうとする意識が感想としては多いように思います。(右段に続く)

特定の場所というよりも、下町といわれている地域の中では一般的な家屋形態ということで、どこの地域ということではありません。現在でも二階建ての長屋は見掛けますが、平屋はほとんどありません。二階建ても少なくはなってきていますが。二階屋か一階屋かでも生活形態はずいぶん違ってきます。たとえば台所の造りが一階の長屋ですと引き窓というのがあってその下で煮炊きをすることになります。二階屋だとまったく家屋の形態が変わってきますので、そのようなところでも生活の変化が発生します。古いスタイルの基準ということで平屋の長屋が残っていた頃を再現していますが、特定のある場所ということではありません。
Q : この資料館の大きな特長はありますか。
石井 : 生活空間をそのまま展示していることです。個々の資料の展示ということではなくて、一階の長屋や商家のように情景展示をすることによってそれぞれの資料が生きてくると思います。たとえば、冬の生活の展示の状況などでは、その特長は顕著だと思います。火鉢があって、炬燵(こたつ)があります。こたつは今の子供たちも知ってはいるんですが、まったく燃料が違っています。今は電気こたつですが、ここにあるこたつは炭火を使っています。入口には七輪があって、もちろん押入れにも様々な道具が収納されていますが、こちらの道具も炭火を使って衣服のしわを伸ばすものです。どれほど炭が生活の中で必需品であったかということが分かります。こたつだけ展示してもあまり説得力が無いと思うのですが、その生活空間を再現することによって、炭火というものが昔の生活の中では重要であり、燃料として不可欠のものであったということを提示し伝えることができると思います。ですから個々の価値というものは少ないかもしれないのですが、トータルに生活空間を再現することによってそれぞれの意義を互いに高めあったり、付加価値が生まれることはあると思います。
Q: これらを収集された際は、どこかで解体されたり廃棄される可能性がある物を集められたのですか。
石井 : そういう場合もありますけれども、直接寄贈して下さる方からの連絡ですね。ですから、ほとんどが使用されたものです。多いのが親御さんが亡くなられたり、ご自身が高齢になって子供に与えても捨てられてしまうからとか、または引越しですとか古い家を建て替えるからというようなことが多いですね。二階には銭湯の番台がありますが、これは廃業した際に寄贈されたもので、この資料館でも一番巨大な資料です。また同じ二階のカフェを再現した一画に浅草の資料を集めているところがあります。そこに粗悪な紙で作られた大道芸の秘伝書を展示していますが、これはいわゆる香具師(やし)が怪しげな芸をしていて、これのやり方をここに書いてあるから必ず家に帰ってから開けるんだよと、幼気(いたいけ)な子供を言いくるめて、ほとんど電車賃だけを残して有り金はたいて買わせてしまいます。中身を見ると、こよりで箸を切る方法、それが図入りで書いてあって十銭の値段がついています。これが明治32年頃で、当時蕎麦(そば)が一銭ちょっとですからかなりの金額です。まるっきり嘘なんですけど「内務省お届け済み」って書いてあります。これは実際に北園孝吉という作家が、大正時代の子供の頃に靖国神社で実際に掴まされたことがあるということをエッセーでも書いていますが、このような資料はなかなか残るものではないと思いますし、このような残そうという意識が持たれないものも、この資料館では収集しています。(次ページに続く)

台東区立下町風俗資料館専門員の石井広士さん