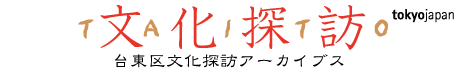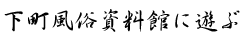懐かしい生活の記憶がここにあります。

長屋の路地では、様々な住人に出会います。
Q : 実際の展示の場で生活するなどの試みをされたことはありますか?
石井 : 実際に寝起きするようなことはありません。ただ、当時の建物や室内を再現して、そこに本物の生活道具を置いています。同じように再現展示している博物館はたくさんありますが、多くの場合は立ち入り禁止としたり、中に人形を置いたりするので、いくらリアルに再現しても客観視するしかありません。しかしこの博物館では、そのような制限や人形を置いたりすることはなくて、展示を視覚だけでなく体験として実感できます。物売りの声や、柱時計の音、向かいから聞こえる三味線の音などのように、当時の生活や情景全体を含めた展示という考え方です。最初に震災前の大正時代というお話はしていますが、厳密に言えば日めくりカレンダーは今日の日付です。時計も合わせてあります。現在の展示では、季節で言えば初午が近いので地口行灯が飾られています。大正時代の今日のこの時間に、来館者がたまたまここを訪れたという形態にしています。一階の展示では今でも大正時代の人々が住んでいるように想定しています。もちろん生活道具も当時見かけた物を揃えています。
厳密にはその後に使われた物も含まれてはいますが、たとえば駄菓子屋さんの店先にある駄菓子や玩具は自由に触れることができますし、実際の駄菓子屋を再現しています。多少時代がずれる物や、お菓子については今でも手に入る昔ながらのお菓子、その代わりになる実際のお菓子を置いています。このような当時の生活を体感できるようにしています。
Q : 通行人が行き来するのも面白いと思うのですが、あえて人は見せないということですか。
石井 : 例えば職員が当時の格好をするということですか。それもひとつの試みだとは思います。それに近い試みとして、職員はユニフォームとして法被(はっぴ)を着ています。
Q : 来館者の皆さんは、自身の子供時代に見たり、遊んだような物によって、記憶を呼び戻すのでしょうか。
石井 : この博物館の来場者の層は、とても幅が広いのです。小学生からご年配の方まで、また外国のお客さんも沢山いらっしゃいます。11-12%は外国からの方です。もちろん日本の幅の広い来館者と外国の方が持つ感覚は全然違いますが、不思議なのは中学生や大学生が大正時代の設定の展示を見て「懐かしい」と言うんですね。お婆ちゃんの家のようであるとか。年配の方にしても、展示は震災前ぐらいですから、平屋で座り流しという生活空間なので実際に体験された方はあまりいないはずなんですが、やはり懐かしいという感想が一番多くあります。(右段に続く)


見る側にとっては厳密に大正10年頃である必要はあまりないのではないかと思います。たとえば江戸時代であれば「歴史」になってしまいます。それは明らかに私たちとは距離があります。けれどもこのような展示では、なんとなくノスタルジーを感じる「記憶」ですので、歴史とは違っていると思います。実際に体験していなくても、畳がある狭い長屋の部屋に和箪笥があり、ちゃぶ台があり、そして火鉢があるような空間を、若い人たちも昔の日本としての記憶を前提として見てるのではと思います。ですから年代の幅はあるのですが、幼い来館者の方は別ですが、大学生くらいの方は自身が知らないはずなのに懐かしいという感想が多いです。そこが他の博物館や美術館、郷土資料館とは違って、歴史への興味とは違ったノスタルジーとして自身が実際に住んでいる国の少し以前の時代へとつながる感覚があるのではないでしょうか。
Q : 一般的には、文化とは生活文化や、いわば公の文化に区分けしたくなりますね。けれども文化の大半は生活文化だろうと思われますね。
石井 : 文化とは遺伝的に獲得したもの以外は全て文化だと言われていた先生もいました。そういった意味では際限が無いのですが、ここでは文化と言うより生活といった方がぴったりとするのかもしれませんね。(次ページに続く)

長屋の路地では、様々な住人に出会います。