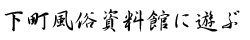ここに住まう人々の息づかいが聞こえます。

手汲みのポンプ、洗い桶に洗濯板に懐かしさがよみがえります。

一階展示室の長屋について
Q : これは昔懐かしい洗濯板ですね。
石井 : これ裏表が違っています。実際に触っていただくことで姿勢のつらさなども分かっていただけると思います。今、表に向いているほうは洗い用です。こちらが濯ぎ(すずき)用です。極めて機能的なんですが、濯ぎのときは泡が両脇に流れていくようになっています。逆にすると泡が溜まります。最初は流れてしまっては困るので。これも昔から使われていたものではないですよね。西洋から来たウォッシュボードですから。それが大正時代頃には広く普及したといわれています。たとえば、これがケースの中に納められている事とは全然違うと思います。小さなお子さんなんかも、これで実際に洗濯する姿勢や、裏表の違いにも触れられます。こういった体験を通して、ものの資料的な意味や価値が伝わるんじゃないかと考えています。(下段に続く)

Q : お稲荷さんや御神籤(おみくじ)も季節によっての違いはありますか。
石井 : たとえば、お稲荷さんの場合は、今ここに飾ってあるように初午(はつうま)が稲荷の祭りになります。あとは11月8日に「ふいご祭り」があります。火を扱う職業の人たちが道具に感謝する祭りです。その際は、お稲荷さんにお供え物を出したりします。あるいは正月もそうですね。正月に鏡餅をお供えしたり、季節に合わせて長屋の生活や稲荷にも季節ごとの展示を行っています。五月のゴールデンウィーク明け頃には台東区内の各地域が祭礼のシーズンに入りますので、その際には祭礼にちなんだ展示になります。そうすると祭礼提灯や花飾りなどを出します。提灯などに三つ巴の神社紋がありますが、いつも外国のお客様には、あれはどういう意味なんだと聞かれます。宗教性を感じるのでしょう。
普通の生活空間を再現しても、そういったものに溢れているんですね。招き猫ひとつとっても、民間信仰の表れですね。たとえば七福神もそうですし、門口に飾ってあるやいかがしなどもそうです。これは節分の時に飾るものですけども、厄除けの意味があります。鰯(いわし)の頭も信心からの語源になったものです。悪疫退散の役割を持っています。
雑巾も毎朝しぼって濡らしておきます。草履(ぞうり)だとか下駄を履いていた頃はどうしても足が汚れてしまうので、上がる時には雑巾は欠かせないものでした。雑巾も生活の中で必要なものとして置いています。ここには職人が住んでいるので、職人の衣服もここに洗濯して干しています。
ここには雪ノ下(ユキノシタ科の多年草)がありまして、向こう側の路地には万年青(おもと、ユリ科の常緑多年草)がありますが、このような鉢植えも展示品の一部です。観葉植物などは、明治頃には、大変値段が上がってブームを迎えました。雪ノ下は観葉植物というよりは民間療法に用いられました。あかぎれとか、ちょっとした病気、怪我に雪ノ下を使っていました。
また、奥に行きますと便所があります。大正時代になると、長屋の各戸に便所が付きます。大正時代はこのトイレ事情の変革期でした。大正10年頃になりますと、糞尿処理が近隣の農村で処理することが出来ない時代になっていました。昔は糞尿が売れ、江戸時代では糞尿が肥料として高額で取引されていました。大正時代になって人口が急激に増え、糞尿の量も膨大になってくるとその処理もできなくなりました。そうして、やがて行政側が汲み取りを始めます。それが始まったのが震災の少し前あたりです。(右下段に続く)
一階展示室の大店(商家)について
石井 : ここには、招き猫の置物があります。こちらが帳場で、そしてこちらが作業場です。ここで製造して、帳場で売り買いのやり取りをします。この帳場は商家の中でも主人と番頭以外には座れない神聖な場所です。商家では、招き猫と大黒様の置物がやはりメジャーな存在です。福助の置物の場合もありますが、縁起物ですね。この商家の二階に繋がる階段は復元ですので、実際に上がることは出来ませんが、通りに面していた商家の多くは二階建てでした。この程度の規模になりますと使用人は6、7人くらいでしょうか。中には住み込みの奉公人もいて、そういう人たちの部屋に使ったりしていました。資料館の建物上の制限がありますので、商家の入口部分だけを再現しています。(下段に続く)

この竹篭(たけかご)は今で言う非常持ち出し用の篭です。これは火災に弱い江戸の名残りです。建物が密集していることや、紙と木で出来ていることから当時の建物は火災に非常に弱かった。いざとなったら大事なものを放り込んで担いで逃げるためのものです。用心籠と呼ばれています。

こちらが便所で、汲み取り口がここにあります。これを開けると本当なら甕(かめ)が入っています。その中に糞尿を溜めて、溜まったのをそこから汲み出します。
井戸はありますけれども、水道の蛇口がありませんので、この吊手水器(つりちょうずき)が手洗いの道具になります。この中に水を入れて、シャワーのように水が出て手を洗うことができます。


手汲みのポンプ、洗い桶に洗濯板に懐かしさがよみがえります。