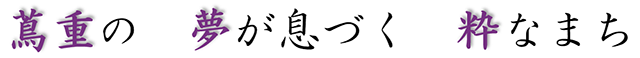2025年放送の大河ドラマ「べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~」。主人公の「蔦重」こと蔦屋重三郎は寛延3年(1750)、江戸・新吉原(現在の台東区千束)で生まれ育ち、その才能を開花させました。本ページでは蔦屋重三郎の生涯や区内のゆかりの地について紹介しています。
蔦屋重三郎の歩み
-
1750(寛延3)年丸山重助の子として江戸・新吉原に生まれる。本名は丸山柯理(からまる)。後に吉原で茶屋「蔦屋」を経営する喜多川氏の養子となる。
-
1772(安永元)年吉原大門前に書店「耕書堂」を開業。
-
1773(安永2)年頃「吉原細見」の販売を開始。
-
1774(安永3)年版元・蔦屋としての処女作となる遊女評判記「一目千本」(花すまひ)を刊行。
-
1775(安永4)年吉原細見の版元・鱗形屋が無断重版による処罰を受けて経営が悪化。これを機に吉原細見の出版に本格的に乗り出す。
-
1780(安永9)年頃朋誠堂喜三二の黄表紙を出版したことを機に出版業を拡大。
-
1781(天明元)年頃狂歌ブームとなり、大田南畝や山東京伝らとの交流が深まる。
-
1783(天明3)年吉原細見が蔦屋の独占販売となる。耕書堂が日本橋通油町(現在の中央区大伝馬町)に進出。
-
1787(天明7)年松平定信が老中に就任、「寛政の改革」が始まる。
-
1791(寛政3)年寛政の改革により、山東京伝の洒落本が取締対象となり、版元である蔦屋重三郎も財産の一部を没収される。
-
1792(寛政4)年頃喜多川歌麿の美人大首絵を発行、大ヒットとなる。
-
1794(寛政6)年東洲斎写楽の役者絵を発行。翌年にかけて約140作品を次々に発表する。
-
1797(寛政9)年脚気により48歳で病没。
蔦屋重三郎ゆかりの地
- 蔦屋重三郎ゆかりの地
- 蔦屋重三郎関係者ゆかりの地
- 同時代の史跡・名所等
-
1耕書堂跡(千束4丁目)蔦屋重三郎は吉原大門前の五十間道に書店「耕書堂」を開業し、書籍の販売と出版を開始した。

-
2正法寺(東浅草1丁目1-15)蔦屋重三郎の菩提寺。墓所は震災・戦災で失われたため、現在は蔦屋家の墓碑と重三郎母子顕彰碑が建つ。

-
1平賀源内の墓(橋場2丁目22-2)平賀源内はエレキテルの復元で有名な本草学者、戯作者。蔦屋重三郎に依頼され「吉原細見」序文を執筆。

-
2山東京伝机塚の碑(浅草2丁目3)山東京伝は、蔦屋重三郎の下、多くの洒落本や滑稽本を執筆した戯作者。表面には晩年の京伝撰「書案之紀」が刻まれている。

-
3佐竹商店街(台東3丁目・4丁目)蔦屋重三郎の盟友で戯作家の朋誠堂喜三二は秋田佐竹藩の江戸留守居役。佐竹商店街付近に佐竹藩の江戸屋敷があった。

-
4葛飾北斎の墓(元浅草4丁目6-9)葛飾北斎は、蔦屋重三郎の下で黄表紙の挿絵などを担当。重三郎の死後に「富嶽三十六景」を発表し、絶頂期を迎える。墓は誓教寺に立つ。

-
5蜀山人の碑(上野公園4-1)蜀山人(大田南畝)は蔦屋重三郎と交流が深く、狂歌や黄表紙、滑稽本と多彩なジャンルで活躍した幕臣。

-
1見返り柳(千束4丁目10-8)吉原遊郭帰りの客が、名残を惜しみつつ、この柳のあたりで振り返ったことからその名がついた。

-
2吉原大門跡(千束4丁目15)塀と堀に囲まれていた吉原遊郭唯一の出入口。現在は交差点やバス停にその名が残る。

-
3吉原神社(千束3丁目20-2)かつて吉原遊郭に祀られていた5つの稲荷神社と近隣の吉原弁財天が合祀され、現在の吉原神社となった。

-
4山谷堀公園(東浅草1丁目4-9)元は隅田川に注ぐ水路で、「猪牙舟」でこの水路を通り吉原遊郭に行くことが、贅沢な遊びとして流行した。

-
5浅草寺(浅草2丁目3-1)都内最古と言われている古刹。江戸中期には境内に茶屋や見世物が立ち並び、江戸の信仰と文化の中心として栄えた。