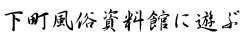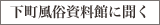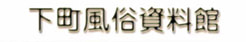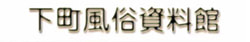懐かしい駄菓子屋の店先では、瞬く間に子供の頃がよみがえります。軒下には、陳皮(ちんぴ、みかんの皮を干して薬用にもちいた)や酸漿(ほおずき)、大蒜(にんにく)や布海苔(ふのり、洗濯糊や洗髪にも使用)などが下げられています。
明治・大正・昭和のまちがありました。
台東区は、明治・大正の頃までは、江戸の名残りが強くありましたが、大正12年(1923)の関東大震災、そして昭和20年(1945)の戦災により、そのほとんどの面影を失いました。また、昭和30年代後半の東京オリンピックを契機として、まちは再開発されて一段とその様相を変えてしまいました。このような江戸期から営々と築かれた文化、そして明治・大正・昭和の名残りが次々と失われつつある事から、庶民の歴史や生活、そしてその記憶を次の世代に伝える目的から、台東区立下町風俗資料館は昭和55年(1980)10月1日に閑寂な不忍池の畔に開館しました。

館内一階では、関東大震災以前の大正期の下町の一角が再現されています。懐かしい井戸端、そして洗濯途中の洗濯盥(たらい)、洗濯板、たわしなどが置かれています。鋳物製の手押しポンプは、明治末以降から普及しました。ブリキ管の先の木綿の袋は、ごみや鉄分を漉すための工夫でした。

竈(かまど)の脇には、薪(たきぎ)が置かれ、その脇にはごみ箱がありました。各戸のごみは、大正7年(1918)以降から東京市全域で公的に回収されるようになりました。路地には、ごみ箱が置かれるようになりました。井戸やごみ箱も、路地と同じように長屋の住人が共同使用していました。

年老いた母と娘が営む駄菓子屋の居間の卓袱台(ちゃぶだい)、姫鏡台、針箱や絎台(くけだい)などから、つつましく簡素な生活が見えます。井戸や路地を共有したこのような長屋の暮らしから、下町独特の人情や気質が生まれました。

台所の板の間には、揚板(あげいた)があり、用具や食物の貯蔵庫にも使われていました。

銅壷職人の住まいには、桐箪笥、長火鉢などの他に、主人の手習いの三味線箱も見えます。

年老いた母と娘が営む駄菓子屋の居間の卓袱台(ちゃぶだい)、姫鏡台、針箱や絎台(くけだい)などから、つつましく簡素な生活が見えます。井戸や路地を共有したこのような長屋の暮らしから、下町独特の人情や気質が生まれました。

台所の板の間には、揚板(あげいた)があり、用具や食物の貯蔵庫にも使われていました。

銅壷職人の住まいには、桐箪笥、長火鉢などの他に、主人の手習いの三味線箱も見えます。