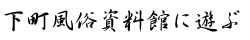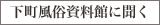懐かしい銭湯の番台、金盥(たらい)を抱えたおかみさんが暖簾(のれん)を上げて入ってきそうです。(絵 : 戸塚はる奈)


館内にある銭湯の番台は、台東区蔵前にあった銭湯「金魚湯」で実際に使用されていたものです。番台に上り、しばし銭湯の番頭さんの心持ちを味わう事が出来ます。

平和紀念(記念)東京博覧会(大正11年(1922)3月10日-7月31日に開催)
上野公園において開催された平和紀念(記念)東京博覧会(大正11年(1922))で企画展示された「文化村」の文化住宅は、当時理想とされたモダンな住宅のモデルとなりました。台東区には、その文化住宅のひとつでもあった同潤会アパート「上野下アパート」(東上野、昭和4年(1929))なども残っています。
三種の神器が、生活習慣を変えました。
高度成長期の昭和28年(1953)2月にNHK、8月には日本テレビが開局して、テレビの時代が始まりました。その後、洗濯機・冷蔵庫・掃除機の、いわゆる家庭用電気製品の「三種の神器」がもてはやされ、さらに電気炊飯器も登場して、それまでの家事や生活習慣を大きく変える事になりました。これらに拍車を掛けた契機は、昭和34年(1959)の皇太子御成婚のパレードのテレビ中継、そして昭和39年(1964)の東京オリンピックでした。

トースター

電気炊飯器


館内にある銭湯の番台は、台東区蔵前にあった銭湯「金魚湯」で実際に使用されていたものです。番台に上り、しばし銭湯の番頭さんの心持ちを味わう事が出来ます。

平和紀念(記念)東京博覧会(大正11年(1922)3月10日-7月31日に開催)
上野公園において開催された平和紀念(記念)東京博覧会(大正11年(1922))で企画展示された「文化村」の文化住宅は、当時理想とされたモダンな住宅のモデルとなりました。台東区には、その文化住宅のひとつでもあった同潤会アパート「上野下アパート」(東上野、昭和4年(1929))なども残っています。