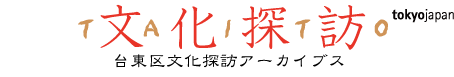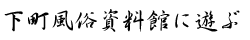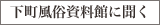江戸の名残りをとどめる生活様式
明治時代は、西欧に倣(なら)った風俗や文化が採り入れられましたが、江戸時代からの習慣も永らく続いていました。大正時代頃までは、近代化と共に古くから使用されてきた生活用品や習俗などが残っていました。昭和時代へと至ると、大正期の西欧への憧れからアメリカ文化のモダンへとその眼差しは移り、東京の市街にはダンスホール、カフェー、映画館やレビュー館などが続々と建てられました。

箱膳
箱膳は、卓袱台(ちゃぶだい)などのひとつの食卓が普及するまで、用いられていました。普段は食器類をしまっておき、食事の際は、蓋(ふた)を返して使用しました。(明治時代)

銅製蒸し器
水を入れて熱して、その蒸気で茶碗蒸しなどの蒸し物を作りました。(昭和初期)

大根のかつらむき器
東京大学内の食堂の厨房で用いられていたもの。大根を差してハンドルを回転させる。(昭和初期)

お歯黒道具
お歯黒は、嫁いだ女性の既婚の証として歯を黒く染める風習で明治初期まで広く行われていました。(明治時代)

手燭(しょく)、籠行灯(かごあんどん)などの蝋燭(ろうそく)や油を用いた照明器具は、電灯が広く普及する明治後期までは依然として庶民の生活に用いられていました。

シンガー卓上ミシン
ミシンは、万延元年(1860)に、ジョン万次郎が米国で購入して日本に持ち込んだといわれています。シンガーミシンは、明治33年(1900)に輸入が始まりました。(明治時代)

手燭(しょく)、籠行灯(かごあんどん)などの蝋燭(ろうそく)や油を用いた照明器具は、電灯が広く普及する明治後期までは依然として庶民の生活に用いられていました。

シンガー卓上ミシン
ミシンは、万延元年(1860)に、ジョン万次郎が米国で購入して日本に持ち込んだといわれています。シンガーミシンは、明治33年(1900)に輸入が始まりました。(明治時代)