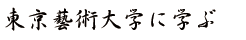絵画科(油画) 坂田哲也教授

静かな石膏室では、学生の絵筆のかすかな音だけがしていました。

美術学部の象徴ともなっている大石膏室では、「再入試」と題された油画の授業が行われていました。林立する石膏像の空間の中で赤・青・黄・緑色のコスチュームを着た女性が、寄り添う、佇む、繰り返す、動く、集合する光景を描くという課題で、学生は5週間を掛けて石膏が置かれた空間と人体の有り様を表現していました。この授業を受けていた学生は、入学試験でも人物の存在する空間を描いており、「再入試」は、学生にとっては再び入学試験の際の緊張感や記憶が蘇るもののようでした。坂田教授のお話では、学生の多くはこれまで静止したものを描いてきているので、この授業は石膏室という空間でそれぞれ異なった動きをしているモデルの姿や絵画表現の基礎となる色彩に着目して、光・色の三原色と人物を組み合わせて描かせる試みであるとの事でした。


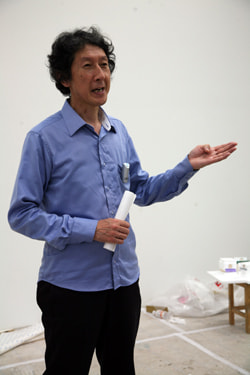
絵画科(油画) 坂口寛敏教授



一方の絵画棟アートスペースでは、授業と展示を組み合わせた実習を行っていました。
指導の坂口教授のお話では「日常─非日常、連続─不連続に関する美術表現」と題して世界の新たな動向を認識しながら、日常のごく身近な事象や個人的な体験からテーマを導き出す課題との事。学生は、台東区の地域バス“めぐりん”を使って藝大の東側に位置する東京スカイツリーを見学し、合羽橋道具街で各々が面白いと感じる物を買い、そして隅田川公園を訪れ建設中のスカイツリーを背景に、買ってきた様々な小物を配して撮影や周辺の取材を行ったとの事でした。翌週は、西側に位置する小石川植物園に行き、ニュートンが万有引力を着想した時のリンゴの木を接ぎ木して育てた木など、世界中の植物をどう育て研究しているかの説明を受けた。この様に藝大が位置する東側、西側でどういう歴史があり今何が行われているかを取材した上で、日常と非日常をどう見て行けばいいのか、学生はそれぞれの手法で表現する。例えば、アニメーションで表現している作品の一つは、電車の中のシーンを二人で描き加えて行き、コマで撮っていく。映像、立体、絵画、色々な表現が出て来て、展示をしながら講評会を行う。学生が非日常性をどう捉えるかがポイント。明治時代以降、非日常性を一括りして、日常から分離させる事で近代化を進めていったが、人びとの夢やそれまでの風習などを非日常としたとき、それが日常の近くにあるということを、もう一度一人一人が再確認する必要がある。(下段に続く)


合羽橋は一般の店よりも発見が多く楽しいし、外国人を連れて行くと喜ばれてさらに良い。面白いと思ったものを風景の中に置いていく事などで、今まで好きな物や気になっていた事、あるいは自然に表現していた事を意識させる。入学試験では、絵画科の学生として確固とした表現のベースを有しているかが試されるが、さらに表現の独自性を持った人を採ろうとすると大変難しい。入学後に認められたいという想いが強いと型にはまってしまう。2年次は、もう一度自分を作り直すための問題点を挙げる時期であるとの事。スケッチによる取材は基本だが、デジタルの情報は手軽なので、最近はデジタルカメラで資料を撮る事も多い。写真に撮った物をドローイングすることに、学生はあまり違和感を覚えないようである。人間の両眼とカメラの単眼との違いは体感させて、描く画材は自由。表現自体が主であり、表現するためのマテリアルに縛りはない。絵画科油画専攻では、絵画表現を前に押し進めるための段階と捉えていて、技法としての油絵には拘っていない。アニメーションは意外かもしれないが、動画は絵がコマになって初めて動くもの。コマとコマの間に非連続の空白があり、目が補う事で物が動くと認識するという事を教えているとの事でした。学生たちの表現は、ドローイング、インスタレーション、写真、ビデオ等を用いたものと自由な表現に溢れていました。

絵画科(版画) 東谷武美教授

ご自身の作品を前に、その技法を語る東谷武美教授

版画研究室には先生の作品の他、版画研究室に関わりの深い小磯 良平、野見山 暁治、小野 忠重、加山 又造、杉全 直、小松崎 邦雄、脇田 和、岡部 徳三の版画作品、そして池田 満寿夫、オディロン・ルドンの作品も掛けられていました。

指導されている東谷教授のお話では、大学院も学部も学生はひとつの部屋で制作しているとの事でした。リトグラフ(石版画・平版)、銅版、木版、シルクスクリーン(孔版)のコースがあり、4つの版種が揃っているのは、日本国内では東京藝術大学のみとの事でした。リトグラフは、本来はリトストーンと呼ばれる石灰石を用いてプリントされるものだが、アルミ板を用いると大きな作品ができるので多用しているとの事。また、最近は版画も大変大きい作品が増えてきたとの事でした。
海外からの留学生も多く、アジアや欧米からの留学生も在籍しているとの事でした。リトストーンは、ドイツとイタリアの地層でしか採れなくて、一枚が40kg程もあって大変重く、一人では到底持てないため、今はアルミ板が主流となっている。リトストーンは砂をかけて研磨して再利用されるとの事でした。用紙は、和紙に拘る学生もいるが、リトグラフに限っては、やはり洋紙の方が刷りやすいとのお話でした。木版画では、水性木版を主にやっている。浮世絵が開発した見当を用いて多色刷りの技法を研究して、現代の木版画を行っている。浮世絵は四六判よりやや横長のサイズで、大きさが決まっている。コンクール等を考え、今の木版は大きなサイズが多いとの事で、バングラデシュから日本の水性木版を学びに来ている学生もいるとの事でした。

リトストーン
リトグラフに用いられる重く大きなリトストーン(石灰石の石版)が、工房には積まれていました。

版画教室
木版やリトグラフの制作に取り組んでいる学生たちは、静かで落ち着いた工房で、制作の手だけが忙しく動いていました。

古い木版画の版木なども所蔵されていて、その技法研究や再生も手掛けられていました。

どの教室にも女性の進出は目覚ましく、女性ならではの細やかな絵柄や描写が表現されていました。

絵画科(油画) 坂田哲也教授

静かな石膏室では、学生の絵筆のかすかな音だけがしていました。
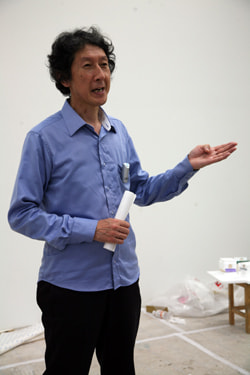
絵画科(油画) 坂口寛敏教授


絵画科(版画) 東谷武美教授

ご自身の作品を前に、その技法を語る東谷武美教授

版画研究室には先生の作品の他、版画研究室に関わりの深い小磯 良平、野見山 暁治、小野 忠重、加山 又造、杉全 直、小松崎 邦雄、脇田 和、岡部 徳三の版画作品、そして池田 満寿夫、オディロン・ルドンの作品も掛けられていました。