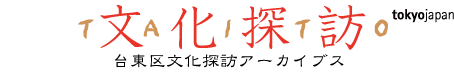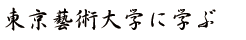保田龍門作「ベートーヴェン像」

ショパン像

山本豊市作「クロイツァー像」
音楽学部、そして美術学部の構内には、著名な音楽家の彫像の他、同学校創設時に貢献した教官等の彫像が多く配されています。
明治23(1890)年に創設された旧東京音楽学校奏楽堂は、建物の老朽化が進み、取り壊しも計画されていましたが、保存運動の末に台東区の協力もあり、昭和59(1984)年に上野公園内に移築されました。現在の東京藝術大学奏楽堂はその跡地に建設され、音響特性を使用目的に応じて変えられるよう、客席の天井全体を可動式にして音響空間を変化させるよう設計されています。舞台にはフランスのガルニエ製オルガンが設置してあります。同奏楽堂は、演奏会の他、同大学の入学式・卒業式にも用いられています。


奏楽堂内には、エラールのダブルアクションハープ(ゴシックスタイル)が保存されていました。このハープは、東京音楽学校、および東京藝術大学音楽学部の初代の専任ハープ教官を務めた阿部よしゑ氏(1904-1969)が第二次大戦中に留学先のパリから持ち帰ったものです。後に阿部よしゑ氏の最後の門下生で卒業生のハーピスト田中恭子氏より同大学に寄贈されました。市川崑監督の代表作「ビルマの竪琴」(1956)では、俳優安井昌二演じる水島上等兵の奏でる竪琴の音は、阿部よしゑ氏によりこのエラールハープで演奏されました。




器楽科(ピアノ) 渡辺健二教授(理事・副学長)
ピアノは一台の楽器で同時に多くの音を出すことが可能であり、ダイナミックレンジも非常に広いため、独奏だけではなく、アンサンブル楽器として、あるいは伴奏楽器として、西洋音楽の基礎になる大変重要な楽器です。また、ピアノ専攻の学生だけではなく、他専攻の学生もその多くが副科としてピアノを学んでいます。在学中に国内外のコンクールやオーディション等で優勝もしくは入賞する者も多く、卒業後にはピアニストとして活動するほか、教育者としても大学などで後進の指導に当たっています。
学生の指導は、個人指導(マンツーマン)で行われますが、ピアノには演奏時間が長い作品も多いので、レッスン時間は一人60分。渡辺教授は火曜と金曜にそれぞれ6名にレッスンしているそうです。戦前或いは戦後しばらくは、西洋の演奏を模範としてそれに倣うということが多かったが、現在ではむしろ、西洋音楽の正統的な理解を基礎としつつも、日本人ならではの感性を活かした、オリジナリティのある演奏が必要であるため、学生の個性を出来るだけ殺さないような指導を心がけているとの事。
日本の西洋音楽の受容は明治時代から本格的に始まったが、当初は和洋合魂の国楽を創作する事、音楽の教育者を育てる事が中心であった。その後、優れた演奏家が生まれるようになり、現在の西洋音楽の興隆があるが、今後は日本人のベートーヴェン、日本人のモーツァルトというものを、もっと世界に向けて発信していくべきだと思っている。コンクールや演奏会で使用されるピアノは、スタインウェイ社製のピアノが多いので、学生に慣れさせるため、レッスンではスタインウェイを弾かせ、練習でも出来るだけスタインウェイを使用させるとの事。また、スタインウェイは演奏者の駄目な点をはっきりと示してくれるので、その意味でも教育的効果が高いとの事でした。
学生の指導は、個人指導(マンツーマン)で行われますが、ピアノには演奏時間が長い作品も多いので、レッスン時間は一人60分。渡辺教授は火曜と金曜にそれぞれ6名にレッスンしているそうです。戦前或いは戦後しばらくは、西洋の演奏を模範としてそれに倣うということが多かったが、現在ではむしろ、西洋音楽の正統的な理解を基礎としつつも、日本人ならではの感性を活かした、オリジナリティのある演奏が必要であるため、学生の個性を出来るだけ殺さないような指導を心がけているとの事。
日本の西洋音楽の受容は明治時代から本格的に始まったが、当初は和洋合魂の国楽を創作する事、音楽の教育者を育てる事が中心であった。その後、優れた演奏家が生まれるようになり、現在の西洋音楽の興隆があるが、今後は日本人のベートーヴェン、日本人のモーツァルトというものを、もっと世界に向けて発信していくべきだと思っている。コンクールや演奏会で使用されるピアノは、スタインウェイ社製のピアノが多いので、学生に慣れさせるため、レッスンではスタインウェイを弾かせ、練習でも出来るだけスタインウェイを使用させるとの事。また、スタインウェイは演奏者の駄目な点をはっきりと示してくれるので、その意味でも教育的効果が高いとの事でした。


保田龍門作「ベートーヴェン像」

ショパン像

山本豊市作「クロイツァー像」
音楽学部、そして美術学部の構内には、著名な音楽家の彫像の他、同学校創設時に貢献した教官等の彫像が多く配されています。