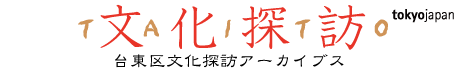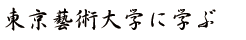伊澤修二胸像
東京音楽学校設立に尽力し、初代校長となった伊澤修二の胸像は、現在、奏楽堂の横にあります。この像は、昭和5(1930)年に創立50周年を記念して、当時の乘杉嘉壽校長の発案で建てられました。当時はこの場所ではなく、東京音楽学校の門を入ってすぐのところに校舎の正面を向いて建てられており、登校時に胸像に一礼して校舎に入る生徒もいたそうです。

音楽学部の前身である東京音楽学校は、明治12年(1879)10月、我が国の音楽教育を実施するに当たっての諸事項を調査するため、文部省に音楽取調掛が置かれた事が始まりです。御用掛には初代の東京音楽学校校長となる伊澤修二が任命されました。翌13年(1880)3月、本郷の文部省用地に取調官署が置かれ、内外音楽の調査をはじめ多くの事業を開始するとともに、東京師範及び東京女子師範の附属小学校、幼稚園生徒に授業を行い、また、取調掛にも伝習人を募集して音楽の授業と教員の養成をはじめました。明治15年(1882)9月以降は、諸外国の音楽学校の制度を調査した上、4年制の音楽専門教育の学制を施行し、取調掛は単に音楽研究の施設であったばかりでなく、我が国最初の近代的な音楽教育機関として成長しました。音楽取調掛は、その後、明治18年(1885)2月には音楽取調所、同年12月に音楽取調掛となり、明治20年(1887)10月に東京音楽学校と改称し、明治23年(1890)5月に西四軒寺跡(現在地)に移転しました。明治26年(1893)からは、一時は東京高等師範学校の附属学校となりましたが、同32年(1899)4月には再び独立し、昭和11年(1936)6月に邦楽科が設置されたのを初めとして、幾度かの制度改革を経て昭和27年(1952)3月に、東京藝術大学として統合されました。東京音楽学校の当初は、4年制の本科(声楽科、器楽科[ピアノ・オルガン・弦楽器・管楽器・打楽器]、作曲科及び邦楽科[能楽・箏曲・長唄])と、4年制の師範科、2年制の研究科(声楽部・器楽部・作曲部・邦楽部)並びに簡易な技能教育を目的とした選科(1-5年以内)からなる専門学校でした。
東京音楽学校の歴史については、「歴史を歩く・旧東京音楽学校奏楽堂を歩く」をご覧下さい。

授業風景、日々の練習にも熱が入ります。


練習ホール館
東京音楽学校存廃論争
明治20年(1887)10月、文部省直轄学校として東京音楽学校が設置され、明治23年(1890)5月には新校舎も落成した。ところがその矢先、同年開院した第一回帝国議会において、音楽学校の廃止案が提出される。予算削減のためであった。東京音楽学校存廃論争の始まりである。学校の存続そのものが問われた、本学の歴史において類を見ない出来事であった。
奏楽堂落成から6ヶ月後の11月29日、第一回帝国議会が開院し、音楽学校では全校を挙げて祝賀演奏会を催した。ところが議会が始まると間もなく、衆議院予算委員会では、予算削減のため高等中学校、女子師範学校とともに東京音楽学校の廃止案が提出された。
東京音楽学校の存廃論争は、工藤行幹議員による「私ハ音楽学校ヲ廃シタイトイフ説ヲ提出致シマス」という発言に始まり、教育上の必要は認めるが、私立学校でできるものを国費で保護する必要はないという意見であった。帝国議会での学校廃止案は新聞各紙で一斉に報じられ、音楽の効用や音楽学校の必要を説いた。明けて1月13日、議会では査定案廃棄の動議、廃止反対意見、そして修正案が提出され、以後、東京音楽学校存廃論争はいっそう白熱する。この間、伊澤修二、神津專三郎ら学校関係者や辻新次文部次官などが音楽学校の必要を説く論述を展開した。これより先、衆議院は特別委員9名を選出し予算案再審査を附託していたが、その一人天野爲之議員が自分を含む特別委員3名は学校廃止に反対であると報告。2月21日、諸学校は天野議員らによる修正案で存続決定、衆議院は3月3日を以て特別委員の提出した修正案を可決した。3月に入ると議員の音楽学校参観が行われた。伊澤校長は演奏曲目を自ら解説し、唱歌編纂事業などにおける音楽学校の役割を強調し、唱歌は徳性を涵養し健康に益し愛国の信条を育てるという演説を行った。
存続決定後も音楽学校論は盛んに発表された。「猶努めよ」「時来れり」「唱歌論」「音楽の必要」「音楽は国家事業なり」など音楽学校への期待を表明するものが相次いだ。しかしその一方で経費節減を求める声も止まず、東京音楽学校は明治26(1893)年9月から高等師範学校附属音楽学校となり、明治32(1899)年4月に再独立するまで5年半を要することとなる。(東京藝術大学広報誌「藝大通信第12号」より)

伊澤修二胸像
東京音楽学校設立に尽力し、初代校長となった伊澤修二の胸像は、現在、奏楽堂の横にあります。この像は、昭和5(1930)年に創立50周年を記念して、当時の乘杉嘉壽校長の発案で建てられました。当時はこの場所ではなく、東京音楽学校の門を入ってすぐのところに校舎の正面を向いて建てられており、登校時に胸像に一礼して校舎に入る生徒もいたそうです。
東京音楽学校存廃論争
明治20年(1887)10月、文部省直轄学校として東京音楽学校が設置され、明治23年(1890)5月には新校舎も落成した。ところがその矢先、同年開院した第一回帝国議会において、音楽学校の廃止案が提出される。予算削減のためであった。東京音楽学校存廃論争の始まりである。学校の存続そのものが問われた、本学の歴史において類を見ない出来事であった。
奏楽堂落成から6ヶ月後の11月29日、第一回帝国議会が開院し、音楽学校では全校を挙げて祝賀演奏会を催した。ところが議会が始まると間もなく、衆議院予算委員会では、予算削減のため高等中学校、女子師範学校とともに東京音楽学校の廃止案が提出された。
東京音楽学校の存廃論争は、工藤行幹議員による「私ハ音楽学校ヲ廃シタイトイフ説ヲ提出致シマス」という発言に始まり、教育上の必要は認めるが、私立学校でできるものを国費で保護する必要はないという意見であった。帝国議会での学校廃止案は新聞各紙で一斉に報じられ、音楽の効用や音楽学校の必要を説いた。明けて1月13日、議会では査定案廃棄の動議、廃止反対意見、そして修正案が提出され、以後、東京音楽学校存廃論争はいっそう白熱する。この間、伊澤修二、神津專三郎ら学校関係者や辻新次文部次官などが音楽学校の必要を説く論述を展開した。これより先、衆議院は特別委員9名を選出し予算案再審査を附託していたが、その一人天野爲之議員が自分を含む特別委員3名は学校廃止に反対であると報告。2月21日、諸学校は天野議員らによる修正案で存続決定、衆議院は3月3日を以て特別委員の提出した修正案を可決した。3月に入ると議員の音楽学校参観が行われた。伊澤校長は演奏曲目を自ら解説し、唱歌編纂事業などにおける音楽学校の役割を強調し、唱歌は徳性を涵養し健康に益し愛国の信条を育てるという演説を行った。
存続決定後も音楽学校論は盛んに発表された。「猶努めよ」「時来れり」「唱歌論」「音楽の必要」「音楽は国家事業なり」など音楽学校への期待を表明するものが相次いだ。しかしその一方で経費節減を求める声も止まず、東京音楽学校は明治26(1893)年9月から高等師範学校附属音楽学校となり、明治32(1899)年4月に再独立するまで5年半を要することとなる。(東京藝術大学広報誌「藝大通信第12号」より)