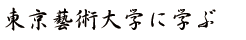器楽科(弦楽) 河野文昭教授

間近で聞かせて頂いたチェロの音は、深くなめらかな音色を湛えていました。

河野教授のお話では、藝大の前身である東京音楽学校は、欧米の文化の取り入れとともに、西洋音楽を教育の中心に置き、日本からも優秀な音楽家を輩出しようという意識から明治時代に創立された。21世紀になり、西洋音楽と世界各国の音楽(日本では邦楽、インドネシアではガムラン等)を対等の立場で見ていこうという新しい流れが出て来た。その意味で独自の伝統音楽を持つ日本人が、どのように自分達のアイデンティティを見出し、その上で再現芸術家としての演奏家がクラシック音楽の世界でどのような表現を生み出していくのか、という意識を持つことが大切である。弦楽科のレッスンの基本は個人レッスンである。平常授業の内容をもとに、前期はクラス内の発表会での演奏や、後期は学内試験などを重視して成績が付けられる。またゼミナール形式で他の学生達の前で演奏をさせ、批評し合うことで学生個々の考えを深める授業や、室内楽、弦楽合奏、オーケストラ等の授業を通して、日々アンサンブル能力の向上にも力を入れている。
現在は海外で活躍する教員が増え、欧米にも引けを取らない授業内容となっており、アジアから藝大に留学して本格的な西洋音楽を勉強するというケースが増えてきているとの事でした。
現在は海外で活躍する教員が増え、欧米にも引けを取らない授業内容となっており、アジアから藝大に留学して本格的な西洋音楽を勉強するというケースが増えてきているとの事でした。

邦楽科(能楽) 関根知孝教授

関根教授のお話では、能は、目に映るもの・心に浮かぶものを、我が身をもって表現する芸で、若い人の芸は強く硬すぎる位がよく、年齢を重ねつつこなれてゆくものだそうです。柔らかく人情のある曲は経験を積みながら体得していくものだが、また、舞台の底知れない深さ、目に見えない存在感を、子供や若い歳のうちに骨の髄で感じ取れるといいとの事でした。さらに、漆黒の黒さに味は乏しく、多くの色を塗り重ね、かそけく黒い、という意味の「幽玄」は、強さとは矛盾しない。粗い芸、弱く格の無い芸はいけない。「芸は盗むもの」と言われる通り、言葉で与えられた芸は借り物でしかない。自分の目で見て、肌で感じ取ることが一番の近道との事でした。今は家元系以外の学生も邦楽科に多く入学してきており、文部科学省が伝統芸能や音楽に力を入れているので、今後はますます層が厚くなるのではとの事でした。授業の合間に伺いましたが、能舞台が設えられた音楽ホールでは静謐で大変厳しい空気が漂っていました。正に手取り、足取りで、一舞い、一舞い毎に厳しさにも細やかな指導と声が響いていました。
関根教授は、同大学邦楽科卒業後に観世流二十五世宗家観世左近氏に内弟子入門され、シテ方として活躍され、同大学では非常勤講師として昭和59(1984)年から教鞭を執られているとの事でした。国内をはじめとして海外での公演や指導にも尽力されているとの事でした。(下段に続く)
関根教授は、同大学邦楽科卒業後に観世流二十五世宗家観世左近氏に内弟子入門され、シテ方として活躍され、同大学では非常勤講師として昭和59(1984)年から教鞭を執られているとの事でした。国内をはじめとして海外での公演や指導にも尽力されているとの事でした。(下段に続く)

舞は、源氏物語「玉鬘」の終局

能にも新作は様々あるが、古典だけを教授しているとの事。今日では、能舞台の体裁やリズム、メロディも多少変わっていますが、能面、面(おもて)やことば、詞章は変わらずに600年間受け継がれてきたもので、自分なりの解釈は許されない。能においては、まず古典を覚える事から始まり、四十代、五十代までも我慢して古典を一通り学んだ後の六十代、七十代になってようやく表す事ができるようになる。一般に、男の場合は、素顔で出て来ておかしくない時には直面(ひためん)という面を掛けないで演じるが、女や鬼、神様の役の場合には面が用いられる。能面を掛け装束を着けた正式の演技の他には、仕舞(しまい)として、3分とか5分程度のさわりの部分のみを演技する事もある。能舞台の4本の柱には大変重要な意味があり、足が近づき過ぎると自身が弱く見え、ある程度の距離まで近づくと良い緊張感となり、またあまり内輪だけで舞うと引き締まらない。(下段に続く)


また所作は型が決まっており、左足から出て左足で止まる。右で止まっておいて捕まえたものを後ろにひきこむというように、右足は特に中途半端な型になり、また意味がある。それが自然の流れの中での法則となり、体系化されている。能には五流があり、中には女性の演者を認めないという流派もある。観世流は認めているが、男性に比べると舞台数のチャンスが少なく、よほど熱心にしないと男性と肩を並べるところまでなかなかたどり着けない。能の五流のうち、同大学では観世流と宝生流が教授されていて、囃子(はやし)の専門課程、ワキや狂言の専門課程が、それぞれ一つずつ設けられているとの事でした。

器楽科(弦楽) 河野文昭教授

間近で聞かせて頂いたチェロの音は、深くなめらかな音色を湛えていました。

邦楽科(能楽) 関根知孝教授